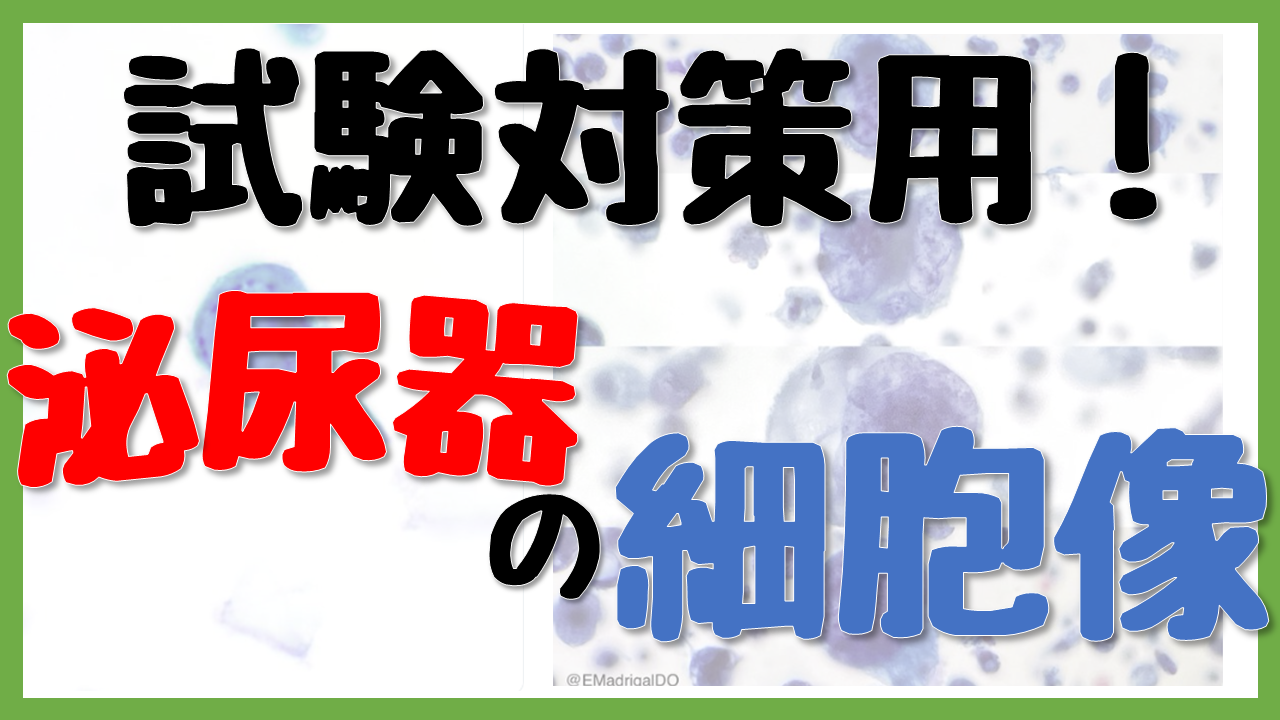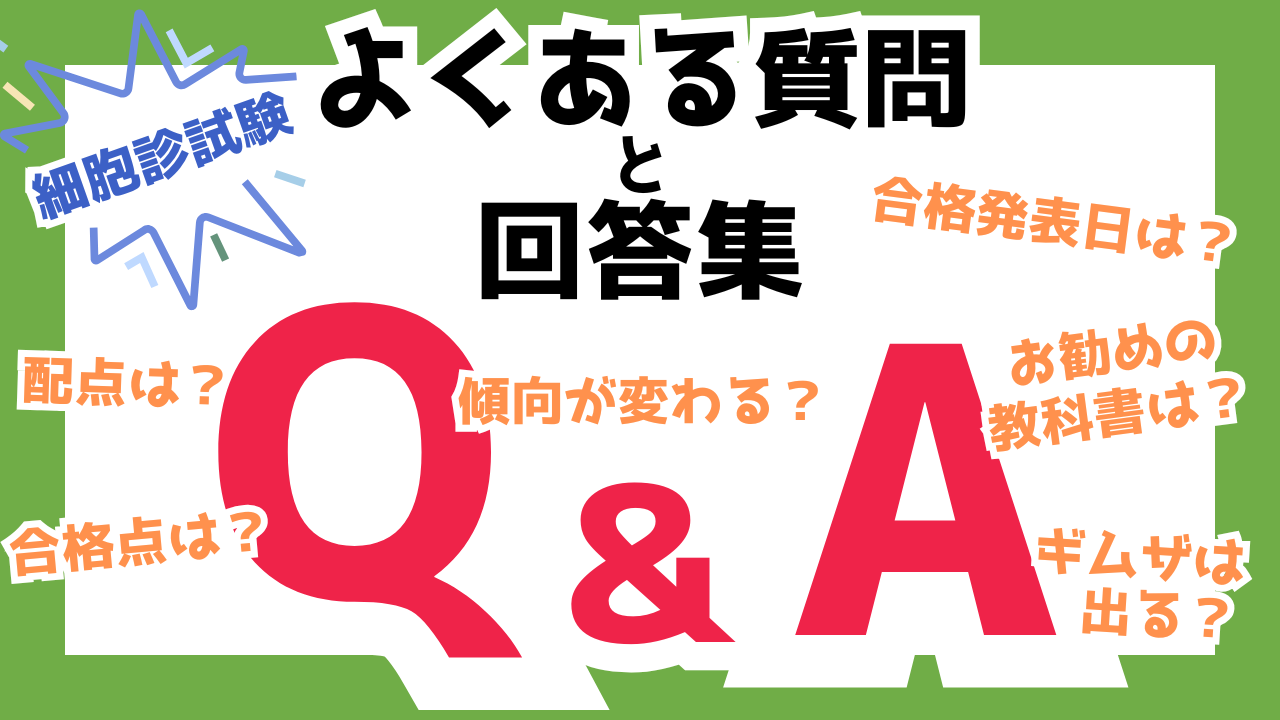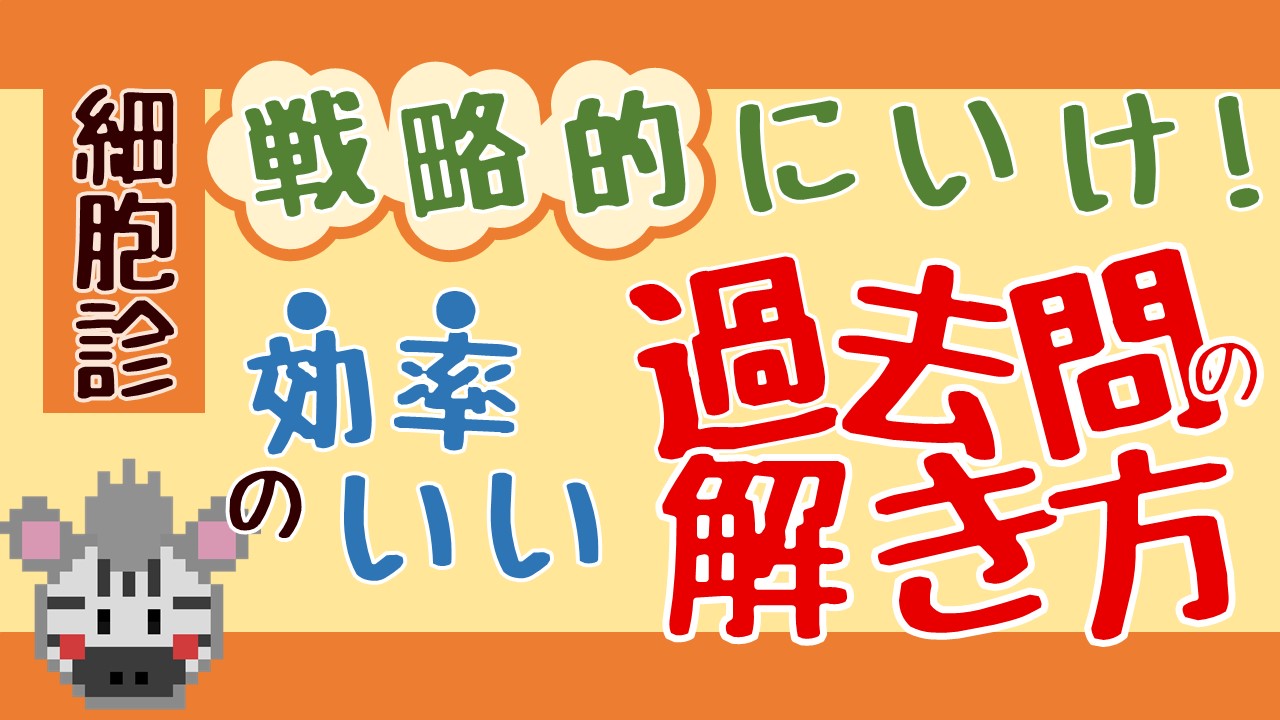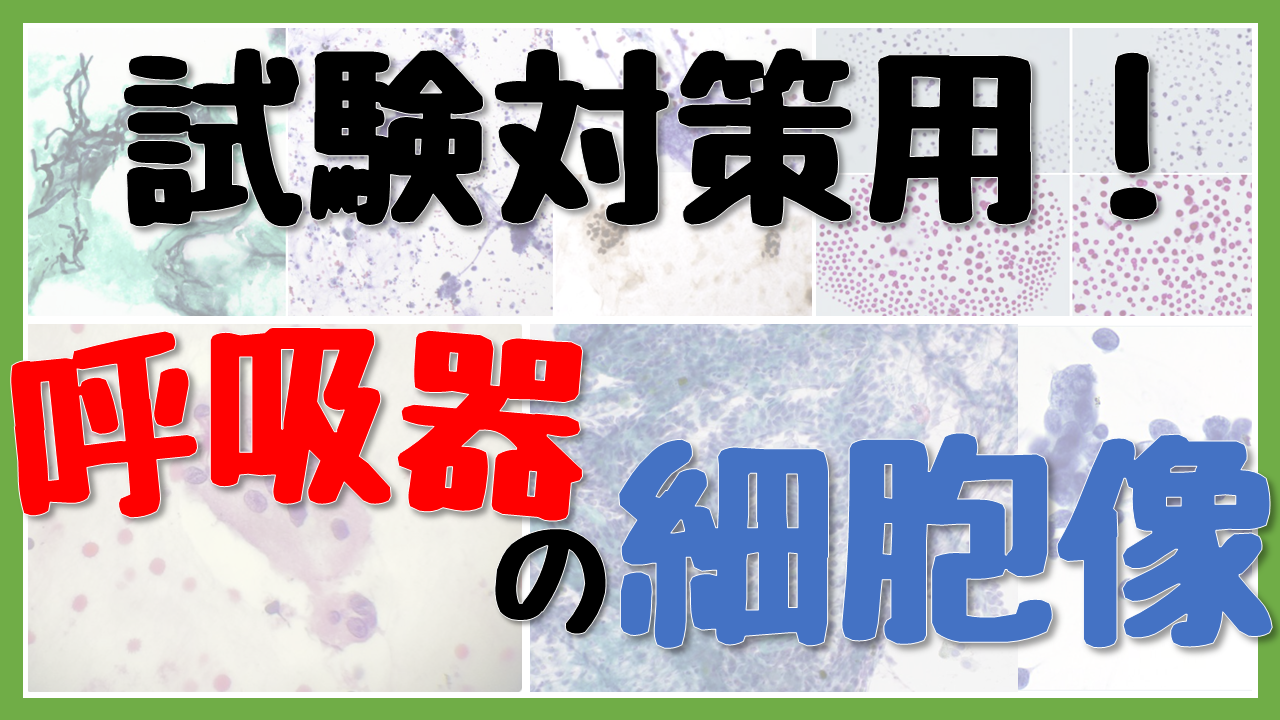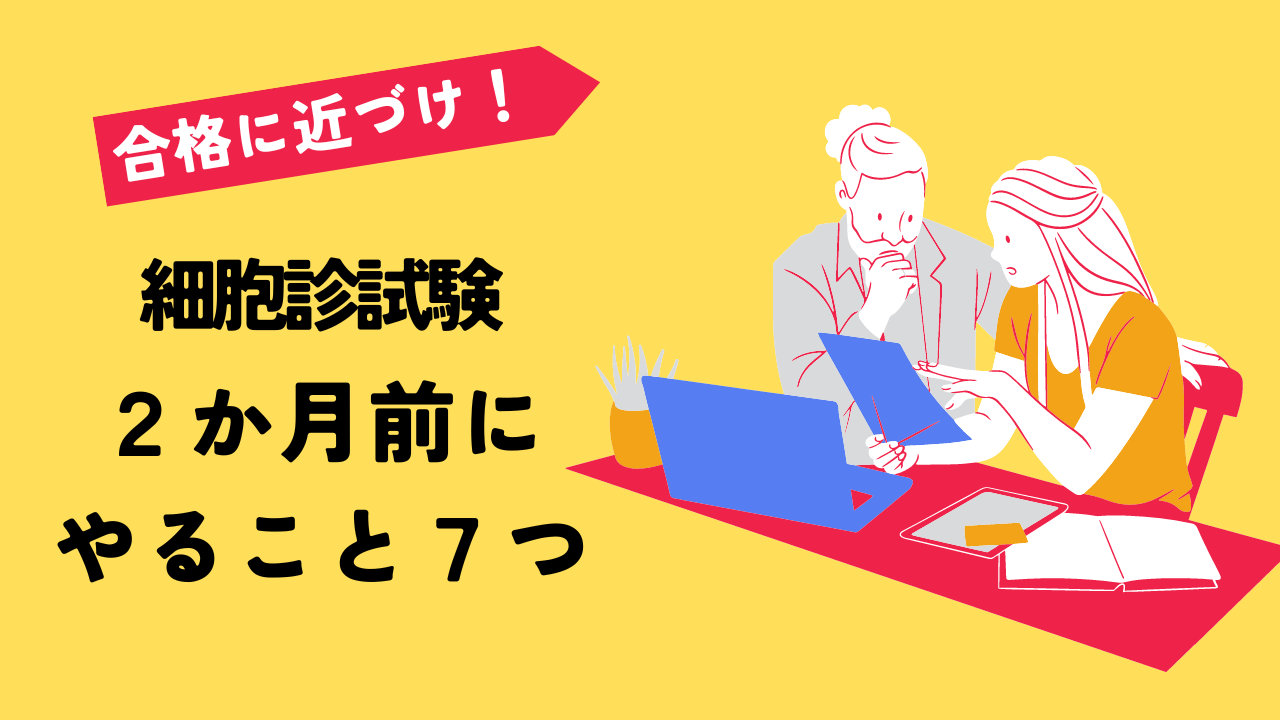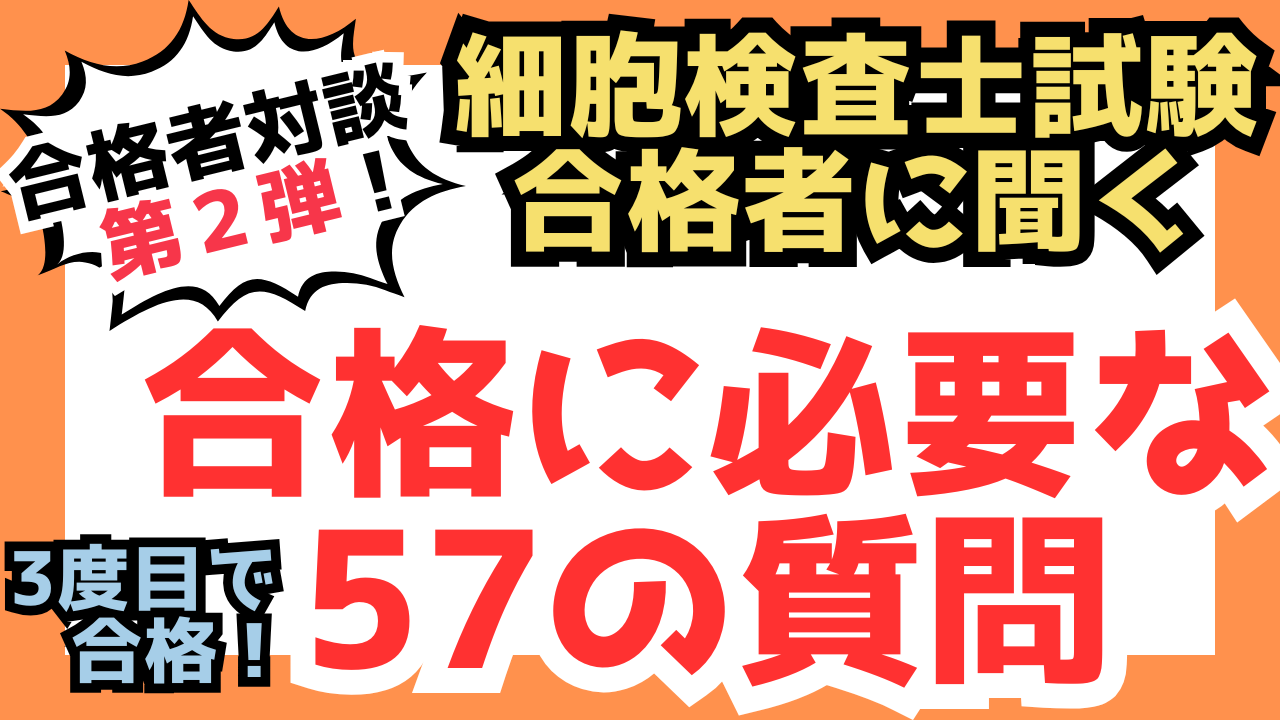【細胞検査士合格者体験談】第1弾!(動画あり)

今回は2024年度の試験に合格したYさんにインタビューをさせて頂きました。
参考になる部分ばかりなのでぜひご覧ください!
- 性別:男性
- 受験回数:4回
- 1回目:一次不合格
- 2回目:一次合格、二次不合格
- 3回目:一次免除、二次不合格
- 4回目:一次合格、二次合格
- 平日の勉強時間:2時間
職場環境や受験のきっかけ
- 細胞検査士の試験を受験することになった経緯を教えてください。
-
元々検査技師の勉強をする中で形態学に興味を持ち、細胞診が楽しそうだと思ったのがきっかけです。職場でも細胞検査士の資格はほぼ必須で、取得するようにというプレッシャーもありましたが、自分自身が「取りたい」という気持ちが大きかったため、受験を決意しました
- 職場で細胞検査士の資格取得は必須ですか?
-
はい、職場は絶対取らないとまずいです。ただ、気持ちとしては職場からのプレッシャーによる受験というより自分自身が「取りたい」という気持ちが大きかったため、受験を決意しました
- もし取らなくてもいい場合は受験しなかったですか?
-
絶対取ってました。
- 一次試験と二次試験はそれぞれ何回受験されましたか?
-
合計で4回受験しました。
1回目は一次試験で不合格、2回目は一次試験は合格しましたが二次試験で不合格、3回目は一次試験免除で二次試験不合格、4回目で一次・二次ともに合格することができました。
勉強法について
勉強のすすめ方
- 本格的に受験勉強を始めたのはいつ頃からですか?
-
1回目の試験の約半年前、受験する年の3月頃から始めました。でも全く間に合いませんでした。
- 初回受験で不合格になった原因は何だと思いますか?
-
1回目はほぼ独学で勉強し、過去問の答えとその周辺だけを覚えて深く掘り下げずに試験に臨んでしまったことが原因だと思います。あとは情報が手に入らず、自分で過去問の答えを一から作っていたため、間に合いませんでした。
- 過去問の解答作成はいつくらいに完成しましたか?
-
8月くらいに5年分が完成しました。そこから覚え始めたので無理ですよね。
- 2回目の受験時はいつ頃からどのように勉強しましたか?
-
落ちた年の12月に勉強を始めました。1回目の受験で規約も見ないとダメだと思って規約も使って勉強し始めました。呼吸器の置換型とかの問題が出てきて置換型って何?ってなりました。その時にぜぶら先生のYoutube解説を見つけてYoutubeを見て勉強するようになりました。
Youtubeを見てこんなに深く勉強しないといけないのかと思って、知識の広げ方が特に参考になりました。
- 具体的な目標やスケジュール設定は行いましたか?
-
筆記試験に関しては、「7月の終わりまでに過去問5年分で9割正解できる状態にする」という目標で勉強していました。5年分全てで9割というのは、かなり大変でした。
- なぜ7月末までに筆記試験の目標を達成しようと考えたのですか?
-
8月からは2次試験(鏡検)の対策に本格的に取り組まないと間に合わないと思って。8月から始めても本番まで4ヶ月しかないので、それまでに筆記は仕上げておく必要がありました。
- 2次試験(鏡検)の対策はいつから始めていましたか?
-
4月から8月までの期間、毎週土日のどちらかは必ず標本を見る日と決めて鏡検しました。土日のうち1日は「標本を見る日」に固定し、もう1日は「筆記の勉強をする日」または「気分転換で休む日」としていました。
- 筆記試験の勉強は主にどこで行っていましたか?また、自宅以外の場所で勉強することはありましたか?
-
主に自宅です。私の場合はカフェなどに行くと周りの人が気になってしまい、全く集中できなかったので、勉強は自宅か職場で行うようにしていました。
- 自宅で集中して勉強できないという意見をもらうことがあるのですが、Yさんとしてははどうすれば良いと思いますか?
-
もし可能であれば職場を利用するのが良いかもしれません。顕微鏡も見れますし。
- 勉強する中で、特に苦手だった分野はありましたか?また、克服法はありますか?
-
「免疫染色(免染)」と「リンパ腫」が最後まで苦手でした。
免染は「内因性ビオチンがどう影響するか」など染色原理に関する部分がややこしく、覚えるのに苦労しました。免染はぜぶら先生の解説ブログの記事を印刷して、それを何度も読み込んで覚えました。非常に重宝しました。
リンパ腫は低悪性度と高悪性度や細胞所見などそれぞれの特徴が似ていて区別するのが難しかったです。これはとにかくアウトプットを繰り返しました。ルーズリーフにひたすら殴り書きしたり、特徴を箇条書きで書き出したりして、それをずっと眺めて覚えました。
- 勉強法の中で、特に「これは効果があった」と感じるものは何ですか?
-
【どっと本】細胞診過去問解説集を全て印刷して、紙媒体で勉強したことです。なかなか覚えられない問題の正しい答えに線を引いて余白ページに要点を殴り書きしながら覚えていきました。
- 勉強は全て紙媒体で行いましたか?
-
デジタル教材と使い分けていました。自宅の机に向かって、集中してがっつり勉強する時は紙を使って、 通勤途中や昼休みなどの隙間時間はデジタル教材を使いました。
- 隙間時間には、具体的にどのような勉強をしていましたか?
-
「今日の昼休みは呼吸器の解剖だけ覚えよう」みたいにテーマを絞り、携帯で教材を見ながら勉強していました。ご飯を食べに行って料理が出てくるまでの待ち時間なども活用していました。
- 「紙」と「デジタル」を使い分ける方法はおすすめできますか?
-
はい、非常に効果的で良い方法だったと感じています。集中して取り組む時間と隙間時間でツールを使い分けるのはかなりおすすめです。
- 過去問解説集はいつから使い始めましたか?
-
4回目の受験の時からです。2回目と3回目の受験時はYouTubeの解説動画をメインに勉強していました。もっと早くこの教材を知っていれば、1回目の不合格はなかったかもしれないと感じています。
- YouTubeの解説動画と、文字ベースの教材では違いを感じましたか?
-
い、全く違いました。私にとっては、以下のような使い分けが最適でした。
- YouTube(動画): 学校の講義を受けるような感覚で、すっと頭に入ってくる。
- 文字ベースの教材: 自分で能動的に勉強している感覚。深くやり込むのに向いている。 最終的には、文字ベースの教材で勉強し、理解できない部分を動画で補うという形で活用していました。
- なぜ2次試験(鏡検)の対策はもっと早くから始めるべきだったと感じるのですか?
-
1次試験が終わってからでは、対策の時間が全く足りないからです。鏡検のスキル習得は時間がかかるため、4月や5月の連休明け頃から、1次試験の勉強と並行してコツコツと標本を見ておくべきだったと痛感しています。
- 鏡検のスキル習得で時間がかかる点はどのような点だと思いますか?
-
異常な細胞を「見つける(ピックアップする)」だけでは不十分で、その細胞を「何に分類するか(マイルド・モデレート・シビアなど)」を判断できるようになるまでに、時間がかかりました。ピックアップまでは比較的すぐにできるようになりますが、そこからの壁を越えるのに苦労しました。
- 1次試験と2次試験の勉強を並行して行うメリットは何ですか?
-
知識が結びつき、相乗効果が生まれることです。例えば、筆記試験で「反応性中皮細胞の特徴」を文字だけで覚えようとすると大変ですが、実際に鏡検で細胞像を見ていれば、「ああ、あの細胞のことか」とイメージしながら覚えられるため、理解が格段に深まります。
- 「これはやっておいて本当に良かった」と思うことは何ですか?
-
やはり「細胞診過去問解説集」です。
- 他にやっておいて良かったことはありますか?
-
過去に出題された問題をまとめた資料(2次試験で出やすいものなど)を読んだことです。これにより、「試験ではどういうことが問われるのか」という全体像や傾向を掴むことができ、「これだけ覚えればいいんだ」と的を絞って勉強できました。闇雲に手を広げすぎず、まず基本的なことをしっかり理解することが重要だと感じました。
使用教材
- 筆記試験の対策で、メインで使っていた教材は何ですか?
-
【どっと本】細胞診過去問解説集を使ってました。この教材を徹底的にやり込みました。本当にありがたかったですね。
- 教科書のような、メインとなるテキストは使っていましたか?
-
「スタンダード細胞診テキスト」を使用していました。主に勉強の序盤で、細胞診の全体像を掴むために使用しました。あくまで全体を理解するために使いました。
- 知識を深めるためには、どの教材を使っていましたか?
-
過去問が中心でした。全体像を「スタンダード細胞診テキスト」で確認した後は、ひたすら過去問を解いて知識を深掘りしていくというスタイルでした。
- 「スタンダード細胞診テキスト」は出版が2018年と少し古いですが、規約の古さなどは気になりませんでしたか?
-
気になりませんでした。私の勉強法が「過去問中心」で「スタンダード細胞診テキスト」はあくまで勉強初期に全体像を掴むためだけに使っていたので、細かな規約の更新などはそこまで気になりませんでした。
- 一次試験の細胞像は、どの教材で対策しましたか?
-
「細胞像試験問題集(第2版)」を使用していました。選択肢を見なくても、写真を見ただけで疾患名が即答できるレベルになるまで、繰り返し解いて答えは覚えてしまってました。その対策として問題集を逆さまにして1ページ目から解き直してました。
- 問題集を逆さまにする勉強法は効果を感じましたか?
-
非常に効果がありました。同じ画像のはずなのに、向きを変えるだけで全く違う問題のように見え、新鮮な気持ちで取り組むことができました。細胞像の勉強法として、個人的にとても好きなやり方でした。
二次試験について(勉強法を含む)
- 二次試験対策はどのようことを行いましたか?
-
ひたすら陰性の標本(正常な細胞像)を見ました。まず正常を覚えた上で、悪性細胞を見始めるようにしました。
- 標本は職場にたくさんありましたか?
-
婦人科のLBC標本は比較的たくさんありました。他にも先輩方が昔の標本を教育用に揃えてくれていて、それをひたすら見ました。
- 軟部腫瘍などの希少例はありましたか?
-
全くなかったです。その辺の分野は鏡検の代わりに画像問題を見て練習しました。
- 2次試験のスクリーニングは、時間に余裕はありましたか?
-
時間はカツカツで余裕は全くありませんでした。
モチベーションについて
- 4年間という長丁場の受験勉強で、モチベーションを維持するのは難しかったですか?
-
非常に難しくて、2年目あたりで心が折れそうになりました。でも「せっかく勉強を始めたのだから、途中でやめたらもったいない」「ここで諦めたら一生後悔する」「自分が好きな分野を勉強できている」と考えることで、頑張ることができました。
- 受験勉強で、精神的に一番きつかったのはどのような点ですか?
-
二次試験(鏡検)の「どこまで勉強すれば合格できるのか、ゴールが見えない」という点です。勉強をやったらやった分だけ必ず合格できるという確証がないため、常に大きな不安感がありました。
- 後輩や同僚に先に合格されてしまった時、焦りはありませんでしたか?
-
はい、ものすごく焦りました。実際に後輩が一発で合格した時は、「どうしよう」と強く思いました。その時は「試験の合否」という結果から、「細胞を見る経験を積む」という本質に考え方を切り替えました。「合格していても不合格でも、標本を見れば見るだけ自分の経験と知識は増えていく。日頃見られない希少例を見るチャンスでもある」と考え、とにかく目の前の細胞から学ぶことに集中しました。
- 試験の合否にこだわりすぎない、という考え方が重要ってことですかね。
-
はい。「資格を持っているか」よりも「細胞を見れる技術があるか」が本質だと考えました。「甲状腺の細胞なら誰よりも多く見てきた」というように、自分の経験値に自信を持つことで、合否とは少し距離を置いて勉強に取り組むことができました。
- 周囲からの「合格してほしい」という期待がプレッシャーになる時はどうすれば良いですか?
-
非常に難しい問題ですが、「試験の合格も大事だが、細胞を正確に見れるようになることが本質だ」と考えることが一つの解決策かもしれません。合格という結果だけに囚われず、日々の勉強で得られる知識や経験の蓄積に目を向けることで、プレッシャーを少し和らげることができるかもしれません。
- とはいえ、やはり「合格したい」という気持ちは強いですよね?
-
もちろんです。そのために勉強しているので、「合格したい」という気持ちは一番にあります。一発で合格できれば最高なのも間違いありません。その気持ちと長期戦を戦い抜くための精神的なバランスを取ることが、この試験の難しいところだと思います。
- 仕事終わりで疲れてしまい、勉強できない時はどうしていましたか?
-
無理せず、すぐに寝ていました。きつい時に勉強しようとしても、どうせ頭に入らないので、気持ちを切り替えて休むようにしていました。オンとオフのメリハリをつけることが非常に大事だと考えています。
- 勉強が嫌になったり、やる気が出ない時はどうしていましたか?
-
「今週の土日は全く勉強しない」というように、思い切って休みの日を作っていました。自分にご褒美を与えながらでないと、この試験の長期的な勉強は身が持たないと思います。
- この試験は、精神的な負担も大きいと感じますか?
-
はい、非常に大きいと思います。特に働きながら勉強する社会人の受験者にとっては、勉強内容そのものよりも、精神的なコンディションを維持することの方が大変かもしれません。
試験当日の話
- 受験回数を重ねるごとに、試験前の緊張感は増しましたか?
-
はい、増していきました。試験の1週間前は緊張で眠れないほどでした。「また不合格だったらどうしよう」という不安と、「また1年間この勉強をしなければならない」という恐怖で、回数を重ねるごとにプレッシャーは大きくなりました。
- 試験前の強い緊張感には、どのように対処していましたか?
-
主に2つの方法で対処していました。
- SNS(Xなど)を見る: 自分と同じように「今週試験だ」と投稿している人たちを見て、「みんな同じように緊張しているんだ」と思うことで、自分だけではないと感じられ、少し気持ちが楽になりました。
- オンラインの交流グループに参加する: ぜぶら先生が作ってくれた試験前の集まりみたいなやつあったじゃないですか。そこで受験者同士で答え合わせをしたり、情報交換をしたりすることで、孤独感が薄れ、緊張が紛れました。仲間がいると感じられる場は、精神的に非常にありがたかったです。
試験合格時の話
- 4回目の1次試験と2時試験が終わった直後の手応えはどうでしたか?
-
1次試験は「割とできたな」という感触で、自信がありました。2次試験は「絶対に落ちた。もうこの試験は一生受からない」と思うほど、全く手応えがありませんでした。精神的に立ち直れないほどの感覚でした。
- 「絶対に落ちた。もうこの試験は一生受からない」と思うほど、全く手応えがありませんでした。精神的に立ち直れないほどの感覚でした。
-
はい、全く逆でした。不合格だった年(3回目)は「絶対に受かった」と強い自信があったのですが、結果は不合格でした。逆に、合格した年(4回目)は「絶対に落ちた」と思っていたのに、結果は合格でした。
- 受験者の「手応え」は、あまり当てにならないと感じますか?
-
当てにならないと思います。SNSなどで毎年「今年の試験は難化した」という声が上がりますが、それもあまり当てにならないかもしれません。
- 不合格だった時、職場の人の反応はどうでしたか?
-
皆さん非常に優しかったです。「大丈夫だよ」と温かく接してくれました。周りの人は、自分が頑張っている過程を知ってくれているので、結果がどうであれ、意外と気にしていないものだと感じました。
- 合格発表はどのように確認しましたか?
-
自分一人で見る勇気がなかったので、職場の上司と一緒に見てもらいました。
- 自分の受験番号を見つけた瞬間、どのような気持ちでしたか?
-
「100%不合格だ」と思い込んでいたので、自分の番号を見つけた時は「嬉しい」という感情よりも先に、「何であるんだろう?何かの間違いかな?」という気持ちが来ました。
- 合格を実感したのはいつ頃ですか?
-
しばらくは複雑な気持ちでしたが、「これで4年間の長い戦いが終わったんだ」という安堵感と、周りの期待に応えられたという喜びが徐々に湧いてきました。お世話になった方に「合格できました」と報告できた時が、一番「やっと終わった」と実感できた瞬間です。
試験合格後の話
- 実際の試験で、何か想定外の出来事や印象に残っていることはありましたか?
-
特に想定外のことはありませんでした。問題に多少難しいものはありましたが、試験の形式や流れは基本的に「思っていた通りだな」という感じでした。
- なぜ模擬試験を解くことが有効なのですか?
-
新しい問題に触れることで、脳が刺激され、知識を思い出す作業(アウトプット)と新しい知識を入れる作業(インプット)が同時にできるからです。過去問ばかりだと飽きてしまうので、新しい問題で実践的な練習を積むことは非常に良い手法だと考えます。
- 資格を取得して、何か心境や職場での変化はありましたか?
-
一番大きな変化は、念願だった細胞診の業務に就けたことです。
- 実際に細胞診の業務に就いてみて、どう感じていますか?
-
とても楽しいです。試験勉強とはまた違う難しさがありますが、自分が本当にやりたかった好きな仕事ができるのが、何よりも嬉しいです。資格を取って一番良かったと強く感じる点です。
フォロワーさんからの質問
- 2次試験対策で、職場に標本が少なく希少症例が見られません。そういったものも対策すべきでしょうか?
-
対策はしておくべきですが、優先順位が重要です。私は婦人科・呼吸器・体腔液という主要分野を標本で重点的に見て、同定でしか出ないような希少例は写真(問題集など)で勉強していました。まずは配点の高いメインどころから固めるべきで、骨肉腫のような希少例にだけ時間を使いすぎるのはもったいないかもしれません。
- 標本を1枚見るのに6分かかってしまいます。早く見れるようになるコツはありますか?
-
とにかく「数をこなすこと」だと思います。私も最初は10分くらいかかっていましたが、多くの標本を見ていくうちに、「これはじっくり見なくていい細胞だ」という判断が瞬時にできるようになり、自然とスピードは上がっていきます。まずは量を見て、質は後からついてくると考えるのが良いと思います。
- 1日にどれくらいの枚数の標本を見ていましたか?
-
平日は20枚程度、休日に集中して見る時は100枚近く見ていました。100枚見るのは本当に大変でヘトヘトになりますが、その苦しい経験も含めて、試験本番で力を発揮するための鍛錬になったと感じています。
- 働きながら勉強するにあたり、平日の勉強時間はどれくらいでしたか?
-
仕事から帰宅後、21時頃から2時間ほど筆記の勉強をしていました。それが限界だと思います。社会人が毎日長時間を確保するのは現実的ではないかなと思います。体を壊さないよう、無理のない範囲で継続することが大切だと痛感しました。
- 2次試験で使われる顕微鏡は、席によって性能が異なりますか?
-
わかりません。私は二次試験を3回受験しましたが、違いは全く分かりませんでした。オリンパス社製とニコン社製の両方に当たりましたが、特に差は感じなかったので、気にする必要はないと思います。
これから受験する方へ
- これから受験する方へメッセージをお願いします!
-
まずは体を壊さないよう、健康に気をつけながら勉強を続けてください。一度で受かろうと気負いすぎず、自分のペースを守ることが大切です。(もちろん一度で受かればそれが一番ですが。)合格すると本当に気持ちがいい試験なので、応援しています。ぜひ、ぜぶら先生を頼ってください!