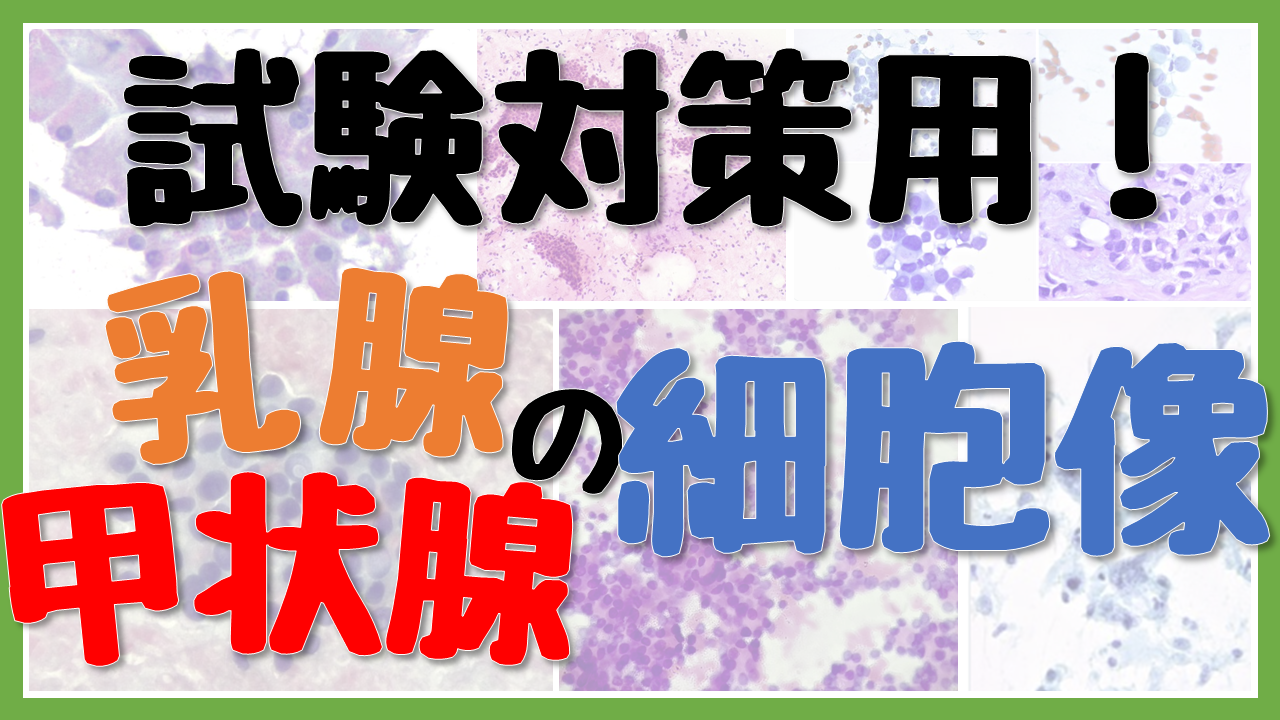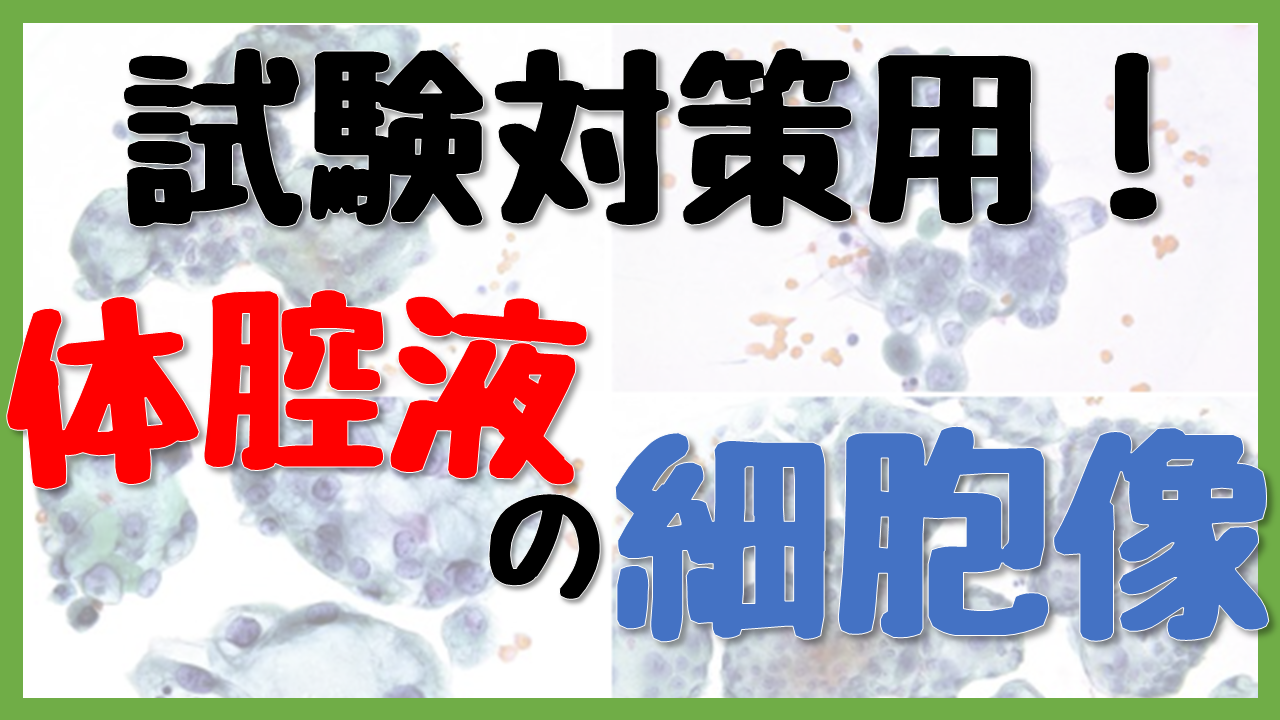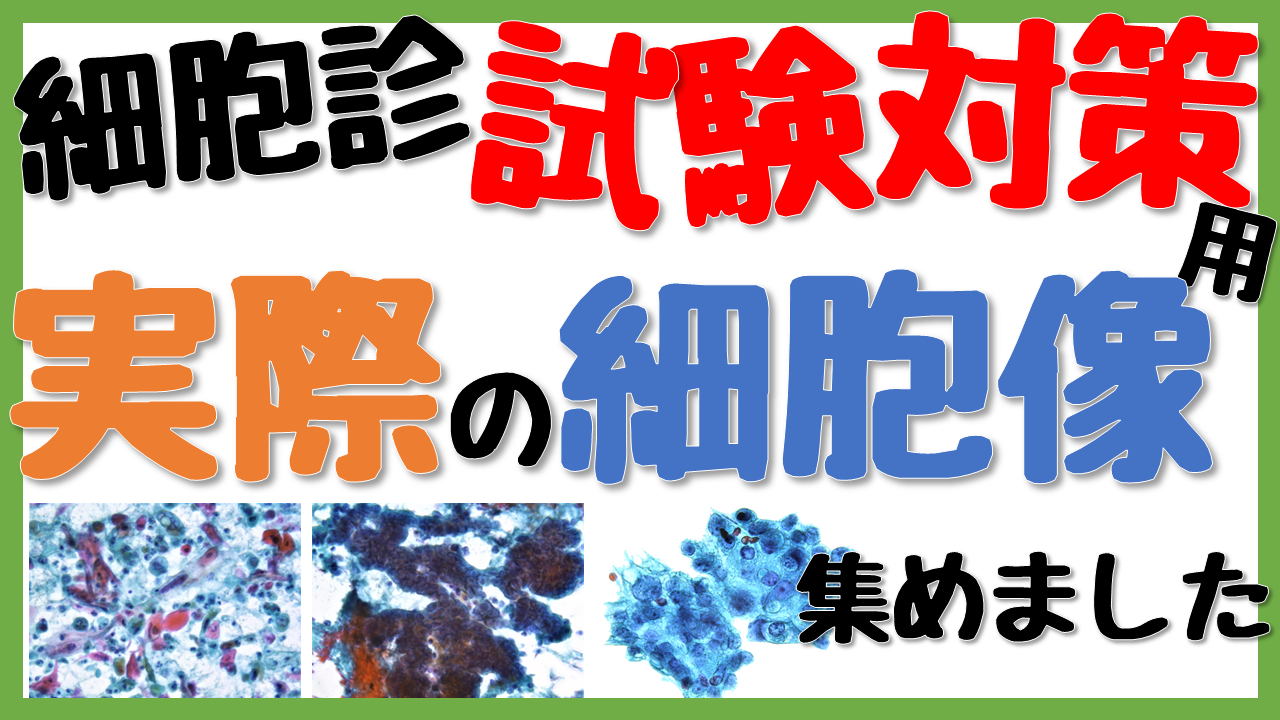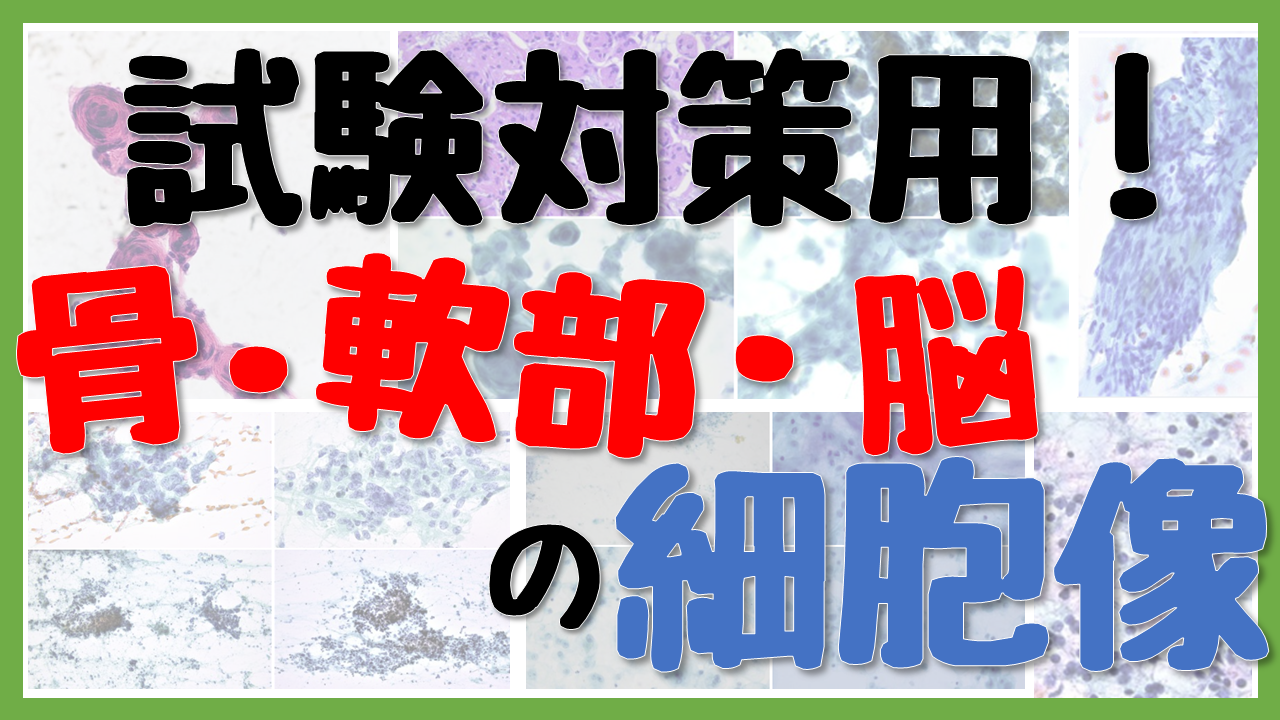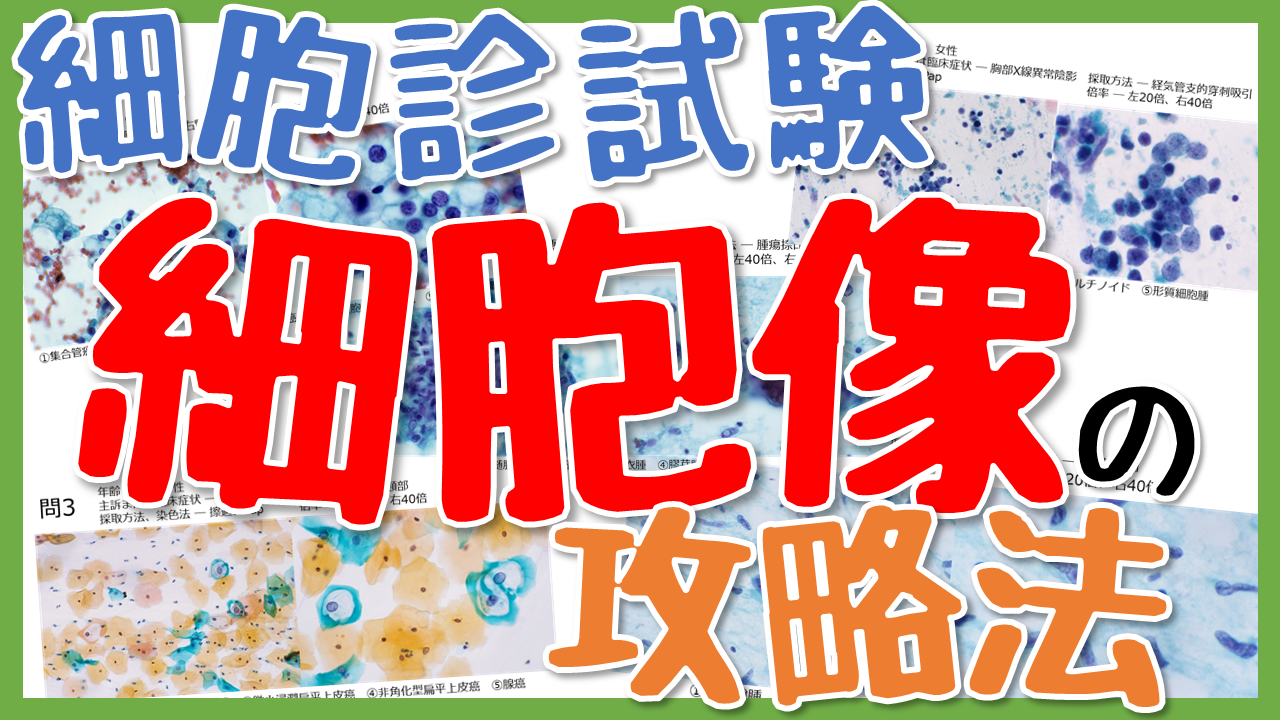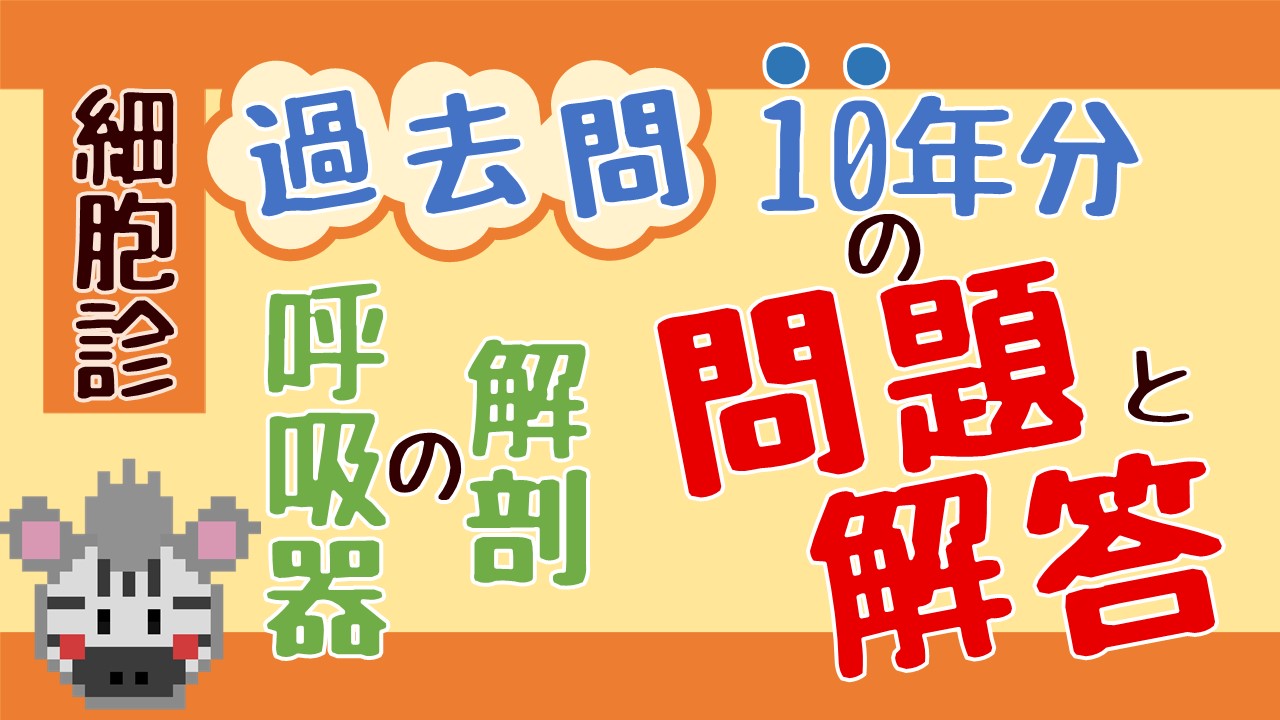細胞検査士 模擬試験の解答・解説
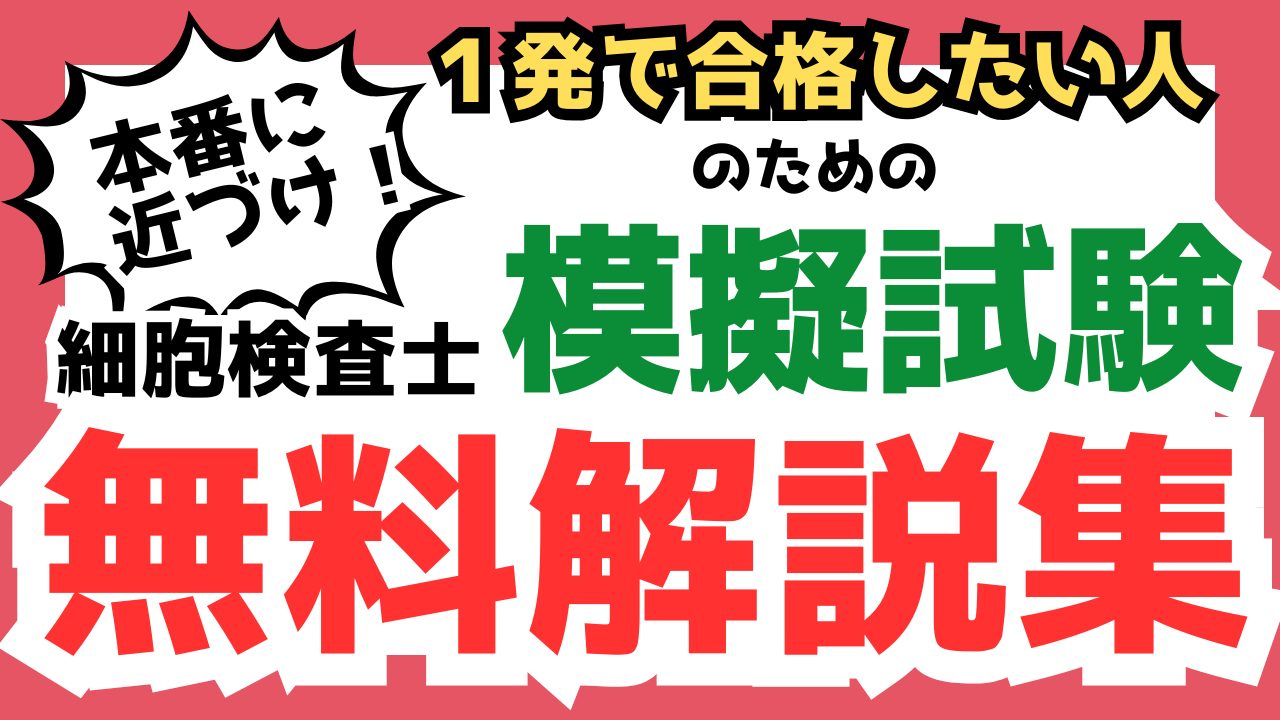

細胞検査士のどっとぜぶらです。
ここでは細胞診模擬試験の解説を記載していきます。
細胞診模擬試験 ~難易度1~の解説
80.66%(96.8問正解/120問中)
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度1】では最低限知っておきたい簡単な問題を作成しました。
まずはここから一緒に始めましょう。
毎月問題を解いていけば必ず合格に近づきます。
試験まで一緒に頑張っていきましょう!
- 【総論】の解答
-
- 1.答え4
A:中胚葉
B:中胚葉
E:内胚葉 - 2.答え2
A:休止期と呼ばれる細胞周期外のフェイズ
B~D:間期
E:分裂期と呼ばれる細胞が分裂する時期 - 3.答え3
A:DNAやRNAを含み転写などを行う
B:リボソームが付着した小胞体
C:蛋白を合成する
D:酸性加水分解酵素で異物を消化する
E:蛋白の修飾を行う - 4.答え3
A:多列線毛円柱上皮で被覆される。呼吸器系は線毛が生える上皮が多い。
D:単層円柱上皮で被覆される。消化器系は基本単層円柱上皮。
E:単層円柱上皮で被覆される。外分泌腺は基本単層円柱上皮。 - 5.答え2
腺房は外分泌腺にしかない。つまり外分泌腺を選べばよい問題。
A:外分泌腺
B:内分泌腺
C:内分泌腺
D:内分泌腺
E:外分泌腺 - 6.答え5
細胞死にはアポトーシスとネクローシスが出題されやすい。それぞれ特徴が反対になることが多いので何がどちらなのか覚えたい。
A:アポトーシスは細胞が破壊されないため周囲への影響がない。ネクローシスはある。
B:アポトーシスは自ら死の選択をするためエネルギーを使う。ネクローシスは使わない。
C:アポトーシスは細胞が収縮する。ネクローシスは膨化する。
D:アポトーシスはヌクレオソーム単位で核の断片化が起きる。ネクローシスは特徴的な断片化は起きない。
E:アポトーシスは細胞膜が最後まで保たれる。ネクローシスは保たれない。 - 7.答え2
細胞所見は細かく覚えるよりまずは2~3個の特徴的な所見を覚えたい。その後に鏡検で必要な所見を追加で覚えよう。
A:好酸性上皮細胞とリンパ球が特徴。
B:単核の巨細胞、2核の鏡面像、核小体が特徴。
C:異型の強い細胞が特徴。脳腫瘍で渦巻き状は髄膜腫。
D:核偏在した2核細胞(出目金細胞)が特徴。葉巻状核は平滑筋肉腫。
E:異型の強い腫瘍細胞と成熟リンパ球が特徴。 - 8.答え5
A:ピロリ菌が関連する。
B:口腔のカンジダ感染症のこと。
C:感染は関係ない。前癌病変の一つ。
D:ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)が関連する。
E:ポリオーマウイルスが関連する。 - 9.答え3
A:弧在性で核腫大、核異型をもつ粘液保有細胞が特徴。
B:類上皮細胞、ラングハンス巨細胞(多核組織球)、壊死が特徴。
C:多核細胞、微絨毛の発達、hump、オレンジG好性細胞などが特徴。
D:平面的配列、類円形核、ごま塩状クロマチンが特徴。
E:星雲状封入体が特徴。 - 10.答え1
どの小体がどの疾患に出るかは100%最低限で覚えたい。
C:正常胸腺や胸腺腫など胸腺疾患でみられる。
D:卵黄嚢腫瘍でみられる小体というか構造の名称。細胞診では基本見られない構造。
E:マラコプラキアでみられる小体。 - 11.答え2
1:上皮系細胞
3:神経系細胞
4:神経膠細胞
5:間葉系細胞
そもそも中間径フィラメントって人はこちら - 12.答え3
小細胞癌の所見は壊死、核線が背景にみられ、弧在性~小集塊で出現。細胞質は乏しく裸核状(N/C比が高い)で大きさはリンパ球の3倍程度以内。クロマチンは細顆粒状で核小体は目立たない。
1:角化型扁平上皮癌の特徴。
2:腺癌の特徴。
4:基本的には角化型扁平上皮癌の特徴。石灰化小体なども該当すると考えるとそれがみられる腺癌などの特徴ともいえる。
5:腺癌に多い特徴。もちろん腺癌以外でも目立つものはある。 - 13.答え4
ヘルペスウイルス感染細胞は特徴的な所見がたくさんあり、①核縁肥厚②すりガラス状核③多核④核圧排像⑤好酸性・好塩基性封入体などがある - 14.答え5
罹患数と死亡数は下URLで最新のものを確認しておこう!
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
1:2位
2:3位
3:4位
4:5位 - 15.答え4
腫瘍は性差や年齢を必ず覚えておこう。
4番以外は男性に多い。 - 16.答え2
腫瘍は性差や年齢を必ず覚えておこう。
2番以外は高齢者に多い。 - 17.答え3
正常の組織像は必ず頭にいれておきたい。
1:ペプシノゲンを分泌
2:粘液を分泌
3:塩酸を分泌
4:粘液を分泌
5:ガストリンを分泌 - 18.答え5
甲状腺乳頭癌の特徴は①砂粒小体②ロープ―コロイド③乳頭状構造④すりガラス状核⑤核溝⑥核内細胞質封入体⑦核重畳などがある。 - 19.答え15
この小体がみられるのは他に甲状腺乳頭癌、粘液癌などがある。 - 20.答え12
多核細胞だからといって悪い細胞ではないので要注意!
- 1.答え4
- 【技術】の解答
-
- 21.答え2
進行性はマイヤーとリリーマイヤーの2つのみ。あとは全部退行性。 - 22.答え1
A:光の回析と干渉を利用して透明な標本に明暗のコントラストを付けて観察する。
B:弧仮の屈折率と厚さの違いを利用して観察する。
C:試料面をスポット状のレーザービームで走査してその焦点面からの蛍光と反射光の空間分布を記録し、コンピューターを通してその切片画像を再現する。X-Y平面およびZ軸上(深さ方向)の分解能が高い画像が得られる。蛍光で染められた試料の三次元構造を把握できる。
D:偏光という光を用いて偏光特異性のあるもの(結晶やアミロイドなど)を照明し、標本を透過した後の偏光の状態を、明暗のコントラストや干渉色による色の変化にして観察する。
E:X線、紫外線、可視光線(400~700 nm)などの光(励起光)を物質に照射すると、物質中の分子あるいは原子から蛍光が放出される。その蛍光を観察する。暗い背景の中に目的物が光って見えるため、感度が高い。FISHやその他の蛍光染色標本に使用する。 - 23.答え5
この方法は細胞診の液状検体をFFPE標本(ホルマリン固定パラフィン包埋標本)にする技術のこと。組織と同じようにホルマリン固定し、切片を作製することができる。また電顕や遺伝子解析、免染、蛍光染色など通常の組織と同じ応用ができる。アルギン酸ナトリウム法はアルギン酸と塩化カルシウムが反応すると固形化することを利用した方法である。 - 24.答え2
擦過や穿刺材料を保存固定液に溶解する方法のこと。
B:保存液や専用の機器を必要とするためコストがかかる。
C:背景所見が減弱する特徴がある。
D:塗抹範囲は狭い。 - 25.答え3
この液は検診喀痰用として使用された固定液で2%カーボワックスと50%エタノールの混合液。もちろん喀痰以外でも使用できる。 - 26.答え1
異染性を示す染色法はそんなに多くない。色素としては青系の色素が多い。 - 27.答え4
A:何度も行うと挫滅が起きるため3回以内におさめる。
B:強いと挫滅が起きるため軽くする。
C:比重が重い癌細胞は辺縁や引き終わりに集まりやすい。
D:有核細胞は上清と赤血球層の間に存在する。その層を有核細胞層(バッフィーコート)と呼ぶ。
E:陰圧を解除してから抜く。 - 28.答え5
A:核
B:細胞質
C:細胞質 - 29.答え1
A:洗浄はどこでも生理食塩水で行う。
B:喀痰などの剥離細胞診では粘膜下の細胞まで採取できない。
C:消化酵素によって細胞が変性するため、氷冷して酵素を働きにくくする。
D:消化酵素によって細胞が変性する。
E:早朝尿は細胞が浮遊した状態で存在するため変性が強く検体として適さない。 - 30.答え4
A:黄色
B:色温度は変えずに明るさだけを調節する。
D:カラー写真はアポクロマートレンズが適する。 - 31.答え2
1:酸性粘液多糖類を染める。
3:基底膜や粘液、グリコーゲンなど多くのものを染める。
4:内分泌顆粒やラ氏島A細胞などを染める。
5:血液系細胞を染める。 - 32.答え3
検体によって細胞が壊れやすいものがある。そういうものは低回転数、長時間(大体1000rpm, 10分程度)で遠心を行うと良い。 - 33.答え4
1:発色基質として使用される。
2:発色基質と反応する酵素として使用される。
3:発色基質として使用される。
5:免疫染色時の洗浄液として使用される。 - 34.答え2
蛍光標識されたプローブを使って目的の核酸を検出する方法。間期も検出可能で蛍光を使うため感度が高いが永久標本にはならない。 - 35.答え2
1:酸性粘液多糖類を染める。
3:カルシウムを染める。
4:アミロイドを染める。
5:脂肪を染める。 - 36.答え1
2:有機溶剤
3:指定物質ではない
4:有機溶剤
5:有機溶剤 - 37.答え5
これは一旦細胞を1か所に集める方法の総称。検査技師国家試験にも出題される。 - 38.答え4
ギルのヘマトキシリンの組成は①エチレングリコール②氷酢酸③硫酸アルミニウム④ヨウ素酸ナトリウム⑤ヘマトキシリン⑥蒸留水。過ヨウ素酸ナトリウムがヘマトキシリンに使われることはない。 - 39.答え25
2:赤く染まりやすくなる。
5:PAS染色は湿固定標本でも乾燥標本でも染色ができる。 - 40.答え12
1:数µmの孔があいたフィルターで大きな細胞を補足する方法。効率よく細胞を回収できる。
2:遠心力を利用してガラスに細胞を塗抹する方法。効率よく細胞を回収できる。
3:粘稠検体に用いる方法で、ある程度検体量が無いとこの方法は使えない。
4:比較的年度の低い検体に用いる方法で、ある程度検体量が無いとこの方法は使えない。
5:細胞診の液状検体をFFPE標本(ホルマリン固定パラフィン包埋標本)にする方法。細胞量がかなり無いと作製するのが厳しい。
- 21.答え2
- 【その他】の解答
-
- 41. 答え1
C:濾胞上皮由来の腫瘍である乳頭癌が多い。
D:予後良好の乳頭癌が多い
E:炎症疾患も対象となる。一部対象とならない疾患もある。 - 42. 答え1
A:髄様癌の特徴。
B:甲状腺領域だと亜急性甲状腺炎でよくみられる所見。 - 43. 答え5
濾胞性腫瘍は良悪性の鑑別ができない。その理由は良悪性の診断基準が細胞診で判定できない次の3つからなるためである。①被膜浸潤②遠隔転移③脈管侵襲。 - 44. 答え2
A:試験レべルでは明らかにこの細胞があれば確実に良性の判定で考えて良い。実際はDCISなどではみられることがある。
B:どちらかというと悪性に多い。正常の細胞ではみられない。
C:結合性は基本的に悪性細胞で緩く良性細胞で強固になる。EMTと呼ばれる現象が関連するためと考えられる。
D:基本的には悪性細胞に多い。稀であるが良性でも一部みられるものはある。この問題集を解く段階ではまだその疾患を覚えなくてよい。
E:基本的には良性に多い所見。 - 45. 答え1
この分子は細胞接着分子の一つで、免染すると小葉癌で陰性、浸潤性乳管癌 硬性型で陽性を示すため鑑別に有効となる。 - 46. 答え4
サブタイプ分類は治療方針を決めるために癌の特徴で分ける分類のこと。ER、PgR、HER2、Ki-67の4因子で分類される。 - 47. 答え1
尿中にはAやBのような高異型度な腫瘍が出現しやすく、判定もしやすい。良性腫瘍や腎癌はそもそも尿中に出現しにくい。 - 48. 答え3
A:前立腺癌は前立腺の外側に発生し、尿管の圧迫なども起こしにくいため初期では特に症状が出にくい。 - 49. 答え5
A:淡明細胞型が多い。
B:ウィルムス腫瘍は腎芽腫のことで小児に多い。
C:淡明細胞型は細胞質が比較的広い。
D:腎癌は基本的に尿中に出現しにくい。
E:多くの腎癌は尿細管上皮に由来する腺癌。 - 50. 答え2
B:微絨毛はみられるが、線毛はみられない。
C:正常でも悪性でも産生する。
D:I型のCollagenous stromaを形成することがある。 - 51. 答え4
4:I型は良性の所見Ⅱ型、Ⅲ型となるに層が厚くなり悪い細胞で出やすい。 - 52. 答え5
中皮腫マーカーとして①Cytokeratin5/6②Calretinin③D2-40④WT1の4つはまず覚えたい。 - 53. 答え1
2:10代
3:10~20代
4:10代
5:50代 - 54. 答え5
担空胞細胞(physaliferous cells)と呼ばれる空胞状細胞細胞が特徴的。 - 55. 答え2
魚骨様配列(ニシンの骨様配列、杉文模様、herring-bone pattern)富部れる細胞の配列が特徴。1は横紋筋肉腫。3は悪性線維性組織球腫や隆起性皮膚線維肉腫。4はEwing肉腫など。5は悪性度の強い未分化な細胞にみられる。 - 56. 答え2
星細胞腫とは神経膠腫の中でも星細胞由来の腫瘍。GradeⅠ~Ⅳまであり①毛様細胞性星細胞腫②びまん性星細胞腫③退形成性星細胞腫④膠芽腫などがある。 - 57. 答え4
この線維はソーセージ状でオレンジG好性の線維で毛様細胞性星細胞腫に特徴的。 - 58. 答え4
Bcl-2はアポトーシスに関連する蛋白の一つ。反応性では発現しておらず、濾胞性リンパ腫で高発現するためこの腫瘍の判定に有効な蛋白。 - 59. 答え14
2:成人T細胞リンパ腫やセザリー症候群でみられる異型の強い細胞。
3:悪性細胞の所見。特に異型が強いホジキンリンパ腫や未分化大細胞リンパ腫などに目立つ。
4:胚中心にいる正常細胞で核破砕物を貪食した組織球のこと。
5:未分化大細胞リンパ腫などでみられる核内細胞質封入体をもつ細胞。 - 60. 答え14
2:ホジキンリンパ腫の特徴。2核で鏡面像を呈する細胞。
3:サルコイドーシスにみられる石灰化物の小体。
5:木村病やホジキンリンパ腫でみられる。
- 41. 答え1
- 【呼吸器】の解答
-
- 61. 答え2
この物質は界面活性物質で肺や気道がつぶれるのを防ぐ。この2つの細胞が産生する。 - 62. 答え3
3cm以下の限局性病変でⅡ型細胞やクララ細胞様の腫瘍細胞が置換型増殖を示す。異型が弱いため良性との鑑別が難しい。間質浸潤、脈管浸潤、胸膜浸潤は示さない。置換型を示すものはすりガラス状陰影がみられやすい。 - 63. 答え5
A:中悪性
B:低悪性
C:中悪性 - 64. 答え1
喫煙は中枢に発生しやすい腫瘍と関連が深い。 - 65. 答え1
肺癌は基本的には男性に多い。女性に多い腫瘍はどこでもそんなに多くないので覚えたい。 - 66. 答え1
腺癌はTTF1とnapsin A、神経内分泌腫瘍はchromogranin Aやsynaptophysinなど。 - 67. 答え3
扁平上皮癌はp40とCK5/6、神経内分泌腫瘍はchromogranin Aやsynaptophysinなど。 - 68. 答え4
扁平上皮癌はp40とCK5/6、腺癌はTTF1とnapsin A。 - 69. 答え2
中枢に発生しやすい腫瘍は喀痰に細胞が出やすく、喫煙と関連が深いことも併せて覚えておこう。 - 70. 答え5
A:角化型扁平上皮癌の所見。
B:基本的には腺癌で目立つ所見。非角化型扁平上皮癌でもみられる。
C:組織球で使われる所見用語。 - 71. 答え3
2番目は扁平上皮癌、3番目は小細胞癌、4番目は大細胞癌。 - 72. 答え2
肺腺癌の約80%にドライバー遺伝子が存在し、EGFRが腺癌の約50%と最も多い。 - 73. 答え4
1:腎癌や甲状腺癌
2:乳がんや子宮癌
3:子宮体部や卵巣の漿液性癌
4:大腸癌
5:前立腺癌 - 74. 答え2
ひし形正八面体の結晶で好酸球の顆粒が結晶化したもの。Papではオレンジに染まり、光輝性がある。気管支喘息、肺吸虫症などアレルギー疾患や寄生虫感染で見られることが多い。 - 75. 答え1
この疾患に有効な染色は6つ。①Grocott染色②PAS反応③Alcian blue染色④mucicalmine染色⑤Masson Fontana染色⑥墨汁染色。 - 76. 答え3
肺は転移性腫瘍が多く、原発巣によっては分かりやすいものがある。その代表例が大腸癌の転移で、肺腺癌ではあまりみられない高円柱状細胞がみられた場合は大腸癌を考える。 - 77. 答え4
肺がん検診はA~Eに区分される。Aが検体不適、Bが軽度異型扁平上皮細胞や他の正常細胞。Cが中等度異型扁平上皮細胞や核の増大、濃染を伴う円柱上皮細胞。Dが高度異型扁平上皮細胞、悪性が疑われる細胞。Eが悪性腫瘍。 - 78. 答え2
胸腺にはリンパ球と扁平上皮系の細胞が存在するため、上皮性悪性腫瘍で最も多いのは扁平上皮癌。 - 79. 答え14
1:肺胞に入る組織球のことでこの細胞が無いと検体不適性になる。
4:腺癌で見られやすい。 - 80. 答え12
細胞像が特徴的で定型カルチノイドは異型の弱い大きさがほぼ均一な円形核細胞が平面的にみられる。細胞質は広いが辺縁や境界は不明瞭。核は小型円形でゴマ塩状クロマチンがみられる。壊死は見られない。異型カルチノイドは細胞異型が強く、核分裂像や壊死も見られることがある。
- 61. 答え2
- 【消化器】の解答
-
- 81. 答え2
A:扁平上皮癌の判定に深層型扁平上皮細胞の存在が重要となるためその細胞を採取するようにすることが重要。
B:扁平上皮系細胞は基本的にLBCが有効。
C:採取器具として綿棒やブラシがあるが、ブラシの方が細胞採取量が多い。
D:出血が多いと鏡検しにくい。 - 82. 答え5
A:喫煙が関連する。
B:HPVが関連する。
C:喫煙、飲酒、慢性刺激などが関与する。
D:扁平上皮癌の危険因子として喫煙がある。 - 83. 答え3
A:25cm程度。
B:粘膜と呼ばれる部分で重層扁平上皮は大体非角化型。
C:上部は横紋筋、中部が横紋筋と平滑筋の混合、下部は平滑筋で構成される。
D:中部に多い。
E:腺癌が発生しやすい。 - 84. 答え3
A:扁平上皮癌が一番多い。
D:粘膜下層までにとどまるものと定義される。
E:リンパ節転移の有無は問わない。 - 85. 答え1
C:粘液を分泌する。塩酸を分泌するのは壁細胞。
D:エオジン好性であるためHE染色では赤っぽく染まる。Papでは淡橙色やライトグリーンで顆粒状に染まる。
E:幽門部に多い。 - 86. 答え3
A:癌とも関連がある。
D:平滑筋腫が最も多い。大体その組織を構成する筋腫が多い。
E:KITはGISTで陽性になる。 - 87. 答え5
D:十二指腸の粘膜下層にある粘液腺。分泌する粘液はアルカリ性で胃酸を中和する。
E:小腸陰窩底部にみられる赤い顆粒を持った細胞。リゾチームなどを分泌する。 - 88. 答え4
A:高分化なものが多い。低分化な癌が多いという場所はほぼ無いと思われる。
B:高円柱状の形態が特徴的。
C:円柱上皮で被覆される組織は腺癌が多い。
D:左側の特にS状結腸や直腸に多い。
E:大腸癌は腺腫から発生することで有名。この腺腫から腺癌が発生することをadenoma carcinoma sequenceと呼ぶ。正常粘膜から直接癌が発生することもあり、それはde novo発癌と呼ばれる。 - 89. 答え3
A:肝組織内の毛細血管を類洞を呼ぶ。類洞と肝細胞索の間にあるすき間はディッセ腔と呼ばれる。
B:類洞内にはクッパ―細胞と呼ばれるマクロファージが存在する。
D:グリコーゲンをもつためPAS反応に陽性を示す。
E:肝三つ組みとはグリソン鞘にある小葉間静脈、小葉間動脈、小葉間胆管のことである。 - 90. 答え2
B:肝硬変から肝細胞癌に進行することがある。
C:低分化な癌は度の癌でも異型が強い。
D:未分化な癌は低分化な癌よりも分化度が低く、良性とかけ離れた所見を持つことが多い。
分化の言葉が分からない人はこちら - 91. 答え4
基本的にはいわゆる悪性所見があてはまる。核小体は胆汁などでは変性によって目立つことがあり、悪性所見には含まれない。 - 92. 答え1
- 93. 答え1
90%以上にこの遺伝子の変異がみられる。 - 94. 答え2
腫瘍は男性に発生するものが多い。膵臓でSolidpseudopapillary neoplasmは若年女性に好発することで有名。インスリノーマは良性が多い。 - 95. 答え4
自己免疫性疾患水疱性疾患で、Tzank細胞と呼ばれる細胞がみられる。どっとゼブラ的にぱっと見の印象が扁平上皮化生のような感じ。 - 96. 答え2
- 97. 答え5
日本だと直腸下部に多いといわれる。 - 98. 答え4
異染性を示すとよく記載されるのは、基底細胞腺腫、腺様嚢胞癌、多形腺腫。 - 99. 答え23
1:絨毛腺腫は癌化しやすい。
2:若年にも成人にも発生する。
4:潰瘍性大腸炎やクローン病などに付随して発生するもので癌化はほぼない。
5:非腫瘍様病変のひとつ。つまり癌化はほぼない。 - 100 答え12
- 81. 答え2
- 【婦人科】の解答
-
- 101. 答え1
形成されるのは膣上部、子宮頸部・体部、卵管。 - 102. 答え3
子宮頸部はSCJと呼ばれる2種類の上皮の境界があり、その上皮とは膣側の非角化型重層扁平上皮と体部側の単層円柱上皮。 - 103. 答え2
豊富な細胞質を有する細胞がシート状ないしリボン状の流れるような配列を示し、平面的な集塊を形成する。細胞境界は比較的明瞭。核は腫大し、核小体は明瞭化するが、N/C比は低く、クロマチンは繊細で増加を認めない。B~Dは悪性細胞所見。 - 104. 答え1
HPVは良性の乳頭腫に関連するlow riskの6型、11型と癌に関連する18型、31型、32型、51型などがある。 - 105. 答え3
A:「LSIL」に含まれる。
D:「SCC」に含まれる。
E:「Adenocarcinoma」に含まれる。 - 106. 答え5
A:非浸潤性病変では壊死性背景になりにくい。良性疾患や非浸潤性病変でも壊死を特徴とするものもあるのでそこは注意(結核や乳腺DCISなど)
B:癌では核分裂像を認めることがある。
C:分化度が高い腺系の腫瘍は結合性が強い状態で出現することが多い。 - 107. 答え3
A:辺縁が不明瞭にみえる。
D:婦人科だとヘルぺスウイルスでみられる所見。
E:婦人科だとヘルぺスウイルスでみられる所見。 - 108. 答え2
A:細胞質内に分泌物を含み一つ一つの細胞境界がはっきりする。
B:重積が目立つのは増殖期。
C:濃縮が目立つのは萎縮内膜。
D:分泌期は分泌物を含むため細胞質が豊富になる。
E:分泌期は細胞質も核も腫大傾向を示す。 - 109. 答え1
依存性の腫瘍は類内膜癌G1、G2。非依存性は類内膜癌G3、漿液性癌、明細胞癌。 - 110. 答え5
明細胞癌が最も関連し、次に類内膜癌が多いといわれる。 - 111. 答え2
- 112. 答え3
胎盤を構成する絨毛細胞の一つで多核の合胞体を形成する。この細胞がhCGを産生する。 - 113. 答え3
- 114. 答え2
1:上皮性腫瘍
3:胚細胞腫瘍
4:上皮性腫瘍
5:胚細胞腫瘍 - 115. 答え1
産褥期はホルモンの影響が無くなっているため細胞成熟度指数は左方移動を示す。そのため一番左に偏っているものを選べばよい。 - 116. 答え4
コルポスコピーでは酢酸加工をすることによって上皮の変化を際立たせて異常病変を分かりやすくする。 - 117. 答え5
正常でも腫瘍でも見られる特徴的な構造。 - 118. 答え1
腫瘍自体が産生しており、この腫瘍の特徴的な細胞所見の一つである硝子様小球はこの物質の塊であるとされる。 - 119. 答え14
- 200. 答え35
卵巣腫瘍の中でも胚細胞腫瘍は若年者に好発する。上皮性腫瘍は高齢者に多く、性索間質性腫瘍はどちらもある。
- 101. 答え1
細胞診模擬試験 ~難易度2~の解説
82.7%(99.2問正解/120問中)
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度2】では最低限知っておきたい簡単な問題+ほんの少し気になる問題を含めて作成しました。
毎月問題を解いていけば必ず合格に近づきます。
試験まで一緒に頑張っていきましょう!
- 【総論】の解答
-
- 1. 答え3
A:エネルギー産生を行う。分泌物産性はゴルジ装置が行う。
D:リボソームが付着するためタンパク合成に関与する。脂質代謝は滑面小胞体。
E:細胞分裂や線毛形成などを行う。蛋白修飾はゴルジ装置が行う。 - 2. 答え2
全ての組織は上皮組織、支持組織、筋組織、神経組織の4つの組織に分類される。
A:筋組織
E:神経組織 - 3. 答え3
導管は外分泌を行う場所にみられる。
A:小葉構造はあるが導管は無い。
B:外分泌を行うため導管をもつ。
C:外分泌腺であるため導管を持つ。
D:内分泌を行うため導管が無い。
E:分泌は行わないため導管が無い。 - 4. 答え1
C:重層扁平上皮
D:重層扁平上皮
E:重層扁平上皮 - 5. 答え2
A:神経細胞の中間径フィラメント
B:上皮系の中間径フィラメント
C:間葉系の中間径フィラメント
D:筋系の中間径フィラメント
E:神経膠細胞の中間径フィラメント - 6. 答え3
核に陽性を示すのは脂溶性ホルモン関連、転写因子、細胞周期系などがある。
A:細胞質
B:細胞周期マーカー
C:脂溶性ホルモンの受容体
D:細胞質
E:細胞膜 - 7. 答え5
A:分化した細胞が別の分化した細胞になること。
B:通常ライトグリーン好性を示す。
C:上皮細胞なので結合性を示す。中皮の結合はWindowと呼ばれる名称と呼ばれる。
D:良性なのでクロマチンの増量は無い。
E:尿路上皮最外層にあるアンブレラ細胞は多核細胞も多々みられる。 - 8. 答え4
C:悪性ではN/C比が高くなる傾向にある。
D:悪性では粗顆粒状クロマチンが不均一に分布する。悪性ではその他、ゴマ塩状クロマチンなど独特なクロマチン構造も存在する。 - 9. 答え3
マクロファージは存在する組織によって名前が変わる。有名なものは覚えておきたい。
A:肺胞のマクロファージ。
B:肝臓ディッセ腔に存在する細胞。ビタミンAや脂肪を蓄える。
C:細気管支に存在するサーファクタント分泌細胞。
D:肝臓のマクロファージ。
E:特異性炎でみられる馬蹄形核をもつ多核マクロファージ。 - 10. 答え5
D:神経系に見られる構造。真正ロゼットと偽ロゼットが存在する。
E:重層扁平上皮に見られる構造。重層扁平上皮のデスモソーム結合をこのように呼んでいる。 - 11. 答え3
1:静止期。周期外でほとんどの細胞はこの期で存在する。
2:DNA合成準備期。DNAの合成を準備する時期。
3:DNA合成期。合成の英語(Synthesis)のS。この時期にDNAが合成される。
4:分裂準備期。分裂の準備をする時期。
5:分裂期:有糸分裂(Mitosis)のM。細胞の分裂が開始される。 - 12. 答え2
- 13. 答え3
- 14. 答え5
1:外胚葉
2:外胚葉
3:外胚葉
4:外胚葉 - 15. 答え1
1:膵癌などに関与する癌遺伝子。
2:p53やp40のようなp~(数字)の遺伝子は全て癌抑制遺伝子。
4:乳癌、卵巣癌、前立腺癌、膵癌などに関与する癌抑制遺伝子。
5:大腸癌に関与する癌抑制遺伝子。 - 16. 答え4
1:小腸に見られる構造。
2:胃副細胞から分泌される。壁細胞からは塩酸と内因子が分泌される。
3:小腸に見られる赤色顆粒を持った細胞。
5:胆嚢に見られる構造。腺筋腫症などで増生が見られる。 - 17. 答え4
1:ペプチドホルモン
2:ペプチドホルモン
3:ペプチドホルモン
5:アミノ酸誘導体ホルモン - 18. 答え2
- 19. 答え12
セミノーマ、ディスジャーミノーマ、ジャーミノーマは背景の成熟リンパ球と異型の強い腫瘍細胞を特徴とする。橋本病は好酸性濾胞上皮細胞と背景の成熟リンパ球を特徴とする。 - 20. 答え35
2023年2月現在最新のがん死亡数(2021年)1位は男性が肺、女性が大腸である。
- 1. 答え3
- 【技術】の解答
-
- 21. 答え3
B:励起光を照射できる顕微鏡。蛍光を観察できる。
C:試料面をスポット状のレーザービームで走査してその焦点面からの蛍光とは反射光の空間分布を記録し、コンピューターを通してその切片画像を再現することにより、X-Y平面およびZ軸上(深さ方向)の分解能が高い画像が得られる。 - 22. 答え2
擦過はブラシなどが届く場所に使われることが多い。最近は内視鏡などの発達で胆管や膵管などにも使われる。
A:綿棒やブラシが使われる。
B:穿刺吸引が多い。
C:穿刺吸引が多い。
D:自然尿が多い。
E:擦過、洗浄、穿刺、喀痰など幅広い。 - 23. 答え1
A:遠心力を利用してガラスに塗抹する。少量の細胞数でも塗抹されやすい。
B:濾過膜ごと塗抹するため少数の細胞でも塗抹されやすい。
C:ある程度の検体量が無いと作製は厳しい。
D:生検材料の一部など組織片などに有効。
E:少ない材料だと挫滅してしまい良くない。 - 24. 答え2
ギムザが有効かどうかの問題。
A:通常パパニコロウ染色とギムザ染色を行う。
B:パパニコロウ染色のみ行うことが多い。
C:パパニコロウ染色のみ行うことが多い。
D:パパニコロウ染色のみ行うことが多い。場合によっては特染も行う。
E:細胞の張り付きが悪いため、ギムザ染色が有効。 - 25. 答え5
A:人為的な差が生まれにくいため不適正標本が減る。
B:特殊な機器や固定液を使用するためコストがかかる。
C:背景所見が減弱しやすい特徴がある。
D:保存液の組成は会社によって異なるが、低濃度のアルコールベースであることが多く、弱い固定作用がある。
E:これはそのまま。 - 26. 答え3
B:分子量の異なる酸性色素で染める。
C:乾燥は厳禁で1秒以内に95%エタノールで固定する。 - 27. 答え4
PAS反応は過ヨウ素酸シッフ反応の英語の頭文字を取った染色名で、その名の通り過ヨウ素酸とシッフ試薬が使われる。シッフ試薬には塩基性フクシンが含まれる。 - 28. 答え4
A:内因性アルカリホスファターゼ阻害剤として使う。
B:内因性ペルオキシダーゼ阻害剤として使う。
C:DABとも略され茶色に発色する。
D:AECとも略され赤色には発色する
E:内因性ペルオキシダーゼ阻害剤として使う。 - 29. 答え5
A:ホルマリンで固定する。
B:塩化カルシウムはアルギン酸ナトリウム法で使う。
C:遠心が必要。沈査をコロジオン膜ごとスピッツから取る。
D:免染、FISH、遺伝子検査などあらゆるものに応用できる。
E:薄切するため複数の抗体で免染できる。 - 30. 答え1
C:細胞質
D:細胞膜
E:細胞膜 - 31. 答え1
収差には色収差と単色収差がある。単色収差はザイデルの5収差と呼ばれ、球面収差、コマ収差、非点収差、像面歪曲、歪曲収差がある。 - 32. 答え2
アスベスト線維は鉄と蛋白を含むためベルリン青染色で青に染まる。 - 33. 答え1
1:生理食塩水、血清、スキムミルクなどに浸すか標本上に満載する。
2:乾燥後アルコール固定した標本では効果が薄い。
3:2日以内には行う。
4:効果が薄い。
5:長すぎては良くない。 - 34. 答え4
1:グリコーゲンを染める染色
2:核小体の染色
3:迅速ギムザ染色
5:銅を染める染色 - 35. 答え4
1:約37%を含む。
2:劇物に分類される。
3:0.1ppm以下。
4:空気より重いため排気装置は下におく必要がある。
5:第2類物質に分類される。 - 36. 答え5
1:DNAを1本鎖にする時やハイブリダイズ時に熱をかける必要がある。
2:使える。そのため細胞診標本にも有効。
3:使える。
4:DNAもRNAも検出できる。 - 37. 答え4
1:これはそのまま。
2:これを含むためpHが下がり、進行性となる。
3:これはそのまま。
4:退行性であるため分別を必要とする。
5:これはそのまま。 - 38. 答え3
この固定法は基本的に脂肪染色で行われる。アルコール系固定液で固定すると死亡が流出するためである。選択肢で脂肪染色は3のみ。 - 39. 答え14
- 40. 答え23
1:脂肪染色
2:DNAを定量的に染める染色。
3:DNAとRNAを染める染色。
4:真菌の染色。
5:弾性線維とHBs抗原を染める。
- 21. 答え3
- 【その他】の解答
-
- 41. 答え1
A:癌の中では珍しく女性に多い。女性に多いものが出てきた時はその都度覚えておきたい。
B:放射性ヨウ素をため込むため放射線と発生が関与すると言われている。
C:乳頭癌が多い。90~95%以上は乳頭癌。
D:甲状腺と前立腺は微小癌が多い。
E:発生する。おそらく発生しない組織は無いと思われる。 - 42. 答え4
A:乳頭状に出現する。
B:ロープ―コロイドやチューインガムコロイドと呼ばれる引き伸ばし多様な形状のコロイドがみられる。
E:すりガラス状のクロマチン構造を示すため淡染に見える。 - 43. 答え3
A:アミロイドは髄様癌で見られやすい。
B:特徴的な所見は無いが、大量のコロイドを認めることが多い。コロイドが多く厚いため、標本上でひび割れ、パズルピース様コロイド等と呼ばれる。
C:好酸性濾胞上皮細胞と成熟リンパ球を特徴とする。
D:多核組織球が特徴。
E:弧在性に出現し、背景のアミロイドを特徴とする。細胞形態は多彩で形質細胞様、紡錘形、カルチノイド様などがみられる。 - 44. 答え3
A:良性でも悪性でも出現があり得る。
B:これがあれば基本的には良性を考える。
C:良性でみられることが多い。異型がある場合は癌との鑑別が難しい。
D:小葉癌でみられやすい構造。
E:浸潤性微小乳頭癌でみられやすい出現様式。 - 45. 答え2
- 46. 答え5
上皮と間質の混合腫瘍ではあるが、悪性の指標は間質成分のみに絞られる。 - 47. 答え1
細胞質にグリコーゲンや脂肪を含むため、それらを染める染色が有効。
1:脂肪染色
2:糖や基底膜などの染色
3:アミロイドの染色
4:酸性粘液多糖類の染色
5:神経系顆粒やメラニン等の染色 - 48. 答え2
B:弧在性の細胞がみられやすい。自然尿で集塊上の細胞がみられた場合は腫瘍を疑いたい。
C:腎障害などがあればみることがある。異型がある時は癌との鑑別が必要。
D:核小体は目立つこともある。 - 49. 答え2
A:膀胱頂部に多い。
B:尿路上皮癌と腺癌、扁平上皮癌が合併した場合、主診断は尿路上皮癌となる。
C:これはそのまま。
D:細胞診で原発・非原発の判断は厳しい。 - 50. 答え5
A:好塩基性(青っぽい)を示す。
B:シート状集塊で見られる。
C:windowを形成するのは中皮細胞。
D:これはそのまま。
E:I型、II型、III型があり、I型は良性でも見られやすい。 - 51. 答え4
弧在性の出現を特徴とする腫瘍。4以外の選択肢の特徴をみることは基本的にはない。 - 52. 答え1
- 53. 答え2
腺癌のマーカーとして、CEA、MOC-31、Ber-EP4などがある。2以外の選択肢は全て中皮腫マーカー。 - 54. 答え3
- 55. 答え5
- 56. 答え3
- 57. 答え4
- 58. 答え1
2:脊索腫などで見られる所見。
3:骨肉腫などで見られる所見。 - 59. 答え13
軟骨芽細胞腫は骨巨細胞腫に比べると核の数が少ないといわれる。骨巨細胞腫は単核細胞と多核細胞間に移行像がみられる。 - 60. 答え12
1:側脳室や第四脳室に好発する。
2:第三脳室に好発する。
3:前頭葉に多い。
4:大脳半球に多い。
5:聴神経(第Ⅷ神経)に多い。
- 41. 答え1
- 【呼吸器】の解答
-
- 61. 答え5
D:気管から区域気管支に存在する。
E:細気管支から呼吸細気管支に存在する。 - 62. 答え3
A:3cm以下の限局性病変。
B:置換型増殖を示す腫瘍はすりガラス状陰影を示しやすい。
C:これはそのまま。他の増殖形式があれば浸潤とみなされる。
D:異型は弱い。
E:浸潤・非浸潤の判断ができないため細胞診では診断できない。 - 63. 答え3
- 64. 答え2
異型細胞とオレンジG好性細胞があれば角化型扁平上皮癌を考える。集塊上で見られる場合辺縁に着目し、辺縁が平滑であれば扁平上皮癌の可能性が高い。集塊全体としては流れがあると言われるが、塗抹時に腺癌でも流れが出るため実際の鏡検では辺縁を見る方が良いと思う。 - 65. 答え4
ロゼット構造は基本的には神経系の腫瘍にみられる構造であるため、神経系腫瘍を選ぶ。 - 66. 答え1
ヘルペスウイルスでは核内封入体をみることがある。ヘルペスウイルスⅤ型のサイトメガロウイルスは核内封入体をもったフクロウの目細胞を特徴とする。 - 67. 答え1
C:心臓の栄養血管。
D:機能血管
E:機能血管 - 68. 答え2
A:腺癌の核に染まる。
B:扁平上皮癌の細胞質に染まる。
C:腺癌の細胞質に染まる。
D:神経内分泌腫瘍の細胞膜に染まる。
E:扁平上皮癌の核に染まる。 - 69. 答え3
- 70. 答え4
A:疾患特異性はない。
B:喀痰中にみられる。
E:好酸球の顆粒に由来するのはシャルコーライデン結晶。 - 71. 答え1
- 72. 答え5
1:菌糸自体がみられない。
2:菌糸自体がみられない。
3:90度分岐の菌糸がみられる。
4:菌糸自体がみられない。 - 73. 答え5
- 74. 答え1
2:判定区分C
3:判定区分D
4:判定区分E
5:判定区分A - 75. 答え3
少なくとも2種類の間葉成分が混在する。細胞診では呼吸器系で軟骨成分がみられた場合、本腫瘍を一番に考える。 - 76. 答え4
- 77. 答え3
腎癌で最も多いのは淡明細胞型でその転移が多いと考えられる。その場合、細胞質は広い。 - 78. 答え2
粘表皮癌は粘膜下に腫瘍を形成するため基本的には喀痰中にみられない。 - 79. 答え24
気管から区域気管支までしか見られない。 - 80. 答え25
- 61. 答え5
- 【消化器】の解答
-
- 81. 答え4
A:標本背景に無駄な物質を出現させないために細胞診前は咳嗽を行う。
B:LBCも有効。
C:これはそのまま。
D:深層細胞をいかに採取できるかが重要となる。
E:10回程度は擦る。 - 82. 答え3
B:口腔のカンジダ症で前癌病変ではない。
C:水疱性の自己免疫性疾患で前癌病変ではない。 - 83. 答え5
- 84. 答え1
唾液腺腫瘍は基本女性が多いが、AとBは男性に多い。 - 85. 答え1
他には腺様嚢胞癌も異染性を示す。 - 86. 答え5
A:扁平上皮癌の危険因子となる。
B:腺癌が発生しやすい。
C:中部から発生しやすい。
D:これはそのまま。
E:基本的に悪性腫瘍は男性の方が多い。 - 87. 答え3
A:幽門腺に多い。
C:塩酸と内因子を分泌する。
D:粘液を分泌する。
E:十二指腸側のことを指す。 - 88. 答え2
B:神経鞘腫のマーカー。
C:横紋筋肉腫のマーカー。
D:平滑筋肉腫のマーカー。 - 89. 答え1
C:早期癌はリンパ節転移の有無を問わない。
D:低分化な癌。低分化であるがゆえに弧在性に腫瘍細胞が出現する。
E:左鎖骨上窩リンパ節はウィルヒョウ転移。 - 90. 答え1
A:グリコーゲンを持つためPAS反応陽性を示す。
B:若年男性に多い。 - 91. 答え4
基本的に円柱上皮の組織は腺癌ができやすい。 - 92. 答え1
- 93. 答え2
- 94. 答え3
1:大小不同があるため小型均一とはならない。
2:良性であるため基本的には重積性に乏しい。
3:本疾患は顕著な大小不同を特徴とする。画像問題等では大小不同があるからといって癌にしないように気を付けたい。
4:N/C比は変わらない。
5:良性であるため基本的には核形不整に乏しい。 - 95. 答え4
1:高分化の特徴。
2:高分化の特徴。
3:低分化の特徴。
5:未分化や低分化の特徴。 - 96. 答え3
他の消化器とは違い、粘膜筋板と粘膜下層がない。 - 97. 答え5
- 98. 答え4
変性によって核小体が目立つことが多々あるため、悪性所見とはしない。 - 99. 答え24
2と4以外は男性に多い。 - 100. 答え13
2:陽性を示す。その他の神経内分泌系マーカーも陽性となる。
4:ごま塩状クロマチンを示す。
5:核縁は薄い。神経内分泌腫瘍は基本的には核縁が薄い。
- 81. 答え4
- 【婦人科】の解答
-
- 101. 答え4
A:円柱上皮細胞の所見。
B:円柱上皮細胞の所見。
E:修復細胞の所見。 - 102. 答え5
A:原虫感染症。
B:核腫大はみられるが、核形不整はみられない。
C:辺縁が不明瞭。 - 103. 答え2
A:LSILに含まれる。
E:SCCに含まれる。 - 104. 答え3
A:G1、G2、G3とグレードが上がるにつれて異型が強くなる。
B:これは特徴的な所見の一つ。
C:G1やG2はエストロゲン暴露によって発生する腫瘍であるため背景粘膜は増殖症のことが多い。
D:グレードが高い腫瘍は分化度が低く、弧在性に出現しやすい。
E:間質細胞の付着は良性に多い。 - 105. 答え5
A:粘液性癌の特徴。
B:漿液性癌の特徴。
C:類内膜癌G1の特徴。 - 106. 答え2
同所性とはその組織を構成する成分(例えば子宮体部だと平滑筋など)のことを指す。対義語は異所性といい、その組織には無い成分(例えば子宮体部だと横紋筋など)のことを指す。 - 107. 答え1
- 108. 答え2
B:月経期で目立つ像。
C:分泌期で目立つ像。
D:分泌期で目立つ像。 - 109. 答え5
A:細胞質ではなく核がすりガラス状になる。
B:ヘルペスウイルス感染細胞の所見。
C:この所見は特になし。 - 110. 答え5
胃型関連の疾患はHPV陰性となる。 - 111. 答え2
1:分化度が低いほど感受性が高い。
2:小細胞癌、扁平上皮癌、腺癌の順に感受性が高い。
3:正常細胞も影響を受ける。
4:細胞質の変化から起きる。
5:高いものが多い。 - 112. 答え4
1:分泌期の所見。
2:分泌期の所見。
3:分泌期の所見。
5:分泌期の所見。 - 113. 答え5
増殖症では3分岐以上の多分岐腺管②腺の増生③有端腺管の増加などが所見として挙げられる。 - 114. 答え3
1:胚細胞腫瘍
2:性索間質性腫瘍
4:胚細胞腫瘍
5:性索間質性腫瘍 - 115. 答え4
- 116. 答え2
2:有核発生の場合は陰性を示す。父親由来の遺伝子ではこの遺伝子がメチル化されており、発現しないためである。 - 117. 答え2
- 118. 答え3
- 119. 答え14
- 120. 答え45
1:基本的には卵巣から分泌される。
2:基本的には卵巣から分泌される。
3:視床下部から分泌される
- 101. 答え4
細胞診模擬試験 ~難易度3~の解説
85.9%(103.2問正解/120問中)
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度3】基本的な問題を1と2より本番に近い形で作成しています。
今までより少し難しくなっていますが、まだ簡単な方です。
毎月問題を解いていけば必ず合格に近づきます。
試験まで一緒に頑張っていきましょう!
- 【総論】の解答
-
- 1. 答え4
A:ヒトの体細胞は元々2倍体でS期に4倍体になる。
B:サイクリンAはCdk1や2と複合体を形成してS期の途中からG2期まで発現している。
C:この蛋白はG1期に発現するサイクリンDとCdk4/6を止める方向に働く。つまり細胞周期を止めることになる。細胞周期が止めるため「癌抑制遺伝子」に区分される。
D:この蛋白はサイクリンEを発現させるE2Fの働きを止めている。つまり細胞周期を止めている。これも細胞周期が止めるため「癌抑制遺伝子」に区分される。
E:間期とは分裂期以外の部分つまりG1、S、G2期を指す。間期の方が分裂期より長い。 - 2. 答え1
細胞骨格は太い順に①微小管②中間径フィラメント③アクチンの3種類がある。
C:間葉系細胞の中間径フィラメント
D:上皮系細胞の中間径フィラメント
E:神経細胞の中間径フィラメント
- 3. 答え5
A:酸性加水分解酵素をもつのはリソソーム。
B:タンパクの合成はリボソームが行う。
C:この役割は滑面小胞体行う。
D:合成された蛋白が入る面がシス面、出る面をトランス面と呼ぶ。
E:形質細胞で発達しており、それが核周囲の明庭として観察される。 - 4. 答え2
B:これをラテント癌と呼ぶ。クルーケンベルグ腫瘍は胃癌をはじめとする消化器癌の卵巣転移のこと。
C:これは重複癌のこと。多発癌は同じ臓器に同じ種類の癌が複数個発生すること。
D:これは多段階発癌の説明文。デノボ発癌は正常組織から癌が発生する。 - 5. 答え1
A:高分化な腫瘍は結合性が強いことが多い。
B:分化度が低い腫瘍は分裂速度が速いことが多く、放射線が奏功するものが多い。
C:低分化だと正常から離れた構造となるため特徴所見がみられにくい。
D:基本的には分化度が低い腫瘍は異型が強い。
E:分化度が低いほど結合性が弱いため細胞が採取されやすい。 - 6. 答え3
導管は基本的に外分泌腺にみられる構造。BとCは外分泌腺では無いため導管がみられない。 - 7. 答え4
A:すりガラス状核、核溝、核内細胞質封入体など特徴的な核所見を示すが、核小体は目立たない。
B:内分泌腫瘍はどこの組織で発生しても大体ごま塩状のクロマチン構造を示す野が特徴。
E:小細胞癌は核小体が目立たないことが特徴の一つ。 - 8. 答え2
A:杯細胞や多列線毛円柱上皮細胞がみられる。
B:多列線毛円柱上皮で被覆される。鼻付近で重層扁平上皮は鼻前庭のみ。
C:尿道の近位部は尿路上皮で被覆される。
D:子宮頸部は単層円柱上皮および非角化型重層扁平上皮で被覆される。
E:消化器は基本的に単層円柱上皮。 - 9. 答え2
筋上皮細胞は外分泌腺の腺房や介在部導管にみられる平滑筋のような収縮能力を持った上皮細胞。今回の選択肢の1と5は内分泌組織であるため筋上皮細胞はみられない。 - 10. 答え4
A:S100が陽性。αSMAは平滑筋腫瘍で陽性。
B:KIT(c-kit,CD117)、CD34、DOG1が陽性。CD56はNCAMとも呼ばれ、神経内分泌腫瘍で陽性を示す。
E:αSMAが陽性。DOG1はGISTで陽性。 - 11. 答え4
1:種類によるが、基本的には紡錘形のものが多い。
2:腺癌と鑑別が必要になるような上皮様集塊がみられる。
3:空胞状の明るい細胞質と粘液性背景が特徴。
5:広い細胞質と目立つ核小体、メラニンが特徴。 - 12. 答え3
1:原虫様であるが実は真菌。
2:HPV感染が主な原因。
3:原虫に分類される。
4:EBV感染によって引き起こされる。
5:呼吸器で良く出題される真菌。 - 13. 答え1
寄生虫感染では好酸球が増加する。呼吸器で寄生虫感染が起きると好酸球が増加し、好酸球の顆粒が素になるシャルコーライデン結晶がみられやすくなる。 - 14. 答え5
サルコイドーシスは結核に似た細胞像を呈する。しかし、結核と違い乾酪壊死はみられない。 - 15. 答え4
1:内胚葉
2:外胚葉
3:内胚葉
5:中胚葉 - 16. 答え3
進行性病変に含まれるのは再生、化生、肥大、過形成など。退行性病変に含まれるのは変性、萎縮、壊死、アポトーシスなど。 - 17. 答え5
1:膵胆道系のマーカー
2:乳癌のマーカー
3:卵巣癌のマーカー
4:腺癌全般のマーカー
5:他にγセミノプロテインも特異的なマーカーの一つ - 18. 答え1
1:流れるようなシート状集塊でみられ、核の腫大・大小不同、明瞭な核小体がみられる。
2:細胞質突起をもつ敷石状配列で出現し、ライトグリーン濃染細胞質、核腫大・大小不同、明瞭な核小体を示す。
3:ケラトヒアリン顆粒は表層細胞の細胞質に見られる顆粒。
4:好塩基性細胞質、核偏在、核周囲明庭、車軸状核を特徴とする。
5:尿路上皮は3層で構成され、その最外層にある大きな細胞をアンブレラ細胞と呼ぶ。 - 19. 答え23
1:ロゼット配列は神経系腫瘍に特徴的な配列で、上衣腫では真のロゼットがみられる。
2:この配列、パターンは線維肉腫で見られる。
3:髄芽腫は小型円形核が特徴。柵状配列は示さない。
4:篩状構造は細胞集塊内に粘液球がいくつか存在する像で腺様嚢胞癌でよくみられる。
5:この配列は細胞が一列に並んだ状態を指す。小葉癌や小細胞癌などでみられる。 - 20. 答え34
アポトーシスは細胞内外のなんらかの刺激で生じ、カスパーゼの活性化を介して最終的にヌクレオソームの単位の核断片化を引き起こす。細胞質は破壊されないため炎症が起きない。最終的には細胞が収縮しアポトーシス小体を形成する。ミトコンドリアを介したアポトーシスではBcl-2などが膜電位を保ってアポトーシスを抑制し、BadやBaxが膜電位を低下させアポトーシスを誘導させる。
- 1. 答え4
- 【技術】の解答
-
- 21. 答え4
A:PAS反応の原理は①過ヨウ素酸で酸化②アルデヒド基が生じる③シッフ試薬で呈色の流れ。
B:中性粘液を染める。
E:間質性粘液や基底膜が異染性を示す。 - 22. 答え3
A:複数箇所から採取する。
D:圧挫法は組織片など塊になっている検体に用いる。
E:すり合わせは3回以内。回数が多すぎると細胞が挫滅して鏡検しづらくなる。 - 23. 答え5
A:陰圧を解除してから針を抜く。
B:蒸留水ではなく生理食塩水やLBC固定液や培養液などで洗浄する。
C:塗抹後乾燥させればギムザ染色も行うことができる。 - 24. 答え1
A:感度は高いが、特異度は低くなる。
B:賦活化は熱処理(オートクレーブ、電子レンジなど)もしくはタンパク分解酵素で処理する。
C:基本的にはヘマトキシリンを用いる。この時のヘマトは進行性のマイヤーが多い。
D:ペルオキシダーゼなどの酵素をたくさん結合できるため感度が高い。
E:洗浄はPBSで行う。 - 25. 答え2
A:退行性のギルのヘマトキシリンを用いる。
B:溶血して細胞を効率よく回収すると良い。
C:細胞が壊れやすいため1000rpm程度の低回転数で遠心する。
E:細胞の回収率が良いため細胞数が少ない検体に有効。 - 26. 答え5
カラーコードは①4倍:赤②10倍:黄③20倍:緑④40倍:青⑤100倍:白である。 - 27. 答え4
A:転座にも有効。遺伝子配列が大幅に変化するものには有効だが、点突然変異など微小な変化には別の方法を行う必要がある。
B:間期にも有効。
C:FISHのFはFluorescence(蛍光)のことで、蛍光色素を使っているため観察は蛍光顕微鏡を用いる。
D:核酸を検出する方法であるため、DNAもRNAも検出できる。
E:多くの色を使った多重染色も可能。 - 28. 答え2
A:オレンジG、エオジン、ライトグリーンの分子量が違う3色素を使って染め分ける。
B:Papのヘマトキシリンは退行性のギルを用いるため分別が必要。
C:ビスマルクブラウンはEA-50液に含まれる。
D:OG-6とEA-50液は95%エタノールで分別する。
E:Papの最大の特性の一つに透過性が良いというのがある。 - 29. 答え1
開口絞りを絞ると①開口数が小さくなる②分解能が低くなる③焦点深度は深くなる④明るさは暗くなる⑤コントラストは増加する。 - 30. 答え3
A:半年に一回行う。
D:3年
E:50ppm以下 - 31. 答え4
4:RNAは逆転写酵素を使ってDNAに変換してからでないとPCRを行えない。 - 32. 答え2
2:ギムザは透過性が悪いため引き終わりを作ると細胞が重なって見づらくなる。
引き終わりを作らずに引ききる。 - 33. 答え2
1:ヘマトキシリンは天然色素でそれ自体には染色する能力はない。
2:水銀を含むのはハリス。ギルはヨウ素酸ナトリウム。
3:カリウムやアルミニウムとレーキをつくらせ正に荷電させる。
4:ヘマトキシリンは全て塩基性色素。
5:進行性は核のみを徐々に染めるため分別が必要ない。 - 34. 答え5
1:冷風で急速乾燥させる。
2:メチレン青とエオジンが含まれ、前者が塩基性色素、後者が酸性色素。
3:細胞透過性が悪いため重積性のある集塊などはみにくい。一方Papanicolaou染色は透過性が良い。
4:乾燥させるため剥離しにくい。
5:pH6.4にすることでロマノフスキー効果を惹起する。 - 35. 答え3
1:起床直後は睡眠中膀胱内に溜まった尿で細胞変性が強いため適さない。随時尿が良い。
2:喀痰の方が変性が強い。基本的に剥離細胞診は変性が加わる。
4:体位変換をして細胞を浮遊させた方が良い。
5:癌の好発部位であるSCJから細胞を採取する必要がある。 - 36. 答え5
1:37%含む水溶液。
2:劇物に分類される。
3:架橋固定が原理。アミノ基を架橋するため免染時に賦活化する必要がある。
4:発がん性が認められている。 - 37. 答え1
1:スキムミルク、生理食塩水などを満載する再水和処理を行うと染色性が改善す
る。
2:水分が残るとその水に色素が移動し退色の原因となる。
3:エオジンに染まりやすくなり、赤みを増す。
4:このアーチファクトは封入前に乾燥することで起きる。
5:ギムザと同様に膨化する。 - 38. 答え4
LBCの欠点は①コストがかかる②従来法と見え方が違うの2つが挙げられる。利点は①塗抹範囲がせまい②標本作製が標準化できる③細胞が重なりにくい④細胞回収率が高い⑤遺伝子検査に応用できるなどがある。 - 39. 答え23
1:細胞膜
2:核
3:核
4:細胞膜
5:細胞質 - 40. 答え34
1:プロテイン銀を使う。
2:鉄が含まれるが銀は含まれない。
3:硝酸銀
4:メセナミン銀液を使用するが、メセナミン銀という銀は無く硝酸銀からつく
る。
5:銀液を使わない。
- 21. 答え4
- 【その他】の解答
-
- 41. 答え1
選択肢ABは悪性中皮腫有意のマーカー。CDEは腺癌に有意なマーカー。 - 42. 答え5
A:10~30代の女性に多い。
B:細菌感染によって生じる。
C:好酸球がみられる。
D:多核組織球や類上皮細胞の出現をみる。
E:多核組織球、類上皮細胞に加えて壊死がみられる。 - 43. 答え3
A:高齢者に多い。
B:アミン、アニリン、ベンチジン、塩化ビニル、オーラミンなどが危険因子。
C:高異型度腫瘍で細胞診で判定しやすい。
D:乳頭状集塊は尿中に出現しにくく、平坦状病変は出現しやすい。
E:尿路上皮癌でなく、腺癌。 - 44. 答え4
骨腫瘍で破骨細胞様巨細胞が目立つのは軟骨芽細胞腫と骨巨細胞腫。骨巨細胞腫の方が核の数が多いと言われる。 - 45. 答え2
A:血管周囲偽ロゼットや真のロゼットがみられる。
E:Homer-Wright型偽ロゼットがみられる。 - 46. 答え1
C:神経鞘腫でみられる所見。
D:乏突起膠腫でみられる所見。
E:膠芽腫で見られる所見。 - 47. 答え3
A:自然尿にはみられにくい。
B:胚細胞腫瘍のセミノーマが最も多い。
C:異型の強い腫瘍細胞と成熟リンパ球の二相性が特徴。
D:PSAが上昇するのは前立腺癌
E:血中βhCGが上昇する。 - 48. 答え4
A:陽性になる。
B:T細胞リンパ腫。
E:発生する。むしろ小児や若年成人に多い。 - 49. 答え2
筋上皮細胞は良性疾患で見られやすい。この選択肢で良性はAとEのみ。 - 50. 答え3
A:原発性のものは少なく、浸潤性や播種性のものが多い。
B:球状集塊を示すものは腺癌の可能性が高い。
C:グリコーゲンを含むためPAS反応が陽性となる。
D:上皮性腫瘍であるため結合性がある。体腔液中ではより結合性が強い状態でみられることが多い。
E:所見の一つに多核がある。あまりに多い多核細胞の場合は中皮腫の可能性が高い。 - 51. 答え5
1:乳腺の異常として最も多い。
2:非炎症性・非腫瘍性の疾患。
3:非炎症性・非腫瘍性の疾患。
4:増殖性変化と退行性変化が共存する。
5:主な変化は①乳管過形成②小葉過形成 ③腺症 ④線維症 ⑤嚢胞 ⑥アポクリン化生 ⑦線維腺腫性過形成 - 52. 答え1
1:自然尿では悪性所見。擦過やカテ尿など物理的に剥離させる採取法では悪性所見とは言えない。
2:紡錘形細胞も見られる。尿で紡錘形細胞がみられた場合は低異型度も考慮する。
3:非浸潤だが壊死を認めることがある。
4:平坦状病変。
5:混在する場合は尿路上皮癌となる。尿路上皮癌と混在する扁平上皮癌や腺癌は基本的に尿路上皮癌になるが、小細胞癌と混在する場合は小細胞癌となる。 - 53. 答え4
4:好塩基性を示す。 - 54. 答え5
1:炎症細胞と多核巨細胞を特徴とする。
2:好酸性濾胞上皮細胞と背景のリンパ球が特徴。
3:大量のコロイド、泡沫細胞、ヘモジデリン貪食組織球などがみられるが、特徴的な細胞像は無い。
4:核溝、核内細胞質封入体など乳頭癌に似た核所見を持つ。
5:アミロイドは髄様癌の背景に見られやすい。 - 55. 答え2
- 56. 答え4
1:中高年に多い。
2:成人に多い。
3:35歳以上に多い。
5:中高年に多い。 - 57. 答え3
1:10~20歳代
2:10歳代
4:10歳代
5:30~60歳代 - 58. 答え1
1:危険因子は①放射線被曝②体重増加③遺伝子異常(FOXE1)などがある。
2:陽性を示す。
3:B細胞性が多い。
4:細胞膜や細胞質に陽性を示す。通常他の腫瘍では核に陽性を示す。
5:砂粒体は乳頭癌で見られやすい。 - 59. 答え12
1:必ずそうとは言えないが、基本的にアンブレラ細胞がみられた場合は良性を考える。
2:これはそのまま。問題文で「~することがある」と書かれているものは〇のことが多い。
3:クロマチン構造は見えないが、核腫大やN/C比増大がみられるため、癌との鑑別を要することがある。
4:男性の方が多い。
5:多発や再発やが多い腫瘍。 - 60. 答え34
1:ホルモンが過剰に分泌されるため、その上位のTSHは減少する。
2:ホルモンが分泌されないため、その上位のTSHは増加する。
3:コルチゾールやアンドロゲンが減少する。
4:ACTHが過剰に分泌されるためアンドロゲンやコルチゾールが増加する。
5:バソプレシンが低下することで尿量が増える。
- 41. 答え1
- 【呼吸器】の解答
-
- 61. 答え5
A:扁平上皮癌で陽性
B:扁平上皮癌で陽性
C:神経内分泌腫瘍で陽性 - 62. 答え4
基本的には真菌を染める染色が陽性となる。
C:軟骨などの間葉系成分を染める。異染性を示す。
D:抗酸菌を染める。 - 63. 答え4
A:扁平上皮癌や小細胞癌で見られる所見。
B:扁平上皮癌で見られる所見。
E:扁平上皮癌で見られる所見。 - 64. 答え3
A:気管支炎、気管支拡張症、喘息、高度喫煙者などでみられる。
B:気管支喘息、肺吸虫症 などアレルギー疾患、寄生虫感染でみられることが多
い。
C:免疫不全患者宿主に感染し、日和見感染症である。
D:慢性気管支炎、肺癌、肺気腫、結核など様々な疾患でみられ、疾患特異性はない。
E:中皮腫の発生に関与する。 - 65. 答え2
A:層状構造を示す厚い細胞質は扁平上皮癌を考える。
B:腺癌の所見。
C:腺癌の所見。
D:良性細胞の所見。
E:扁平上皮癌の所見。 - 66. 答え1
A:腺癌、大細胞癌は末梢に多い。
B:約40%を占め、最も多い。
C:低悪性度。高悪性度は微小乳頭型と充実型。
D:線毛がある場合は良性を考える。
E:腺腔様配列は腺癌で見られる。 - 67. 答え4
A:リスクとなる。その他、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎)、職業的暴露(アスベスト、ラドン、ヒ素、クロロメチルエーテル、クロム酸、ニッケル)、大気汚染(特に粒径2.5ミクロン以下)、肺癌の既往歴や家族歴、年齢などが知られている。
B:非小細胞性肺癌は小細胞癌以外の組織型のことで圧倒的に非小細胞性肺癌の方が多い。
C:小細胞癌と扁平上皮癌は肺門部に多い。
D:STASは肺胞腔内に腫瘍が広がった状態のことで浸潤の定義の一つである。
E:腺癌のドライバー遺伝子変異は80%程度ある。 - 68. 答え5
A:右の方が太く角度が浅い。
B:これはそのまま。
C:これはそのまま。
D:層板小体を持つのは II 型肺胞上皮細胞。
E:II 型肺胞上皮細胞が分泌する。 - 69. 答え2
A:これはそのまま。
B:ゴールドスタンダード染色はグロコット染色でギムザ染色。
C:最も有効なのは気管支肺胞洗浄液(BAL)
D:人工的な培養法は確立されていない。
E:これはそのまま。 - 70. 答え3
A:中枢気管支に多い。
B:これはそのまま。
C:それぞれの成分の割合によって決定されるため細胞診では判定できない。
D:異所性成分が必要。
E:ウイルス感染(EBV)が認められる。 - 71. 答え4
1:塵埃細胞が無ければ不適正。
2:これはそのまま。
3:G-CSFを産生することがあるため好中球を認めることがある。
4:粘膜下腫瘍であるため喀痰には出にくい。
5:これはそのまま。 - 72. 答え2
1:細胞質は広い。
2:これはそのまま。
3:みられる。
4:目立つ。
5:大細胞癌との鑑別のために確認する必要がある。 - 73. 答え1
1:特異性は低い。
2:非上皮性の細胞であるため結合性はない。
3:これはそのまま。
4:これはそのまま。
5:これはそのまま。 - 74. 答え3
1:前縦隔か上縦隔に多い。
2:未熟なTリンパ球がみられる。
3:これはそのまま。
4:B2型が最も多い。
5:重症筋無力症の合併症がよくみられる。 - 75. 答え1
1:背景の成熟リンパ球と異形の強い大型腫瘍細胞がみられる。
2:いくつかの胚葉成分や未熟な神経成分がみられる。
3:甲状腺の濾胞構造がみられる。
4:単核のラングハンス型トロホブラストがみられる。リンパ球は特徴ではない。
5:類円形核の腫瘍細胞が平面的にみられる。 - 76. 答え5
1:置換型増殖を示す。
2:末梢肺に多い。
3:II 型肺胞上皮やクララ細胞由来である。
4:通常0.5cm以下。
5:TTF-1やnapsin Aが陽性となる。 - 77. 答え5
5:OG好性細胞で1/3、LG好性細胞で1/2。 - 78. 答え4
1:高悪性度。
2:挫滅しやすいため核線がみられやすい。
3:変性が加わるため顆粒状や濃縮状のものが多い。
4:光顕で判断できるため必須ではない。
5:喀痰は変性が強い。 - 79. 答え23
1:中枢病変を対象とする。
4:A~Eの5区分で判定する。
5:正常なため判定Bとなる。 - 80. 答え12
1:少数であればあってもよい。
2:他の組織型の存在を否定しなければならないため細胞診では判定できない。
3:陽性を示す場合は腺癌。
4:びまん性に陽性を示す場合は扁平上皮癌。
5:びまん性に陽性を示す場合は扁平上皮癌。
- 61. 答え5
- 【消化器】の解答
-
- 81. 答え1
前癌病変は扁平苔癬、白板症、紅板症である。 - 82. 答え4
A:リスク因子となる。
B:男性に多い。
E:絶縁 - 83. 答え5
A:左側結腸に多い。
B:腺腫からの発生が多い。
C:癌化の頻度が高い。 - 84. 答え4
A:非角化型重層扁平上皮で覆われる。
B:外膜で覆われる。
E:円柱上皮化生のこと。 - 85. 答え3
A:男性に多い。
B:このほかANCA抗体も陽性になる。
C:このほか胆管癌の合併も見られる。
D:これが陽性になるのは原発性胆汁性肝硬変。
E:陽性になる。 - 86. 答え2
A:グラム陰性桿菌。
B:鞭毛をもつ。
C:胃癌、特にMALTリンパ腫と関連がある。
D:陽性を示す。
E:これはそのまま。 - 87. 答え5
A:若年女性に多い。
B:膵体尾部に多い。
C:認められる。
D:これはそのまま。
E:血管がみられ、その周囲に小型均一な腫瘍細胞がみられる。 - 88. 答え1
- 89. 答え2
B:カンジダ感染が多い。
C:無核細胞が多数みられる。
D:この細胞は尋常性天疱瘡でみられる。
E:扁平上皮系が主になる部位ではLBCが有効。 - 90. 答え5
A:大小不同が目立つ。
B:目立たない。目立つのは中分化。
C:みられる。
D:これはそのまま。
E:B型とC型は関与する。 - 91. 答え1
- 92. 答え4
1:B細胞性が多い。
2:消化管の中で胃は最も多い。
3:高齢者に多い。
4:異型が弱いため細胞診での判定が難しい。
5:胃幽門前庭部に好発する。 - 93. 答え3
1:男性に多い。
2:50~70歳代に多い。
4:高分化型が多い。
5:腺癌が多い。 - 94. 答え2
1:CA19-9が主な腫瘍マーカー。
3:膵頭部に多い。
4:粘液性腫瘍であるため粘液がみられる。
5:シート状に出現し広い淡明な細胞質を持つ。 - 95. 答え2
1:粘液の形質によって亜型を決定するため免疫染色をしないと厳しい。
3:頻度は低いが合併することがある。
4:拡張する。
5:低異型度、高異型度、上皮内腫瘍、浸潤癌と多段階的に進展する。 - 96. 答え5
5:インスリノーマだけ良性が多い。 - 97. 答え1
1:胃に最も多い。 - 98. 答え4
1:下部食道に多い。
2:乳頭状病変を呈する。
3:平滑筋腫が最も多い。
4:神経鞘由来であるため陽性となる。
5:きわめて稀な腫瘍の一つ。 - 99. 答え15
1:子宮頸部などと同様の所見が見られるためこの所見もみられる。
2:前がん病変であるため移行する。
3:通常核小体が目立つ。
4:光輝性細胞がみられる。
5:良性なのでNILM。 - 100. 答え45
4:悪性化すると境界が不明瞭になることが多い。
5:胆汁は変性が強いため良性でも核小体が目立ち悪性所見として使えない。
- 81. 答え1
- 【婦人科】の解答
-
- 101. 答え4
1:分娩直前はエストロゲンもプロゲステロンも高値を示す。流産はその状態と類似した状態と考えられるため高値を示す。
2:性成熟期でない年齢で性成熟期と同じ変化が起こる事。つまり高値となる。
3:X染色体の片方が全部もしくは一部欠失した性染色体異常症。卵巣機能が弱いため低値となる。
4:ホルモンの低下によって上皮が菲薄化し炎症を起こした状態。つまり低値となる。
5:卵胞はたくさんできるが成熟しないため排卵が起きない疾患。 - 102. 答え1
HPVが関連するのは旧規約で言うところの①通常型内頸部腺癌②特定不能な粘液性癌③腸型粘液性癌④印環細胞型粘液性癌⑤絨毛腺管癌⑥浸潤性重層性粘液産生癌⑦微小乳頭状パターンを示す通常型内頸部腺癌がある。 - 103. 答え2
A:増殖期は直線、分泌期は蛇行した腺管がみられる。
B:増殖しているため核密度が高くなる。
C:細胞内に分泌物をため込むため広くなる。
D:明瞭になる。
E:核も小さく細胞質も狭小になる。 - 104. 答え1
背景は腫瘍性背景で高度な核異型をもった腫瘍細胞が乳頭状に出現する。背景には砂粒体を見ることがある。
Bは明細胞癌の特徴 - 105. 答え4
A:陽性になる。
B:両側性発生が多い。
C:これはそのまま。
D:高頻度でこの遺伝子に変異がみられる。
E:単房性にみられる。多房性は粘液性癌。 - 106. 答え3
A:存在する。前者は類内膜癌G1,G2、後者は漿液性癌と明細胞癌が該当する。
B:類内膜癌が最も多い。
C:5%以下。
D:エストロゲンに依存しないため関連が低い。
E:基本的に上皮性腫瘍は発生年齢が高い。 - 107. 答え2
A:これはそのまま。
B:傍基底・基底細胞の異型が主体となる。
C:浸潤していないため背景はきれい。
D:ほぼ全例で陽性。
E:これはそのまま。 - 108. 答え4
A:2種類の上皮で被覆され、その境界をSCJと呼ぶ。
B:偏在性核と泡沫状細胞質が特徴。
C:エオジンやオレンジGに好染する。
D:流れの有るシート状集塊で出現する。
E:これはそのまま。 - 109. 答え4
適応はCIN3とIA期 - 110. 答え3
A:親のホルモンの影響を受けてるため中層細胞優位。
B:ホルモンが出ていないため傍基底優位。
C:エストロゲンが有意な時期であるため表層細胞優位。
D:プロゲステロン優位な時期であるため中層細胞優位。
E:プロゲステロン優位で見られやすい細胞であるためホルモンが出ない閉経期にはみられない。 - 111. 答え3
放射線の変化は多岐にわたるため、大体のことは起きると思っていた方が良い。ただN/C比は変わらない。 - 112. 答え5
5:2倍体発生。 - 113. 答え2
1:扁平上皮癌が多い。
3:扁平上皮癌が多い。
4:扁平上皮癌が多い。
5:高齢者に多い。 - 114. 答え1
1:核小体の腫大はみられない。 - 115. 答え4
1:p16が有効。
2:関連するものとしないものがある。
3:6型、11型以外はハイリスク。
4:関連する。
5:DNAウイルス。 - 116. 答え1
1:明細胞癌、類内膜癌と関連がある。
2:原因となる。
3:ブルーベリースポットなどの特徴的な病変がみられる。
4:上昇を認めることがある。
5:血液が卵巣内に溜まってチョコレート嚢胞を示す。 - 117. 答え5
この封入体はクラミジアの特徴。 - 118. 答え5
1:上皮性腫瘍
2:性索間質性腫瘍
3:胚細胞腫瘍
4:上皮性腫瘍 - 119. 答え23
基本的に胚細胞腫が若年者に多い。この選択肢で胚細胞腫瘍は2と3のみ。 - 120. 答え25
- 101. 答え4
細胞診模擬試験 ~難易度4~の解説
80.5%(96.6問正解/120問中)
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度4】は1~3よりも本番に近い形で作成しています。
今までよりも難しく感じるかもしれません。
でも難しいものを解いていくからこそ成長できます。
毎月模試を解いて合格を必ず手に入れましょう!
試験まで一緒に頑張っていきましょう!
- 【総論】の解答
-
- 1. 答え2
B:白人で頻度が高いと言われる。本邦では1~2人/10万人と稀な腫瘍。
C:本邦でも増加しているが、基本的には欧米やアフリカに多い。
D:欧米では逆流性食道炎が多いため腺癌が比較的多い。 - 2. 答え3
A:細胞周期を止める方向には働く。
D:細胞周期はG1、S、G2、Mで1周すると細胞が増殖する。
E:核膜は分裂期の前中期に消失する(参考書によっては中期)。 - 3. 答え1
C:内胚葉
D:外胚葉
E:中胚葉 - 4. 答え4
A:細胞膜が保たれたままの細胞死であるため炎症が起きない。
B:収縮する。
E:核は断片化し、DNA{がヌクレオソーム単位で切断される。 - 5. 答え5
A:子宮頸癌や中咽頭癌と関連する。
B:成人T細胞性白血病と関連する。
C:カポジ肉腫や原発性体腔液リンパ腫と関連する。 - 6. 答え4
- 7. 答え1
Ⅰ型は副甲状腺腫瘍、下垂体腺腫、膵消化管内分泌腫瘍が三大病変。ⅡA型は甲状腺髄様癌、副腎褐色細胞腫、副甲状腺機能亢進症、ⅡB型は甲状腺髄様癌、褐色細胞腫、神経腫が主な病変。
C:I型に含まれる。
D:I型に含まれる。
E:I型に含まれる。 - 8. 答え3
エストロゲンが関連するのは子宮体部と乳腺。 - 9. 答え5
ミトコンドリアは働きが活発な部分に特に多く、肝細胞や尿細管上皮細胞は多いことで有名。 - 10. 答え2
A:これにはジフテリア、偽膜性大腸炎、大葉性肺炎、尿毒症性心外膜炎などが含まれる。
B:これにはヘルペスや肝炎ウイルスなどのウイルス感染でみられることが多い。
C:これは連鎖球菌感染症、ペスト、インフルエンザ、発疹チフス、流行性出血熱、ワイル病などで見られることが多い。
D:これには肝硬変、肺線維症などが含まれる。
E:これには結核、サルコイドーシス、猫ひっかき、梅毒、ハンセン病などが含まれる。 - 11. 答え2
1:未分化胚細胞腫の所見。
3:ヘルペスウイルス感染細胞の特徴の一つ。甲状腺乳頭癌でも同様の所見が
4:顆粒膜細胞腫の所見。
5:平滑筋肉腫の所見。 - 12. 答え2
1:萎縮のこと。変性は核や細胞質などが内外からの刺激によって構造的な変化を示すこと。
2:分化した細胞が他の系統の分化した細胞に変化すること。扁平上皮化生、腸上皮化生、腺上皮化生などがある。
3:肥大のこと。過形成は一つ一つの細胞の大きさは変わらないが、数が増えたことによって組織が大きくなった状態。
4:過形成のこと。肥大は一つ一つの細胞が大きくなることで組織が大きくなった状態。
5:変性のこと。萎縮は一旦正常の大きさになった組織が、細胞数の減少や細胞数が小さくなることで組織が小さくなること。 - 13. 答え4
好酸球は寄生虫やアレルギー疾患で増加することが多い。そのためそれらの疾患では喀痰などの呼吸器検体にはシャルコーライデン結晶が見られやすい。結核はリンパ球や組織球が多く見られ、細菌感染では好中球が多い。 - 14. 答え3
1:仮性菌糸と芽胞が特徴。
2:デコイ細胞の原因となるウイルス。核腫大とすりガラス状核を特徴とする。
3:多核、核圧排、核縁肥厚、核内封入体、封入体周囲のhaloを特徴とする。
4:星雲状封入体を特徴とする。
5:細長い菌が集塊で見られる。 - 15. 答え2
2:4つの精子ができる。卵子は1つ、精子は4つであるため注意。 - 16. 答え1
進行性病変には肥大、化生、再生などが含まれる。退行性には変性、萎縮、壊死、アポトーシスなどが含まれる。 - 17. 答え5
1:腺癌全般のマーカー。肝細胞癌はAFPが有名。
2:乳癌のマーカー。卵巣癌はCA125。
3:肝細胞癌や胎児性癌のマーカー。前立腺癌はPSAやγ-smなど。
4:卵巣癌のマーカー。担当癌はCA19-9。 - 18. 答え3
1:非角化型重層扁平上皮
2:単層円柱上皮
4:角化型重層扁平上皮
5:単層円柱上皮 - 19. 答え25
基本的に腫瘍は男性に多い。各論勉強中に女性に多いものが出たらまとめると良い。 - 20. 答え14
1:神経膠細胞の中間系フィラメント。
2:上皮系細胞の中間系フィラメント。
3:中間系フィラメントではない。
4:神経細胞の中間系フィラメント。
5:間葉系の中間系フィラメント。
- 1. 答え2
- 【技術】の解答
-
- 21. 答え2
B:開口数が大きいと分解能は上がる。
C:分解能の数値が小さいほど分解能が高い。
D:倍率が高いほど焦点深度は浅くなる。 - 22. 答え4
A:膨化する。
B:固定前に行う。固定後に行うと効果が無い。
E:膨化するため不明瞭になる。 - 23. 答え3
A:パパニコロウ染色ではギルを使う。
B:pHは酸性。色素の種類としては塩基性色素なので要注意。
C:オレンジG<エオジン<ライトグリーンの順に大きい。
D:塩基性色素。EA-50に含まれる色素で唯一の塩基性色素。
E:OG-6とEA-50は95%エタノールを溶媒とする。 - 24. 答え5
A:細胞質
B:細胞質
C:核 - 25. 答え5
- 26. 答え3
穿刺吸引は基本的に擦過ができない部位に用いる。体表に近い部分は穿刺しやすいため勿論対象となるが、最近では画像描出の技術向上により消化器や呼吸器を対象とした穿刺も可能となっている。
A:擦過が中心。
D:擦過が中心。
E:擦過が中心。 - 27. 答え1
A:酸化によってギ酸が生じる。
B:ホルマリン(ホルムアルデヒ)は発がん性が指摘されている。 - 28. 答え4
A:特定の配列に結合するプローブを用いて目的配列をもつ核酸を検出する。
B:RNAを検出する。
C:蛋白を検出する。
D:目的の抗原(蛋白)を標本上で可視化する。
E:RNAをDNAに変化させてから検出する。 - 29. 答え1
A:複数のエピトープに反応するのはポリクローナル抗体。
B:ポリクローナル抗体は複数のエピトープに反応するため、モノクローナルより特異性が低い - 30. 答え3
A:レンズの種類、倍率、補正系の種類、開口数、視野数、カラーコードが記載される。
B:倍率と明るさは反比例する。
C:4倍は赤。黄色は10倍のカラーコード。
D:未染標本はコンデンサを下げるか、開口数絞りを絞ると見やすい。
E:レンズではなくレボルバで回転させる。 - 31. 答え5
粘膜下腫瘍は剥離細胞診や擦過などでは採取できないことが多いためEUS-FNAが有効となる。 - 32. 答え2
1:Papanicolaou染色をする場合は引き終わりを必ず作る。
2:速度を上げると短く、ゆっくりすると長くなる。
3:角度は小さくすると長く、大きくすると短くなる。
4:素早く入れる。
5:辺縁や引き終わりに集まりやすい。 - 33. 答え1
1:脱水にエタノール、透徹にキシレンを使う。
2:イソプロピルアルコールとポリエチレングリコールが含まれる。
3:凝固固定が原理である。架橋固定はホルムアルデヒドなど。
4:50%エタノールによる半固定しか行われないため塗抹後再固定する。
5:2日以内に行う。 - 34. 答え2
ギルのヘマトキシリンの組成は①ヘマトキシリン②蒸留水③ヨウ素酸ナトリウム④硫酸アルミニウム⑤エチレングリコール⑥氷酢酸の6つ。結晶性クエン酸はマイヤーの組成。 - 35. 答え3
1:基本的には早朝喀痰を採取する。
2:剥離細胞診であるため擦過検体より変性が強い。
3:血液部分から採取すると血液成分しか見られないことがあるため境界部分から採取する。
4:可能な限り挫滅を防ぐためにすり合わせは3回以内にする。
5:室温では5時間以内。 - 36. 答え3
1:Grimelius染色、Masson Fontana染色、Giemsa染色などで染まる。
2:Gmelim法やHole法で染まる。
3:ヘモジデリンはBerlin blue染色で染める。Congo red染色はアミロイドを染める染色。
4:Masson-Fontana 染色、Schmorl反応で染まる。
5:Masson-Fontana 染色、Schmorl反応で染まる。 - 37. 答え4
1:PBSで行う。
2:過酸化水素、過ヨウ素酸、アジ化ナトリウムで行う。
3:ポリマー法は標識物質をたくさん結合できるため感度が高い。
4:DABは永久標本になり、AECはならない。
5:正常動物血清、アルブミン、スキムミルクなどの蛋白で行う。 - 38. 答え5
1:プロテイン銀を用いる。
2:銀は使わない。
3:硝酸銀を使う。
4:硝酸銀を使う。 - 39. 答え45
- 40. 答え24
1:メチル場尿酸が検出される。
3:記録の保存は3年。
5:半年に一回行う。
- 21. 答え2
- 【その他】の解答
-
- 41. 答え5
A:CD5陽性。CD10, CD23陰性。
B:CD15, CD30陽性。CD20陰性。
C:CD20陽性。CD15, CD30陰性。
D:CD30陽性。
E:CD10, CD20, CD79などがB細胞系が陽性。 - 42. 答え2
A:EBVが関与する。
E:HTLV-1が関与する。 - 43. 答え1
神経内分泌腫瘍に有効なマーカーとしてChromogranin A, synaptophysin, CD56などが知られる。
C:腺癌に有効なマーカー。
D:卵黄嚢腫瘍や肝細胞癌に有効なマーカー。
E:上皮系に陽性となる。浸潤性乳管癌と浸潤性小葉癌のマーカーとしても使われる。 - 44. 答え4
A:尿管と回腸の一部を繋ぐため変性した回腸の腺上皮細胞がみられる。
B:生理食塩水を用いる。
E:E.Coliなどの細菌感染が多い。 - 45. 答え3
A:グリコーゲンを持つため陽性を示す。
D:上皮型は比較的細胞数が多く、肉腫型は体腔液中に出現する細胞が少ない。
E:I 型は良性でよく見られる。悪性はII型やIII型が多い。 - 46. 答え3
A:浸出液が多い。循環障害は濾出液。
D:生理食塩水を使うため貯留検体より変性しやすい。
E:健常者でも少量の体腔液は貯留している。 - 47. 答え2
B:後腹膜、四肢の深部組織、血管壁などに好発する。
C:舌、食道、胸壁、乳腺などに好発する。
D:四肢や体幹の深部に好発する。 - 48. 答え5
A:10歳代に好発する。
B:30~60歳代に好発する。
C:10~20歳代に好発する。 - 49. 答え1
A:良性腫瘍は筋上皮細胞を認めることが多い。
B:核小体が目立つ裸核状細胞が弧在性に出現する。
C:アポクリン化生を伴うことはある。
D:DCISなどでも認めることがあるため断定はできない。
E:乳頭状集塊が見られやすいのは乳管形成型。硬性型は索状配列やくさび状配列などがみられる。 - 50. 答え4
A:皮膚を原発とするT細胞リンパ腫。
B:CD30陽性の大型細胞がみられるT細胞リンパ腫。
C:高悪性度のB細胞リンパ腫。
D:低悪性度の中で最も多いB細胞リンパ腫。
E:菌状息肉症の類似疾患であるT細胞リンパ腫。 - 51. 答え3
1:好酸性の細胞質を持つ細胞がみられる。
2:腫瘍ではなく腫瘍様病変である。
3:多核組織球の出現が特徴的。
4:核溝や核内細胞質封入体は目立つが、すりガラス状核は目立たない。
5:放射性ヨウ素の取り込みが癌と関連していると言われる。 - 52. 答え5
15番染色体にあるPML遺伝子と17番染色体にあるRARA遺伝子が融合したキメラ遺伝子で急性前骨髄球性白血病の90%異常で認められる。 - 53. 答え2
1:細胞質内小腺腔は浸潤性乳管癌や小葉癌で見られる。
2:背景に石灰化小体を認めることがある。
3:PASにもAlcian blueにも陽性を示す。
4:軽度なものが多い。
5:結合性は強く、球状集塊になることが多い。 - 54. 答え1
1:バソプレシンとオキシトシンが産生される。
2:ここからはパラトルモンが産生される。カルシトニンは甲状腺傍濾胞細胞(C細胞)から産生される。
3:ここからはバソプレシン、コルチゾール、アンドロゲンが産生される。カテコールアミンは副腎髄質から産生される。
4:ここからはカテコールアミンが産生される。アルドステロンは副腎皮質から産生される。
5:ここからはカルシトニンが産生される。パラトルモンは副甲状腺から産生される。 - 55. 答え5
大型細胞の出現、目立つ核小体が特徴の腺癌。メラニンを持つこともある。 - 56. 答え5
- 57. 答え2
1:中心性のことが多い。
2:基本的には厚い細胞質をもつ。辺縁は微絨毛の発達によってモヤモヤした淡く染色性を示すこともある。
3:ヒアルロン酸酸性によってアルシアン青が染まる。
4:微絨毛の発達によって細胞辺縁が不明瞭になることがある。
5:多核細胞が多数みられる場合は中皮腫を考慮したい。 - 58. 答え3
1:悪性腫瘍や結核で見られる。
2:サルコイドーシスで見られる小体。
3:多数の腫瘍細胞の中に組織球が見られる像のこと。バーキットリンパ腫でみられる。
4:成人T細胞性白血病/リンパ腫などで見られる異型の強い核を表す。
5:核の中心に穴が開いたように見える構造。未分化大細胞リンパ腫で見られる。 - 59. 答え34
1:バーベック顆粒は組織球が持つ棍棒状の顆粒。組織球由来の腫瘍に認められる。
2:進展することがあるため高分化でも注意。
3:胎児型と胞巣型は小型円形腫瘍。
4:ジアスターゼには消化されない結晶を持つ。
5:シュワン細胞由来であるためシュワン細胞マーカーのS100が陽性となる。 - 60. 答え34
1:甲状腺機能低下症
2:副腎皮質機能低下症
5:下垂体前葉機能低下症呼吸器消化器婦人科
- 41. 答え5
- 【呼吸器】の解答
-
- 61. 答え4
A:硝子軟骨でできている。弾性軟骨は耳介などを構成する軟骨。
B:線毛を持たない。微絨毛をもつ。
C:呼吸器や消化器は内胚葉。
D:気管や気管支は多列線毛円柱上皮。細くなると背が低くなり線毛を欠く。
E:肺胞と肺胞は肺胞孔(コーン孔)で繋がる。ランバート管は肺胞と細気管支を繋ぐ。 - 62. 答え3
A:腺癌が最も多い。腺癌、扁平上皮癌、小細胞癌、大細胞癌の順に多い。
B:非角化型では目立つものもある。角化型では目立たない。
C:中枢に発生しやすい扁平上皮癌と腺癌は喫煙との関連が深い。
D:末梢に多い。
E:低分化な腫瘍で小細胞癌と鑑別が必要なことがある。 - 63. 答え2
A:立体的な集塊は腺癌に特徴的である。
B:小細胞癌や大細胞神経内分泌癌に多い所見。
C:腺癌はライトグリーンに淡染し、泡沫状やレース状の細胞質を示す。
D:層状構造は扁平上皮癌の特徴。層状構造がみられる場合は細胞質に厚みがあると考える。
E:核小体は目立つことが多い。 - 64. 答え4
A:過形成であるため非浸潤性病変である。
B:腺癌と同様にTTF-1もNapsi Aも陽性を示す。
E:核分裂像はほとんど観察されない。 - 65. 答え1
C:神経内分泌腫瘍に含まれる。
D:高悪性度であるためアポトーシスや核分裂像が多い。
E:核小体が目立つことが特徴の一つ。 - 66. 答え1
C:CK20は陰性になる。
D:神経内分泌腫瘍のマーカー。腺癌は陰性。
E:大腸癌のマーカー。通常原発では陰性。 - 67. 答え3
B:孤立性に出現することが多い。高度では集塊になることもある。
C:基本的には扁平上皮癌を疑うが、癌ではない可能性もある細胞群のこと。 - 68. 答え4
A:組織球を認めない場合は唾液や鼻汁が考えられるため判定不能材料とする。
B:生検など組織検査が容易ではないため最終診断になることがある。
E:腺扁平上皮癌は腺癌と扁平上皮癌成分がそれぞれ10%以上を占める必要がある。細胞診や生検検体は腫瘍全体を反映していないためどれくらいの割合を占めているか分からない。そのため細胞診や生検検体では判定出来ない。 - 69. 答え5
D:口腔内の扁平上皮細胞より大きい。
E:細胞質肥厚が顕著で角化傾向が強い。 - 70. 答え2
B:腺癌に多い所見。
C:腺癌に多い所見。
D:腺癌に多い所見。 - 71. 答え4
1:細胞外の粘液が特徴。
2:気腔内の腫瘍細胞塊つまりSTASは浸潤の定義の一つである。非浸潤癌ではこのSTASはみられない。
3:CDX2など腸管分化マーカーが陽性となる。
5:通常の腺癌と異なり、CK20に陽性、TTF-1とNapsin Aが陰性を示す。 - 72. 答え5
小型円形の腫瘍であるため、他の小型円形腫瘍との鑑別が必要な組織型である。 - 73. 答え4
1:空気中にいる真菌だが病原性は低い。棍棒状で黄褐色を示す。
2:Y字状に分岐する菌糸を持つ真菌。
3:直角に分岐する菌糸を持つ真菌。
4:莢膜を有する酵母様真菌。Grocott染色、PAS反応、Alcian blue染色、mucicarmine染色、墨汁法などの染色が有効。
5:放線菌に分類される菌。真菌ではない。 - 74. 答え1
1:真菌であるため、PAS反応やグロコット染色などに陽性を示す。
2:太く直角に分岐する菌糸があり、隔壁を持つ。
3:酵母様真菌であるため菌糸は持たない。
4:弱抗酸性菌でZiehl-Neelsen染色変法のKinyoun染色に陽性を示す。
5:CD4陽性T細胞に感染する。 - 75. 答え1
1:線毛があれば通常は良性を考える。
2:非上皮性細胞であるため結合性が無いのが特徴の一つ。
3:多量の粘液に押されるため核が偏在する。
4:ヘマトキシリンに好染する。
5:好酸球の顆粒に由来する。そのため好酸球が増加する疾患で見られやすい。 - 76. 答え3
1:ROS1、ALKの変異が多い。
2:ROS1、ALK、BRAFの変異が多い。
4:ROS1、ALKの変異が多い。
5:特徴的なドライバー遺伝子変異はない。 - 77. 答え5
p40は扁平上皮癌のマーカー。小細胞癌はsynaptophusin、Chromogranin A、CD56などがマーカーとなる。 - 78. 答え3
3:非喫煙者で(他の肺癌よりも)若年の女性に多い。 - 79. 答え24
ロゼット構造は神経内分泌腫瘍にみられる特徴的な構造である。この選択肢の中で神経内分泌腫瘍は答えの2つのみである。 - 80. 答え14
1:胸腺腫が最も多い。
2:重症筋無力症などの合併がみられる。
4:A型は腫瘍細胞のみでリンパ球がみられない。B型は腫瘍細胞とリンパ球が混在する。
- 61. 答え4
- 【消化器】の解答
-
- 81. 答え1
A:消化管を動かすペースメーカーであるカハール介在細胞由来である。
B:70%は胃発生である。
C:非上皮性腫瘍であるため結合性は弱い。
D:腫瘍径と核分裂像の数で判定される。
E:α-SMAは平滑筋腫瘍のマーカー。GISTはKIT(c-kit、CD117)、CD34、DOG1が免疫染色で有効。 - 82. 答え5
A:Tzank cellは尋常性天疱瘡でみられる。
B:尋常性天疱瘡の特徴細胞はTzank cell。
C:核異型は弱いことが多い。無核細胞が出現する。 - 83. 答え3
A:成熟リンパ球が目立つのはワルチン腫瘍。
B:ワルチン腫瘍は好酸性上皮細胞と成熟リンパ球の二相性が特徴。
C:粘表皮癌は粘液細胞、中間細胞、類表皮細胞の3細胞を見るのが特徴。
D:軟骨様基質は多形腺腫で見られやすい。
E:腺房細胞癌は核異型に乏しい。 - 84. 答え5
A:唾液を分泌する外分泌腺。
B:大唾液腺は耳下腺、顎下腺、舌下腺の3つ。
C:耳下腺は外胚葉、顎下腺、舌下腺は内胚葉。
D:舌下腺は粘液線優位の混合腺、顎下腺が漿液腺優位の混合腺。
E:筋上皮細胞は平滑筋作用を持つためα-SMAに陽性を示す。 - 85. 答え4
変性が強いため、核小体の存在は悪性の基準とはならない。その他、明瞭な細胞質境界、均一なクロマチン、集塊辺縁を覆う平滑な細胞質の存在は良性を考える。 - 86. 答え2
A:鞭毛をもち、移動する。
B:青色に染まる。
C:らせん菌を染めるため染まる。硝酸銀を使う染色。
D:グラム陰性菌。
E:Cag Aタンパクを放出してMALTリンパ腫を引き起こす。 - 87. 答え3
A:若年女性に多い。しかし高齢者にも発生はする。
D:小型の細胞が血管周囲に配列する像が典型的。
E:通常は細胞質に示すが本腫瘍では核に陽性となるのが特徴。 - 88. 答え5
- 89. 答え2
A:他の消化器と違い、内斜、中輪、外縦の3層で構成される。
B:幽門前庭部に多い。
C:アジアの方が多い。
D:ヘマトキシリンに好性。壁細胞はエオジンに好性。
E:幽門腺にはガストリンを分泌するG細胞が発達している。 - 90. 答え4
A:RNAウイルス。肝炎ウイルスでDNAウイルスはHBVのみ。
B:自己免疫性疾患で経口避妊薬は関連しない。経口避妊薬の関連は肝細胞腺腫と限局性結節性過形成。
C:肝硬変、肝炎、肝細胞癌でみられる小体。
D:細胞密度が増加した増殖性病変。
E:肝硬変の合併や癌への進展はない。 - 91. 答え1
筋上皮が見られる腫瘍としては、多形腺腫、筋上皮腫、基底細胞腺腫、基底細胞腺癌、腺様嚢胞癌、上皮筋上皮癌などがある。 - 92. 答え2
1:右側結腸に多い。
2:直腸から連続性に広がり左側に多い。
3:通常の結核と同様に乾酪壊死がみられる。
4:グリコーゲンを持つためPAS反応に陽性を示す。
5:発生する。名前で騙されやすいので気を付けよう。 - 93. 答え3
1:腺癌が最も多い。
2:合併はほとんどない。
4:ほとんどが腺癌であるため、通常は細胞質が淡い。
5:悪性であるため核形不整はみられる。その他の核腫大クロマチン増量などの悪性所見もみられる。 - 94. 答え4
1:CA19-9が有名なマーカー。CA125は卵巣がんのマーカー。
2:男性に多い。胆嚢癌は女性に多い。
3:5年生存率7%以下で予後不良。
5:関連する。他にも糖尿病、肥満なども関連する。 - 95. 答え5
1:周囲肝組織の2倍以上の細胞密度増大を認める。
2:血行性転移は認めない。
3:肉眼的には小結節で境界不明瞭。
4:高分化癌と同様に細胞が小型化してN/C比は増大する。 - 96. 答え3
1:非機能性が多い。
2:良性が多い。インスリノーマ以外は悪性が多い。
3:ガストリノーマではガストリンを産生するためZollinger-Ellison syndromeを引き起こす。
4:神経内分泌マーカーのクロモグラニンA、シナプトフィジン、CD56などが陽性となる。
5:陰性となるのが特徴。 - 97. 答え4
リスク分類は腫瘍径と核分裂像で行われる。 - 98. 答え4
1:最外層は外膜で被覆される。
2:多くは中部に好発する。下部は腺癌が多い。
3:上部は横紋筋のみで構成される。横紋筋と平滑筋が混合するのは中部。下部は平滑筋のみで構成される。
4:扁平上皮癌はグリコーゲンの消費が激しいためルゴールで陰性を示す。
5:早期癌は粘膜内にとどまるもの。粘膜下層までにとどまるものは表在癌。 - 99. 答え15
2:60代の高齢男性に多い。
3:異形が強い。口腔に限らずどこに出来ても基本的には異形が強い
4:ライトグリーン好性を示す。 - 100. 答え24
2:最も癌化しやすいが、発生頻度は低い。
4:癌化の頻度が高い。大腸に加えて骨、軟部腫瘍などを合併する。
- 81. 答え1
- 【婦人科】の解答
-
- 101. 答え3
A:内膜は単層円柱上皮のみ。扁平上皮と円柱上皮で被覆されるのは子宮頸部。
B:増殖期には粘度低下、牽糸性増加、分泌期には粘度増加、牽糸性低下がみられる。
C:膣側が重層扁平上皮、体部側が単層円柱上皮。
D:膣に対して前傾である。
E:平滑筋で構成される。自分で動かせない筋肉は大体平滑筋。 - 102. 答え4
A:卵巣から分泌される。内膜はその影響を受けて腺が増殖する。
B:ほとんどは皮膚と同じ角化型重層扁平上皮で被覆される。
C:表層上皮と呼ばれる立方形の上皮で覆われる。発生学的には中皮と同じであるため中皮と言っても過言ではない。
D:エストロゲンで増殖、プロゲステロンで肥厚する。
E:上皮ではなく間質細胞が脱落膜化する。上皮はアリアスステラ反応を起こす。 - 103. 答え5
A:下垂体前葉から分泌される。
B:下垂体前葉から分泌される。
C:視床下部から分泌される。 - 104. 答え3
A:漿液性癌が最も多い。
D:扁平上皮癌が最も多い。
E:扁平上皮癌が最も多い。 - 105. 答え2
A:性器出血などがみられる。水溶性帯下はHPV非依存性腺癌である胃型腺癌や分葉状頸管腺過形成でみられやすい。
E:ポリープ状の腫瘤を形成するのが特徴。 - 106. 答え1
C:カンジダではなくトリコモナスとの併存が多い。
D:キャノンボールはトリコモナス感染症で見られやすい。
E:星雲状封入体はクラミジア感染で見られる。 - 107. 答え5
A:発生頻度自体は高いが、癌への進行は稀である。
B:従来Ⅱ型腫瘍と呼ばれてきたエストロゲン非依存性腫瘍である。漿液性癌もエストロゲン非依存性腫瘍。
C:閉経後の60代以降に多い。エストロゲン非依存性腫瘍はエストロゲン依存性腫瘍と比較して後発年齢が高い。
D:他にもNapsi Aに陽性を示す。
E:エストロゲン依存性腫瘍は肥満と関連がみられる(脂肪からエストロゲン依がつくられるため)。 - 108. 答え2
A:フロント形成とは正常部分と腫瘍部分の明瞭な境界のことで通常の上皮内腺癌でみられる。
B:低リスクHPV(6型、11型)が関係する。
C:高リスクHPVが関連する。
D:コスモスパターンは分葉状頸管腺過形成で認められる。 - 109. 答え4
A:8000個以上は直接塗抹の適正条件。LBC法は5000個以上で適正。
B:中等度異形成はHSILに分類される。
E:上皮内腺癌はAISと判定される。AGCは腺異型細胞や腺癌疑いの場合に用いる。 - 110. 答え5
A:子宮内膜上皮、間質の集塊や間質集塊中に血管を認めることがある。
B:適応はCIN3、IA1期、IA2期の3種類。
C:発見されることがしばしばある。
D:妊孕性が保たれる。
E:検査および治療目的で行う場合と、検査目的で行う場合がある。 - 111. 答え2
1:増殖期はエストロゲンの作用によって表層細胞主体となる。
2:赤血球、白血球の他、内膜細胞もみられる。
3:デーデルライン桿菌は分泌期に多くみられる。
4:ケラトヒアリン顆粒は増殖期に目立つ。
5:舟状細胞はプロゲステロンの影響で出現するため分泌期にみられる。 - 112. 答え1
1:子宮頸部におよぶものは子宮頸癌、外陰におよぶものは外陰癌に分類される。
2:最も多いのは扁平上皮癌。
3:子宮頸部はほとんどがHPV陽性だが、外陰では40%程度に過ぎない。
4:高齢者に多い。
5:悪性黒色腫はS-100に陽性を示し、外陰悪性黒色腫も通常のものと同様に陽性を示す。 - 113. 答え4
1:砂粒体は漿液性癌の所見。
2:硝子様小球は卵黄嚢腫瘍の所見。AFPの塊である。
3:Call exner bodyは顆粒膜細胞腫の所見。
4:ブレンナー腫瘍はコーヒー豆様の核溝やが特徴。
5:two cell patternは未分化胚細胞腫の所見。腫瘍細胞とリンパ球の2種類の細胞がみられるパターンのこと。 - 114. 答え4
1:正常細胞も良性細胞も悪性細胞も影響を受ける。
2:核や細胞質の増大はみられるが、全体が増大するためN/C比の増大はみられない。
3:小細胞癌>扁平上皮癌>腺癌の順に感受性が高い。
4:小細胞癌は高悪性度で増殖能が高いため感受性が高い。
5:低分化な方が高分化な細胞より感受性が高い。 - 115. 答え5
1:DNAウイルスである。
2:基底細胞に感染する。
3:ASC-USにも50%に感染が認められる。
4:ワクチンは治療ではなく予防に用いられる。
5:軽度異形成は約80%、中等度および高度異形成は約90~100%、上皮内癌および浸潤癌はほぼ100%である。 - 116. 答え2
1:CA125が上昇する。CA15-3は乳がんと関連する。
2:不妊、月経痛、ダグラス窩の閉塞などが生じる。
3:チョコレート嚢胞は卵巣に子宮内膜症が生じた場合に見られるもので明細胞癌や類内膜癌との関連が知られている。
4:腹膜にも病変を形成することがある。
5:治療は薬を用いる場合と手術を行う場合がある。 - 117. 答え1
片側発生のものが多い。 - 118. 答え3
漿液性癌は化学療法の感受性が高いが、再発をきたし予後が悪い。 - 119. 答え45
1:上皮性腫瘍の悪性腫瘍
2:胚細胞腫瘍の悪性腫瘍
3:性索間質性腫瘍の境界悪性~悪性腫瘍。
4:性索間質性腫瘍の良性腫瘍。
5:胚細胞腫瘍の良性腫瘍。 - 120. 答え12
3:部分奇胎は部分的に異常があるため胎児性分が見られてもよい。
4:全奇胎の方が部分奇胎より絨毛癌や侵入奇胎に進行しやすい。
5:全奇胎は父親由来の遺伝子で構成された2倍体である。
- 101. 答え3
細胞診模擬試験 ~難易度5~の解説
75.6%(90.7問正解/120問中)
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度5】は1~3よりも本番に近い形で作成しています。
今までよりも難しく感じるかもしれません。
でも難しいものを解いていくからこそ成長できます。
毎月模試を解いて合格を必ず手に入れましょう!
試験まで一緒に頑張っていきましょう!
- 【総論】の解答
-
- 1. 答え1
A:卵黄嚢腫瘍に見られる。血管周囲に高円柱状腫瘍細胞が配列し、その外側の空隙を介してさらに扁平な腫瘍細胞が取り囲む状態を表す。
B:中皮腫や肺癌などと関連する。黄金色で鉄アレイ状の形を示す。
C:サルコイドーシスで見られとされるが特異性は無い。細胞質に見られる石灰化物である。
D:甲状腺乳頭癌、漿液性癌、粘液性癌などで見られる。石灰化物でコッサ反応に陽性を示す。
E:マラコプラキアでみられる。カルシウムと鉄の沈着を伴った層状同心円状構造を有する小球。 - 2. 答え2
A:肺の機能血管
B:心臓の栄養血管
C:肺の栄養血管
D:肝臓の栄養血管
E:肝臓の機能血管 - 3. 答え3
A:男性の罹患数、死亡数ともに2位。
B:男性罹患数の1位。
C:男性死亡数の1位、罹患数の4位。
D:男性の罹患数、死亡数ともに3位。
E:男性死亡数の4位。罹患数は5位以内に入っていない。 - 4. 答え3
A:子宮頸癌や中咽頭癌などと関連する。
B:乳がん、子宮体がんなどと関連する。
C:食道腺癌に関連する。日本より欧米に多い。
D:上咽頭癌やいくつかのリンパ腫などと関連する。
E:胆道癌の原因として知られる。肝癌は肝炎ウイルスやアルコール、肝炎、肝硬変などが原因となる。 - 5. 答え4
A:腺癌の特徴。
B:小細胞がんの特徴。
E:腺癌の特徴。 - 6. 答え5
A:悪性黒色腫、甲状腺癌、肺癌、大腸癌などでみられる。
B:膵臓癌、大腸癌、肺癌、子宮体癌などでみられる。
C:脳腫瘍、肺癌、胃癌、胆管癌、卵巣癌などでみられる。
D:未分化大細胞リンパ腫、肺癌、大腸癌、乳癌などでみられる。
E:乳癌、胃癌などでみられる。 - 7. 答え1
A:細胞内外どちらの刺激からでも起きる。
B:細胞が収縮し、細胞質突起(ブレブ)を生じる。
C:ATPを消費して行う。
D:DNAの不規則な断片化が起きる。
E:細胞も細胞小器官も膨化する。 - 8. 答え4
A:静脈血も動脈血も類洞を通る。
B:胆汁は肝臓から外に流れ、血液は外から肝臓に流れ込む。
C:静脈血は門脈を通って肝臓に流れる。
D:多くは門脈系の静脈血(約70%)である。
E:小葉間静脈から中心静脈の方向に流れる。 - 9. 答え2
4大組織の上皮以外から発生する腫瘍は全て非上皮性腫瘍。
4大組織が分からない人はこちら。 - 10. 答え3
A:皮膚がん、白血病、甲状腺癌などと関連する。
B:皮膚がんと関連する。
C:子宮体癌と関連する。
D:膀胱癌と関連する。
E:皮膚がんと関連する。 - 11. 答え4
1:棍棒状の形をした真菌。
2:隔壁を持つ45度に分岐する真菌。
3:莢膜を持つ酵母様真菌。
4:隔壁を持たない真菌。
5:抗酸性の細菌。 - 12. 答え2
1:細胞増殖に関与するため癌遺伝子。
2:HIF-1αのユビキチン化に関連する癌抑制遺伝子。
3:細胞周期に促進に関与するため癌遺伝子。
4:細胞増殖に関与するため癌遺伝子。
5:細胞増殖に関与するため癌遺伝子。 - 13. 答え2
1:中胚葉
2:外胚葉
3:内胚葉
4:中胚葉
5:内胚葉 - 14. 答え4
1:核内に空砲を認めることがある。
2:核内空砲を認めることがある。
3:核内空胞を認めることがある。嚢胞に関連する症例では細胞質にも認めないわけではないが、典型例では核内に空胞がみられる。
4:細胞質に空胞がみられる。
5:空胞はみられない。多核が特徴。 - 15. 答え5
- 16. 答え3
このほか進行性病変には肥大、再生、過形成なども含まれる。 - 17. 答え4
- 18. 答え5
- 19. 答え35
1:インスリノーマの場合は低血糖を起こす。その他のグルカゴノーマ、ソマトスタチノーマ、ガストリノーマなども元々のホルモンに合わせた症状が起きる。
2:副腎髄質発生が多く、ここからは元々血圧をあげるカテコールアミンが産生される。そのため高血圧になる。
3:重症筋無力症は胸腺腫との合併が良く知られている。
4:小細胞癌は様々な症状を呈することがあり、その一つにクッシング症候群がある。
5:カルシトニンを産生する甲状腺髄様癌でカルシウム濃度低下が起きることがある。乳腺髄様癌では起きない。 - 20. 答え45
1:上皮が筋層まで嵌入した構造で胆嚢に存在する。
2:98~99%は外分泌腺。
3:非角化型重層扁平上皮で被覆される。
4:内斜、中輪、外縦の3層でできている。
5:十二指腸壁内で合流する。壁外で合流した場合、逆流などが起こり胆道癌のリスク因子となる。
- 1. 答え1
- 【技術】の解答
-
- 21. 答え3
A:気管支は擦過や穿刺などの対象となる。
B:体腔液などの液状検体は引きガラス法や集細胞法などが用いられる。
C:脳腫瘍は柔らかい組織であるため圧挫法が有効。
D:喀痰などの粘稠検体はすり合わせ法で行う。
E:口腔は綿棒などで擦過を行う。 - 22. 答え2
1:腫瘤の中央は壊死していることがあるため辺縁を穿刺する。
2:脳脊髄液は細胞が壊れやすいため1000 rpm程度の低回転数で遠心する。
3:すり合わせは細胞の挫滅を防ぐため3回以内におさめる。
4:セルブロックは細胞数が多い検体でないと行うことができない。
5:血液が多い場合は2回遠心法や溶血が有効。 - 23. 答え4
A:ヒアルロン酸はアルシアン青やコロイド鉄染色で染まる。
B:3価の鉄はベルリン青染色が有効。
C:石灰化小体はカルシウムを含むためカルシウムを染めるコッサ反応が有効。
D:クリプトコッカスはムチカルミン、アルシアン青、PAS反応、マッソン・フォンタナ染色、墨汁法が有効。
E:スピロヘータにはワルチン・スターリー染色が有効。 - 24. 答え5
A:直接法より間接法の方が感度が高い。
B:ポリマー法はアビジンを使わないため内因性ビオチンの影響を考えなくて良い。
C:DABは茶色に発色する。
D:過酸化水素、過ヨウ素酸、アジ化ナトリウムなどで行う。
E:緩徐に冷やさないと偽陰性化などを示す。 - 25. 答え2
A:薄切が行えるため数種類の染色に対応できる。
B:液状検体に使用できるため体腔液などに有効。
C:塩化カルシウム溶液を用いる。
D:ブロックのするため薄切が必要。
E:FISH法や遺伝子検査にも対応できる。 - 26. 答え3
A:空気より重い。
D:作業環境測定は半年に一回行う。
E:発がん性はない。 - 27. 答え1
A:位相差顕微鏡は無色の細胞や生きた細胞に適する。
B:偏光顕微鏡は変更を示すアミロイドやケイ酸結晶などに適する。
C:蛍光顕微鏡は蛍光抗体法など蛍光色素を用いた方法に有効。
D:電子顕微鏡は通常の顕微鏡ではみれない小さなウイルスなどに有効。
E:微分干渉顕微鏡は無色の細胞や生きた細胞に適する。 - 28. 答え5
A:ホルマリンはホルムアルデヒドを約37%含む。
B:劇物に指定されている。
C:管理濃度は0.1ppm以下。 - 29. 答え4
A:陰圧を解除して針を抜く。
B:少ない場合は一回合わせるかそのまますぐに固定する。
C:どちらもある場合は充実部分を穿刺する。
D:吹き付け後の針内にも細胞が残るため洗浄して回収すると良い。
E:針先は何度が動かした方が採取効率が良い。 - 30. 答え2
A:OG-6液にはリンタングステン酸、オレンジG、95%エタノールが含まれる。
B:ギルのヘマトキシリンを用いる。
C:オレンジGなど細胞質に関連する染色は全て酸性色素。
D:EA-50液にはライトグリーン、エオジン、ビスマルクブラウンの3色素が含まれる。
E:分別は0.5%程度の塩酸アルコールで行う。 - 31. 答え3
視野絞りは顕微鏡の最も下部に設置されていることが多く、名前の通り視野の範囲を絞ることができる。ケーラー証明の設定時などに行う。 - 32. 答え4
1:擦過検体は浮遊細胞診検体(例えば喀痰や尿など)と比較して新鮮で変性が少ない。
2:引きガラス法では辺塗抹縁や引き終わりに癌細胞が集まりやすい。
3:湿固定する場合、迅速に行わないといけないため、溝に沿って入れずにすぐ固定して少し時間がたってから溝に入れなおす。
4:液状検体を遠心すると上清、バッフィーコート、赤血球層に分かれる。癌細胞はバッフィーコートに存在するためそこを採取する。
5:乾燥固定は冷風で急速に行う。 - 33. 答え5
ビスマルクブラウンは細胞質の染色関与しない。類脂質やカンジダを染めるとされる。塩基性色素である。 - 34. 答え1
Alcian blue染色はpH1.0は硫酸基のみ、pH2.5は硫酸基とカルボキシ基と反応する。それぞれ塩酸と酢酸を用いる。 - 35. 答え1
1:細胞診検体の方がパラフィン切片より活性が高い。
2:平面的な細胞集塊よりも重積性のある部分で偽陰性化が起きやすい。
3:DABは発がん性があるため扱いに注意する。
4:パパニコロウ染色後に封入されたものでも免疫染色は可能である。
5:Ki-67など細胞周期を反映した抗体を利用すれば増殖能をみることが可能である。 - 36. 答え2
1:細胞が沈殿しているため体位変換して細胞を浮遊させた方が良い。
2:抗凝固剤の作用が弱いため、できる限り早く処理する。
3:滲出液の方はタンパク濃度が高いため漏出液より変性速度が遅い。
4:冷蔵保存すれば変性がおさえられ、48時間程度経過しても細胞判定が可能。
5:洗浄は生理食塩水で行う。 - 37. 答え4
1:同じ動物種だと反応しないため異なる動物種を用いる。
2:蛍光は時間とともに減弱するため永久標本にならない。
3:DABが水溶性、AECは非水溶性である。そのため封入剤はDABが非水溶性、AECは水溶性を用いる。
4:LSAB法はアビジンとビオチンを使う方法であるため内因性ビオチンの除去が必要。
5:抗原賦活化はオートクレーブ、電子レンジなどの熱処理、蛋白分解酵素などで行うことができる。 - 38. 答え5
病理分野でとりあえずおさえたい特定化学物質は①ホルムアルデヒである。キシレンやアセトンやメタノールは有機溶剤中毒予防規則の対象となる。 - 39. 答え34
1:大きく分けると吸引吸着転写法と沈降静電接着法があり、これらの作製法の違いで見え方がが異なる。
2:多くのLBC固定液にはアルコール入っているため従来法と比べると収縮傾向を示す。
3:細胞は重なりにくいのが特徴の一つ。
4:炎症細胞や赤血球などの背景所見が減弱しやすい。
5:塗抹後残った検体は免疫染色や遺伝子検査などに応用できる。 - 40. 答え13
1:DABなどで発色するのはCISH。FISHはFITCなどの蛍光色素を用いる。
2:転座など塩基配列が大きく変化するものは検出できる。
3:一塩基多型など塩基配列の変化が乏しいものは検出に不向き。
4:DAPIやPIなどを用いる。
5:熱変性させて核酸を1本鎖にする必要がある。
- 21. 答え3
- 【その他】の解答
-
- 41. 答え1
A:肝臓でエストロゲンの処理が行われているため肝機能低下をきたす疾患は女性化乳房の原因となる。
B:顆粒状の豊富な細胞質、核小体明瞭円形核が特徴。
C:p63は筋上皮細胞のマーカーとして使われる。
D:良性疾患は基本的に筋上皮細胞の付着を認める。
E:名前の通り腺上皮(乳管上皮細胞)も筋上皮細胞も増生する。 - 42. 答え3
A:篩状型ではなく充実-乳頭型に多い。
B:いくつかの亜型が混在していることが多く、多彩な像を示す。
C:面皰型は中心に壊死を持つ型もことであるため壊死がみられる。
D:細胞診で浸潤と非浸潤を鑑別することはできない。非浸潤癌をある程度予測することは可能。
E:良性や非浸潤癌ではアポクリン化生を伴うことがある。 - 43. 答え2
B:Grade2に分類される。
C:Grade3に分類される。
D:Grade4に分類される。 - 44. 答え5
A:正常でも少量の胸水、腹水などの体腔液は貯留している。
B:中皮細胞は良悪性にかかわらず多核になることがある。悪性の方が核の数は多くなることが多い。
C:肝硬変や心不全などでは漏出液が貯留する。癌は滲出液。
D:気胸や寄生虫感染では好酸球が認められる。
E:脳脊髄液は細胞数が少なく細胞が壊れやすいのが特徴。 - 45. 答え4
A:早期の転移例が多く、予後が悪い。
B:白人に多い。
C:S100.NSE、Mealan A、HMB-45などに陽性を示す。
D:比較的広い胞体をもち核小体が目立つ。
E:メラニン顆粒を認めないものも存在する。 - 46. 答え4
A:強い好塩基性を示す。
B:細菌感染では好中球の増加がみられやすい。
C:グリコーゲンを持つためPAS反応に顆粒状の陽性を示す。
D:小さな核小体を認めることがある。
E:2核程度の多核はしばしばみられる。3核以上の多核細胞が多い場合は中皮腫も考慮する。 - 47. 答え3
A:胚中心に存在する組織球。そして胚中心の存在は良性示唆する。
B:monotonousな細胞の増生は悪性を考える。 一方、各分化成熟段階がみられる細胞の増生は良性を考える。
C:10~30代の比較的若年の女性に多い。
D:小児や若年の成人女性に多い疾患でバルトネラ感染が関係する。
E:乾酪壊死を認めない肉芽腫性疾患を非乾酪性肉芽腫と呼び、サルコイドーシスはこれに該当する。 - 48. 答え5
A:副腎皮質の束状帯細胞から分泌される。
B:傍濾胞細胞は甲状腺濾胞間にみられる細胞でカルシトニンを分泌する。
C:下垂体後葉からはオキシトシンとバゾプレシンが分泌される。
D:副甲状腺は主細胞と好酸性細胞があり、主細胞からパラトルモンが分泌される。
E:エストロゲンは主に卵胞の顆粒膜細胞から分泌される。 - 49. 答え2
A:良性腫瘍であるため結合性は比較的強く筋上皮細胞も認められる。
B:組織像が多彩であるため細胞像も多彩になる。この多彩性の具体例としてはアポクリン化生、嚢胞、腺症、小葉過形成、乳管過形成、線維症などがある。
C:上皮・間葉系混合腫瘍であるためどちらの細胞もみられる。
D:細胞量が多く、乳管上皮と間質細胞の両方が見られる。
E:上皮細胞には異型を示さず間質細胞に異型を示す。 - 50. 答え1
A:女性の方が多く、男性の10倍程度である。
B:この好酸性細胞質はミトコンドリアの存在による。
C:すりガラス状核は乳頭癌や硝子化索状腫瘍でみられる。
D:びまん性硬化型乳頭癌は多数の砂粒体を認めることが特徴とされる。
E:アミロイドは髄様癌で見られやすい。 - 51. 答え4
1:10歳代の若年者に多い。
2:粘液ではなく、グリコーゲンに反応して陽性を示す。
3:小型円形腫瘍細胞を特徴とする。そのため小型円形腫瘍細胞の出現を認めるその他の腫瘍との鑑別は難しいことがある。
4:大腿骨などの長管骨の骨幹端に好発する。
5:ロゼット構造を認めることもある。 - 52. 答え3
1:上皮内癌は平坦病変である。平坦病変は膀胱鏡で確認しづらいため細胞診が有用となる。
2:どんな腫瘍でも浸潤癌と非浸潤癌を細胞診で鑑別することは容易ではない。確実に断定することはできない。
3:これはそのまま覚えて欲しい。
4:紡錘形細胞は認められる。異型はそれほど強くないが、紡錘形細胞が目立つ場合は低異型度で考えたい。
5:カテーテル尿は無理やり細胞を剥離させるため細胞集塊が見られやすい。集塊だからと言って悪性というわけでは無いので注意したい。 - 53. 答え2
1:多クローン性のリンパ増殖性疾患。良性疾患であるため小型リンパ球を主体とした細胞像を示すが、形質細胞が多数認める症例がある。
2:t (14 : 18)がみられ、この転座によりBCL2に異変が起きアポトーシスに異常をきたす。
3:マントル細胞リンパ腫はリンパ節にあるマントル層の細胞由来の腫瘍でB細胞性。
4:好塩基性の細胞質、車軸状核、核周囲明庭、偏在性核などを特徴とする。
5:最も多いのはびまん性大細胞型B細胞リンパ腫。ホジキンリンパ腫は5%程度で稀。 - 54. 答え2
1:孤立散在性や乳頭状、マリモ状など様々な出現様式で見られる。
2:Collagenous stromaを囲むことがあるが、層構造は1層でI型Collagenous stromaをと呼ばれる。
3:核は類円形で軽度の核腫大がみられる。核小体も目立つこと多い。
4:2核や3核の多核細胞がみられる。3核以上の多核細胞が多い場合は悪性も考慮したい。
5:細胞同士のクロマチン構造は一様で良性を考える所見である。 - 55. 答え1
1:SV40はポリオーマウイルスのBKウイルスやJCウイルスの検出に有効な抗体。デコイ細胞はBKウイルス感染が原因であるためデコイ細胞に有効である。
2:尿細管上皮や尿路上皮にウイルスが感染し特徴的な細胞所見を示す。
3:顕著な核腫大を示すため高異型度尿路上皮癌との鑑別を要することがある。
4:ポリオーマウイルスのBKウイルス感染が原因。
5:偏在性核の傾向を示し、その細胞はコメット細胞とも呼ばれる。 - 56. 答え5
1:腺癌優位なマーカーで鑑別に有用。
2:中皮腫優位なマーカーで鑑別に有用。
3:腺癌優位なマーカーで鑑別に有用。
4:中皮腫優位なマーカーで鑑別に有用。
5:反応性中皮と悪性中皮腫の鑑別に有用なマーカー。腺癌と中皮腫は陰性となるため鑑別に有用ではない。 - 57. 答え4
1:癌は外腺に発生しやすいため症状が出ないことも多い。
2:造骨性の骨転移を特徴とする。
3:核小体が目立つのが組織所見、細胞所見ともに特徴の一つ。
4:腺房由来が多いため腺房腺癌とも呼ばれる。
5:正常では基底細胞が存在し、癌になると消失するため鑑別の指標となる。 - 58. 答え1
1:濾胞癌は血行性、乳頭癌はリンパ行性転移が多い。
2:乳頭癌は微小癌が多く予後の良いものが多い。
3:乳頭癌をはじめ甲状腺がんの多くは女性に多い。未分化癌は比較的男性に多い。
4:核内細胞質封入体は乳頭癌の特徴的な所見の一つではあるが、硝子化索状腫瘍や髄様癌などでもみられるため一つの所見で断定はできない。
5:sanderson polsterは腺腫様甲状腺腫でみられる構造。 - 59. 答え13
1:前頭葉に多い。
2:第四脳室や側脳室などに多い。
3:小脳中部に多い。
4:松果体に多い。
5:聴神経(第Ⅷ脳神経)に多い・ - 60. 答え45
1:紡錘形細胞の増生と花むしろ状構造を特徴とする。CD34に陽性を示す。
2:高分化型はMDM2やCDK4が陽性となる。脂肪芽細胞はS100陽性であることも覚えたい。
3:線維肉腫は魚骨様形態(herring born pattern)、杉綾模様と呼ばれる形態が特徴。
4:平滑筋肉腫は葉巻状核が特徴で出目金細胞は横紋筋肉腫で認められる。
5:神経鞘腫のAntoni A型は観兵配列がみられ、Antoni B型は比較的異型の強い腫瘍細胞の疎な分布を特徴とする。
- 41. 答え1
- 【呼吸器】の解答
-
- 61. 答え4
A:杯細胞は中枢に多く、末梢に行くほど少ない。最終的にはみられなくなる。
B:線毛は終末細気管支までみられる。
C:層板小体はII型肺胞上皮細胞でみられる。
D:サーファクタントはClub細胞とII型肺胞上皮細胞が分泌する。
E:肺胞表面積を占める割合はI型の高い。数はII型の方が多いとされる。 - 62. 答え3
A:重層扁平上皮
B:多列線毛円柱上皮
C:多列線毛円柱上皮
D:重層扁平上皮
E:重層扁平上皮 - 63. 答え1
A:細胞質の肥厚は著明で角化傾向も強い。
B:高度な炎症や肺結核などで典型的な細胞がみられる。
C:口腔扁平上皮細胞よりも小さい。
D:平面的な敷石状配列を示す。
E:平面的な集塊で出現する。 - 64. 答え2
A:原因はPneumocystis jiroveciiで真菌に分類される。
B:Papではライトグリーンに染まる泡沫状集塊として観察される。
C:有効な検体の一つに気管支洗浄液がある。喀痰では検出されにくいことがある。
D:Pneumocystis jiroveciiは培養ができないため細胞診などでの検出が有効となる。
E:ギムザ染色とグロコット染色が有効な特染。 - 65. 答え4
A:A判定は組織球が認めらない場合の区分である。組織球と正常扁平上皮細胞のみ見られた場合はB判定とする。
B:D判定の指導区分は直ちに精密検査。再塗抹または6か月以内の再検査はC判定に適用される。C:CかDかで迷ったらD判定にする。
D:肺門部の早期肺癌検出を主な目的として行う。
E:C判定標本には扁平上皮癌を疑う細胞はみられない。陰性を考える区分である。 - 66. 答え5
A:上縦隔に発生しやすい。
B:後縦隔に発生しやすい。
C:前縦隔に発生しやすい。
D:前縦隔に発生しやすい。
E:中縦隔に発生しやすい。 - 67. 答え3
A:最も多いのはEGFR変異、肺腺癌の約50%にみられる。
B:腺癌が最も多いが、その他の組織型でも認められないわけでは無い。
C:クリゾチニブはALK融合遺伝子やROS1融合遺伝子をもつ切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に用いられる分子標的治療薬である。
D:ALK変異は腺房型や充実型の腺癌に多いとされる。
E:BRAF遺伝子変異は男性の喫煙者に頻度が高い。EGFR、ROS1、ALKとは少し異なる患者所見を持つ。 - 68. 答え5
細胞診の推定組織型で用いないのは①上皮内腺癌②微小浸潤腺癌③大細胞癌④腺扁平上皮癌⑤肉腫様癌⑥非扁平上皮癌 - 69. 答え4
A:扁平上皮癌は中枢発生が多い。末梢発生のものも増加傾向ではある。
B:CK5/6は扁平上皮癌のマーカーではあるが細胞質に染まる。
C:角化型は類円形細胞から紡錘形細胞まで多形性に富む細胞像を示す。
D:類基底細胞型は低分化で予後の悪い腫瘍。
E:TTF-1は腺癌のマーカーであるため扁平上皮癌は陰性。 - 70. 答え1
A:喫煙との関連が強く中枢気管支に発生しやすい。
B:増殖が速いため手術の適応は少ないが、放射線や化学療法は効きやすい。
C:増殖が速く、早期に転移しやすいため高悪性度腫瘍である。
D:核小体は目立たない。小型の核小体であればみられないわけではない。
E:免疫染色は必須ではなく光顕のみで診断することが可能。 - 71. 答え2
1:腺癌の特徴的な構造は乳頭状、微小乳頭状、細胞集塊辺縁の平滑、核の飛び出しなどがある。
2:集塊辺縁の毛羽立ちや扁平化は扁平上皮癌の特徴。
3:乳頭状や微小乳頭状構造は腺癌の特徴。
4:集塊辺縁からの核の飛び出しは腺癌の特徴。
5:粘液空胞は腺癌の特徴。 - 72. 答え4
1:これはそのまま。
2:多核白血球やリンパ球の浸潤をみるとされる。以前はG-CSFを産生する腫瘍として記載があり、その効果によって多核白血球が見られると思われる。
3:これはそのままで、EBVの関連が証明されないと確定ができない。
4:主気管支から区域気管支のいわゆる中枢気管支に発生する。腺様嚢胞癌も同様に中枢気管支発生が多い。
5:サイトケラチン、ビメンチン、アクチン、S100、KITが陽性を示す。 - 73. 答え5
1:通常、広範な壊死を認めることが多い。
2:TTF-1は陽性となることが多い。小細胞癌よりは陽性率が低いとされる。
3:小細胞癌と違い免疫染色などで神経内分泌分化を確認する必要がある。
4:核小体が目立つが特徴の一つ。
5:細胞質は広いものが多い。 - 74. 答え1
chromogranin A陽性、腺癌および扁平上皮癌マーカー陰性から神経内分泌腫瘍が考えられる。今回の選択肢では1と5が神経内分泌腫瘍に該当するが、大型の細胞がみられるという組織像から小細胞癌は除外される。 - 75. 答え3
1:本組織型は背景に成熟リンパ球は認められるが、核小体が目立つ異型の強い2核細胞や分葉状核細胞も見られるため除外される。
2:本組織型はリンパ球が少ない腫瘍であるため除外される。
3:問題の所見に全て合致する組織型である。
4:本組織型はリンパ球が少なく異型の強い腫瘍細胞がみられるため除外される。
5:本組織型は背景にリンパ球は認められるが、異型の強い大型の細胞が認められるため除外される。 - 76. 答え1
1:真菌症はアスペルギルス症が最も多い。
2:真菌であるためグロコット染色で陽性となる。
3:放線菌に分類されるアクチノマイセスやノカルジアは硫黄顆粒を形成する。しかし、ノカルジアは硫黄顆粒の形成が少ない。
4:真菌の一種。そのためグロコット染色で陽性となる。その他ギムザ染色も有効。
5:サイトメガロウイルスが5型のヘルペスウイルスである。 - 77. 答え2
1:悪性度の高い腫瘍であるため、核分裂像やアポトーシスが多くみられる。
2:細胞の大きさはリンパ球の3倍程度までいうのが一般的である。リンパ球より大きいものの方が多い印象。
3:血流的に脳転移が多い。
4:異所性ホルモンなどを分泌することがあり、様々な腫瘍随伴症候群を示すことがある。
5:小型ではあるが、細胞の大小不同や異型は著明。 - 78. 答え5
1:腫瘍内の壊死は浸潤性の判定となる。
2:上皮内腺癌や微小浸潤癌など浸潤がみられないまたは軽微なものは置換型増殖を特徴とする。
3:3cm以下の孤立性腫瘍である。
4:STASの存在は浸潤性の判定となる。
5:浸潤部分は最大径が0.5cm以内で総和でなく最大のものを計測する。 - 79. 答え23
1:増殖は緩徐。
2:末梢、中年男性に多い。
3:これはそのまま。
4:悪性化は稀。
5:粘膜下腫瘍であるため喀痰には出現しにくい。経気管支針生検などで採取する必要がある。 - 80. 答え45
1:これはそのまま。
2:これはそのまま。
3:これはそのまま。
4:ほとんど重喫煙者から発見されるため喫煙と関連がみられる。
5:癌化率は約30%。軽度や中等度は3%程度。
- 61. 答え4
- 【消化器】の解答
-
- 81. 答え5
A:Tzank cellが認められるのは尋常性天疱瘡。扁平苔癬はケラトヒアリン顆粒を含む細胞とツートンカラーを示す細胞がみられる。
B:癌化はしない
C:CK13は正常口腔扁平上皮で陽性、上皮内腫瘍で陰性。CK17は正常口腔扁平上皮で陰性、上皮内腫瘍で陽性。
D:口腔癌は高分化型扁平上皮癌が多い。
E:白板症は異常角化を示す病変であるため無核細胞が多数みられる。 - 82. 答え2
A:これはそのままで、組織的に二相性を示す。
B:非常にまれな腫瘍で発生頻度が低い低悪性度腫瘍。
C:MALTリンパ腫が最も多い。びまん性大細胞型B細胞リンパ腫は2番目に多い。
D:悪性腫瘍では最も多く、低悪性度のものが多い。
E:ARとGCDFP15が高率に陽性を示す。 - 83. 答え3
A:多形腺腫は軟骨様粘液基質、結合性の緩い上皮細胞集塊、多彩な形態の筋上皮細胞を特徴とする。中でも形質細胞様の筋上皮細胞は特徴とされる。
B:粘表皮癌は粘液保有細胞、中間細胞、扁平上皮様細胞の3種類が特徴。
C:唾液腺導管癌は壊死性背景にライトグリーン好性の細胞質が豊富な核小体が目立つ異型細胞がみられる。
D:Warthin腫瘍は好酸性上皮細胞とリンパ球が特徴。嚢胞形成を伴うため嚢胞内成分(コレステリン結晶、壊死、扁平上皮化生細胞、組織球、類でんぷん小体)などもみられる。 - 84. 答え5
A:最も多いのは扁平上皮癌。
B:男性の方が5倍くらい多い。
C:疣贅癌の頻度は少ない。
D:HPVとの関連は言われていない。
E:類基底細胞癌は男性に多いが、通常の扁平上皮癌に比べると女性の割合が高い。 - 85. 答え1
A:軟骨様粘液基質が見られるためメタクロマジーを示す。
B:基底膜様物質を集塊辺縁に認めるためメタクロマジーを示す。 - 86. 答え4
A:正常肝から発生し、肝硬変からは発生しない。
B:感受性が高いため、シスプラチンを含む化学療法が標準治療となる。
C:中年女性に多い。
D:RAS(ロキタンスキーアショフ洞)の増生が特徴。
E:EUS-FNACなど細胞診検体や生検などでは上皮内癌を診断できない。 - 87. 答え2
A:肝は転移性腫瘍が原発性の20倍程度多い。
B:これはそのままでコレステロールポリープが多い。
C:IgG4関連疾患であるため陽性の形質細胞がみられる。細胞診での判定は難しい。
D:これはそのままで中年女性の膵尾部に好発する。
E:細胞診で浸潤・非浸潤は鑑別が難しい。 - 88. 答え1
A:90%以上にK-ras変異がみられる。
B:Bcl-10、トリプシンなどが陽性となる。
C:アミロイドはインスリノーマで見られやすい。
D:SPNは若年女性に多い低悪性度腫瘍。
E:腺扁平上皮癌は通常の腺癌よりも予後不良とされる。 - 89. 答え3
悪性所見としては①不規則重積②核間距離の不整③核の極性の乱れ④正常の2倍以上の核腫大⑤各の大小不同⑥N/C比の増大⑦核形不整⑧クロマチン増量⑨クロマチン不均等分布などがある。 - 90. 答え5
A:偏性嫌気性の芽胞形成性のグラム陽性桿菌(細菌)のClostridium difficileが原因。
B:小児から成人まで発症する。
C:上皮の障害によって杯細胞の減少が見られる。
D:グリコーゲンを持つため陽性を示す。
E:クローン病は右側結腸(特に回盲部)に好発する。 - 91. 答え4
1:好塩基性顆粒をもつためギムザ染色で青色に染まる。
2:萎縮粘膜などを引き起こす菌ではあるが、そこに菌は存在しないことが多い。
3:幽門部~十二指腸の粘膜下層や筋層に多い。
4:ギムザでは青色に染まる。グラム陰性らせん状桿菌であるためグラム染色では赤色に染まる。
5:日本を含むアジアに発生頻度が高い腫瘍として知られる。 - 92. 答え1
1:上皮内癌は細胞診で判定できない。
2:胆汁性腹膜炎のリスクが高いため行わない方が良い。
3:嚢胞性病変の方が偶発症リスクが高い。本邦では基本的には嚢胞性病変には行わない。
4:微量腹水も適応となる。
5:膵体尾部病変の術前確定診断や切除不能膵癌が疑われる症例の確定診断に用いることができる。 - 93. 答え3
中分化型では偽腺管構造や胆汁産生などを特徴とする。高分化型と同じように好酸性顆粒状の細胞質も持つ。腫瘍細胞は集塊で出現し、豊富な好酸性顆粒状細胞質、核や核小体の腫大、クロマチン増量なども認める。小型でN/C比が高い場合は高分化型を考え、多形性がある場合は低分化型や未分化型を考える。脂肪滴は高分化型でよくみられる。 - 94. 答え2
1:粘膜筋板と粘膜下層を欠く。
2:胆嚢病変は女性に多い。胆石症も例外ではなく女性に多い。
3:線毛はない。単層円柱上皮で被覆される。
4:胆嚢腺筋症は癌化率が低い。
5:1/3の症例では粘液の過剰産生を伴うとされる。 - 95. 答え5
1:膵頭部に好発する。
2:主膵管型の方が予後が悪い。
3:約10%程度合併が見られる。
4:MUC2は陰性を示す。腸型のみ陽性。
5:浸潤性膵管癌と同様にKRAS変異がみられる。膵管内管状乳頭状腫瘍ではみられない。 - 96. 答え1
1:非機能性が多い。
2:インスリノーマは良性が多く、それ以外は悪性が多い。
3:これはそのままで部分症であることがある。
4:神経内分泌マーカーが陽性を示すためCD56も陽性を示す。
5:形質細胞様の核偏在性を示すことがある。 - 97. 答え5
1:ミトコンドリアが豊富であるため好酸性顆粒状でPAS反応陽性を示す。
2:単核も2核も存在する。
3:正常は中心性円形核をもつ。
4:肝硬変との合併も癌化もみられない。
5:C型肝炎を原因とするものが多く、C型肝炎はRNAウイルスである。 - 98. 答え5
1:これはこのままで最も頻度が高い。
2:粘膜下腫瘍であるためFNAが有効となる。
3:消化管運動のペースメーカーであるCajal介在細胞由来である。
4:悪性度の指標には腫瘍径、核分裂数、Ki-67が用いられる。
5:S-100は神経鞘腫などに染まるマーカー。GISTはKIT、CD34、DOG1などが陽性。 - 99. 答え34
唾液腺筋上皮細胞マーカーとして①S-100②CD10③α-SMA④vimentin⑤calponin⑥p63⑦AE1/AE3などがある。 - 100. 答え12
1:炎症病変なのに硬い腫瘤を形成するのが特徴。
2:異型のないリンパ球やIgG4陽性の形質細胞浸潤が特徴的。
3:ミクリッツ病は有名なIgG4関連唾液腺炎の一つ。
4:IgG4が高値となる。
5:50~60歳代の高齢男性に多い。
- 81. 答え5
- 【婦人科】の解答
-
- 101. 答え4
A:ミュラー管からは卵管、子宮体部、膣上部が形成される。
B:子宮筋層は平滑筋。
C:膣はグリコーゲンを含む非角化型重層扁平上皮で被覆される。
D:増殖期の方が頸管粘液の粘度が低い。牽糸性は高い。
E:体温の上昇はプロゲステロンの作用によって惹起される。 - 102. 答え3
A:酢酸加工後にみられる限局性の異常病変で酢酸加工後にみられる。
B:隆起性、白色の限局性病変で酢酸加工前から見られる。
C:不規則な走行を示す不整血管を含む限局性異常病変で酢酸加工前から見られる。
D:モザイク模様を示す限局性の異常病変で酢酸加工後に見られる。
E:酢酸加工によって出現する円柱上皮所見。 - 103. 答え3
A:下垂体前葉から分泌。
B:卵巣にある顆粒膜細胞から分泌。
C:卵巣にある黄体から分泌。
D:下垂体前葉から分泌。
E:視床下部から分泌。 - 104. 答え3
A:単房性が多い。多房性は粘液性腫瘍に多い。
D:化学療法抵抗性の腫瘍である。
E:悪性より良性の方が多い。 - 105. 答え5
A:絨毛血管内には胎児由来の有核赤血球がみられる。
B:hCGは合胞体性栄養膜細胞から分泌される。
C:部分奇胎は3倍体、全奇胎は有核発生の2倍体。
D:部分奇胎は細胞性栄養膜細胞と間質細胞にp57kip2陽性を示す。全奇胎は陰性。
E:3種類の栄養膜細胞(細胞性、合胞体性、中間型)はどれもサイトケラチン陽性。 - 106. 答え2
A:分泌期が鋸歯状の腺管が見られやすくなる。
B:IUDの装着によって石灰化物質や多核巨細胞、類上皮細胞などを認める。
C:萎縮内膜は核が小型濃縮化することが多い。
D:エクソダスは月経期に見られる内膜と間質細胞の集塊。中央が間質で辺縁が内膜腺細胞。
E:核下空胞は分泌期初期に見られる。 - 107. 答え5
A:卒中性平滑筋腫という型では壊死がみられる。
B:低異型度子宮内膜間質肉腫はらせん動脈様の血管を認める。
C:肉腫で最も多いのは平滑筋肉腫。2番目は低異型度子宮内膜間質肉腫。
D:粘膜下や筋層内に発生した場合は過多月経や月経困難症が認められる。
E:規約5版からは上皮性腫瘍に分類されている(以前は上皮性・間葉性混合腫瘍)。 - 108. 答え1
A:代替マーカーとしてp16が使われる。
B:疣状癌は極めて分化度が高い扁平上皮癌である。
C:咽頭などとは異なりEBVが検出されることはほとんどない。HPVは陽性。
D:HPVに関連する。
E:無症状の良性病変で悪性化はしない。 - 109. 答え4
C:核小体は目立たないか小さいものが1つ程度。
D:核形は類円形で異型は弱い。 - 110. 答え5
A:メラニンを持たない無色素性が存在する。
B:早期に転移を起こしやすい。
C:S-100、NSE、HMB45、Melan Aなどが陽性。
D:予後は悪い。
E:ドーパ反応は色素性でも無色素性でも陽性を示す。 - 111. 答え1
星雲状封入体はクラミジア粒子を含んだヘマトキシリン好性の細胞質内封入体。クラミジア感染で見られる。 - 112. 答え3
1:新生児期は中層細胞主体となる。
2:閉経期は傍基底細胞主体となる。舟状細胞はプロゲステロン高値の時にみられる。
3:産褥期初期は分娩後細胞と呼ばれる傍基底細胞にグリコーゲンを含む細胞を認める。
4:exodusは月経期に見られやすい。
5:分泌期は融解した細胞や白血球が多く汚い背景になる。 - 113. 答え2
1:子宮内膜症は明細胞腫瘍や類内膜腫瘍の発生と関連する。
2:片側性発生が多い。
3:エストロゲン産生腫瘍には顆粒膜細胞腫、莢膜細胞腫、ブレンナー腫瘍などがある。
4:成人型はFOXL2が90%以上の症例で認められる。
5:アンドロゲンやエストロゲン産生がみられる。 - 114. 答え3
1:ライトグリーン濃染性で敷石状配列を示す。
2:濾胞性頸管炎はTingible macrophageやリンパ球がみられる。コイロサイトーシスはHPV関連疾患でみられる。
3:炎症性背景に傍基底細胞を主体の細胞がみられる。小型角化細胞やライトグリーンやヘマトキシリン好性の変性物質などもみられる。
4:敷石状配列は化生細胞で見られる。
5:キャノンボールは好中球が球状集塊になったものでトリコモナス感染でみられやすい。 - 115. 答え4
1:単純子宮全摘術が推奨される。
2:同時化学放射線療法が推奨される。
3:単純子宮全摘術+両側付属器摘出術+大網切除術が推奨される。
4:子宮全摘術+両側付属器摘出術が推奨される。
5:外科手術が第一選択となる。 - 116. 答え1
1:性成熟期に好発する。
2:不妊症の原因となることが多い。
3:初期病変は点状や赤色病変だが、時間経過とともに青色~褐色調のブルーベリースポットが見られる。
4:肺、横隔膜、胸膜などに発生すると気胸を起こすことがある。
5:子宮筋層に発生するものは子宮腺筋症として区別される。 - 117. 答え5
1:hobnail構造、基底膜物質を囲む構造、ミラーボール状構造などが見られる。
2:異型の強い腫瘍細胞が結合性の弱い小集塊から孤立散在性に出現する。
3:紡錘形で葉巻状核をもつ異型の強い腫瘍細胞が孤立散在性に出現する。
4:有端腺管の増生、拡張腺管、腺管増生などがみられる。
5:白血球取り込み像は類内膜癌で見られやすい。 - 118. 答え5
Merkel細胞癌はCK20が細胞質内で点状の陽性を示す。 - 119. 答え24
1:卵黄嚢腫瘍はAFPが陽性となる。
3:明細胞癌はHNF1-βやNapsin Aなどが陽性となる。
5:漿液性癌はCA125、WT1、p53などが陽性となる。 - 120. 答え23
2:N/C比は80%以上。
3:核小体は目立たないことが多い。
- 101. 答え4
細胞診模擬試験 ~難易度6~の解説
71.8%(86.1問正解/120問中)
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度6】かなり本番に近い難易度です。
この中の問題から実際の試験に出たものもあります
多く解けば本番類似の問題が出る可能性は上がります。
毎月模試を解いて合格を必ず手に入れましょう!
試験まで一緒に頑張っていきましょう!
- 【総論】の解答
-
- 1. 答え2(AE)
A:DNAを含む
B:RNAを含む
C:RNAを含む
D:RNAを含む
E:DNAを含む - 2. 答え3(BC)
A:微小管>中間径フィラメント>アクチンの順に細くなる。
B:核膜を裏打ちする核の中間系フィラメントで神経系に特異的ではない。
C:中心体に付着する細胞骨格は微小管。
D:微小管をレールのようにして細胞小器官は移動できる。
E:細胞分裂の最後にはアクチンが収縮環を形成し細胞を2つに分ける。 - 3. 答え5(DE)
A:単層扁平上皮(中皮)
B:非角化型重層扁平上皮
C:単層円柱上皮 - 4. 答え2(AE)
A:上皮では特に小腸や毛嚢で盛んに行われている。
B:ヌクレオソーム単位、つまり約180bpでの切断が生じる。
C:細胞膜は保たれる。そのため周囲組織に炎症が起こらない。
D:ミトコンドリアは膨張する。細胞小器官は基本携帯的変化を伴わない。
E:ATPを必要とする。 - 5. 答え3(BC)
A:寄生虫感染では好酸球の増加が認められることが多い。
B:嚢胞には組織球が多数見られる。
C:これはそのまま。嚢胞を含む乳腺の良性病変・疾患にはアポクリン化生細胞を認めることがある。
D:結核と類似の像を示すたラングハンス巨細胞、類上皮細胞、壊死などをみることがある。
E:類骨はみられる。類骨を認めないと骨肉腫の診断は難しい。 - 6. 答え4(CD)
砂粒体が見られやすいのは①漿液性癌②甲状腺乳頭癌③粘液癌④髄膜腫などである。 - 7. 答え1(AB)
C:顆粒膜細胞腫で見られる。
D:形質細胞腫や多発性骨髄腫の細胞核に見られる。
E:神経鞘腫で見られる。 - 8. 答え1(AB)
C:乳がん、卵巣がん、膵がん、前立腺がんなどと関連する。
D:腎芽腫などと関連する。
E:大腸癌と関連する。 - 9. 答え4(CD)
C:前立腺癌は辺縁領域に発生しやすいため早期の場合症状が出にくい。逆に前立腺肥大は移行域や中心域に発生しやすいため排尿障害が起きやすい。
D:褐色細胞腫はカテコールアミン産生腫瘍であるため高血圧となる。
E:肺尖部腫瘍は神経障害を示すことがある。それをパンコースト症候群を呼ぶ。 - 10. 答え5(DE)
A:マロリー小体はケラチンなどのタンパクが変性した蛋白質変性である。細かく分けると硝子変性や好酸性変性などに分類される。
B:印環細胞癌は粘液変性である。
C:類線維素性炎は膠原病などで見られる。 - 11. 答え3
3:円形ではなく紡錘形の細胞が主体の腫瘍。 - 12. 答え2
2:ミトコンドリアの膜電位を保つことでアポトーシスを抑制する遺伝子。アポトーシスが起きない、つまり癌細胞が死なない=癌遺伝子。 - 13. 答え1
2:外膜で覆われる。
3:胃からの酸性液を中和するためアルカリ性の粘液を分泌する。
4:パネート細胞は小腸の陰窩に見られる。
5:十二指腸に接する側は膵頭部。 - 14. 答え1
1:甲状腺髄様癌はC細胞由来でCEAに陽性を示す。他、カルシトニンも陽性。
2:GIStはカハール介在細胞由来でDOG1, KIT, CD34が陽性を示す。
3:顆粒細胞腫は神経鞘腫由来の腫瘍でS-100に陽性を示す。
4:前立腺癌は腺房細胞由来でPSAやγ-Smなどが血中マーカーとして使われる。
5:淡明型腎細胞癌は近位尿細管由来でCD10, EMA, vimentin, cytokeratinなどが陽性となる。 - 15. 答え2
- 16. 答え5
1:塩基置換によってコードされるアミノ酸が変化する変異のこと。
2:エクソンーイントロンのジャンクションに生じる変異のこと。
3:3塩基の読み枠が変化する変異のこと。
4:塩基置換は起こるがコードされるアミノ酸には変化のない変異のこと。 - 17. 答え5
- 18. 答え2
胃癌は肝臓に転移しやすい。 - 19. 答え34
1:中胚葉
2:内胚葉
5:中胚葉 - 20. 答え34
- 1. 答え2(AE)
- 【技術】の解答
-
- 21. 2(AE)
A:ケーラー照明法を行う際に視野絞りを絞ったり開いたりする必要がある。
B:位相差顕微鏡は無染色でも観察可能であるため染色は必ずしも必要ではない。
C:位相差顕微鏡より微分干渉顕微鏡の方が厚い標本に適している。
D:痛風の原因である尿酸ナトリウム結晶は偏光顕微鏡で観察しやすい。
E:暗視野観察はコントラストが高い像を得ることができる。 - 22. 3(BC)
A:結晶クエン酸はマイヤーに用いられる試薬。細胞診ではギルが使われるため結晶クエン酸は用いない。
B:下降アルコール系列は細胞が剥離しやすい。
C:赤血球は赤色や緑色に染まる。
D:水やエタノールの残存は退色を促進させる。
E:細胞質に透明感をもつことを特徴とする。 - 23. 4(CD)
A:細胞が剥離しやすい体腔液や脳脊髄液では剥離しにくいギムザが有効となる。
B:ショール染色は迅速Papanicolaou染色のこと。
C:pHが高いと青みが強くなる。
D:酸性色素のエオジンが含まれる。
E:塩基性色素であるメチレン青などは陽性に荷電している。 - 24. 1(AB)
A:複数切片の作製が可能となる。
B:アルギン酸が粘液多糖類であるため、背景に粘液物質が出現し、アルシアン青で陽性となる。
C:組織と類似の構造や配列が確認できる。
D:ホルマリンで固定する。
E:ホルマリン固定が必要である。 - 25. 5(DE)
A:サポニンは細胞変性が強いためあまり適さない。
B:ポアフィルター法はフィルターに細胞を捕捉でき、集めることができるため集細胞法に含まれる。
C:1000 rpm程度が良い。 - 26. 4(CD)
A:細胞膜
B:細胞膜
E:核 or 細胞質 - 27. 2(AE)
A:平面的に塗抹されためLBCは有効な検体となる。
B:FISHの標的は核酸であるため核に蛍光発色の陽性所見を認める。
C:重積が強い部分は蛍光が重なり判定できない。
D:セントロメアをポジコンとして染めることがある。
E:固定はエタノールでもホルマリンでも可能。 - 28. 5(DE)
A:3類
B:3類
C:3類 - 29. 1(AB)
C:アルシアン青はブルンネル腺は陰性となる。
D:PAS反応は基底膜様物質を染めるが、赤紫色になる。
E:グロコット染色の真菌は黒色に染まる。背景が緑色に染まる。 - 30. 2(AE)
A:異なる性状の3か所から採取する。
E:フィブリンがある場合はピペットなどで潰して細胞成分を液中に出してから遠心する。フィブリン塊はセルブロックにもできる。 - 31. 4
塩基性フクシンが用いられる。 - 32. 1
1:封入剤を硬化させた後に軟化させる。 - 33. 5
胃などを経由して病変を穿刺することがあり、その場合は胃の正常細胞などのコンタミが生じる。 - 34. 2
1:機械などの装置を使って行うため人為的な差が出にくい。
3:ブラシに付着した細胞も液中に溶かすことができるため細胞回収率が高い。
4:塗抹範囲は限定される。
5:収縮傾向を示す。 - 35. 3
1:脱水固定を原理とする。
2:使える。乾燥後、エタノールで固定すると良い。
4:アミノ基を架橋する。
5:保湿成分を含むため乾燥させて良い。 - 36. 3
- 37. 4
- 38. 1
2:媒染剤
3:pH調整剤
4:酸化防止剤
5:媒染剤 - 39. 23
1:直接法は間接法より特異度が高く感度が低い。
4:一次抗体反応前に行う。
5:DABは茶色、AECは赤色に発色する。 - 40. 14
2:反比例する。
3:下げるとコントラストが上がり、上げると下がる。
5:5500Kが適している。
- 21. 2(AE)
- 【その他】の解答
-
- 41. 3(BC)
A:pH6程度の弱酸性
D:良性の腎疾患などでも出現することがあり悪性と断定はできない。
E:尿細管上皮ではなく消化管粘膜上皮。 - 42. 2(AE)
B:細胞質辺縁が陽性となる。
C:多核細胞などが増えると難しいことが多い。容易ではない。
D:平面的なものが多いが、乳頭状の変化を示すこともある。 - 43. 2(AE)
B:いくつか混在することがある。
C:浸潤と非浸潤を細胞診で鑑別することは容易ではない。
D:この所見は低乳頭型。 - 44. 3(BC)
B:良性腫瘍。
C:単クローン性腫瘍。 - 45. 1(AB)
C:血管が豊富で細胞診の背景は血性になりやすい。
D:乳頭癌に多いが、その他の良性疾患で見られることもある。
E:乳頭癌が最も多い。 - 46. 5(DE)
A:I~Ⅳで分類する。
B:grade Ⅲに分類される。
C:ローゼンタール線維は毛様細胞性星細胞腫で見られる。 - 47. 5(DE)
A:併存することが多いが、判定は小細胞癌が優先される。
B:剥離しやすい。そのため細胞診が有効となる。
C:グリコーゲンを有するため陽性となる。 - 48. 2(AE)
A:褐色細胞腫はカテコールアミンを産生し、その代謝産物であるバニリルマンデル酸が尿中に検出される。
B:髄質に発生しやすい。
C:chromograninn A, synaptophysin, NSEが陽性となることが多い。
D:遠位尿細管由来。
E:脂肪を含むため黄色調を呈する。 - 49. 4(CD)
A:胚細胞腫瘍で陽性となるマーカー。
B:中皮腫に陽性となるマーカー。
E:肝細胞癌は両方とも陰性。 - 50. 1(AB)
A:リンパ管侵襲が高頻度に見られる悪性度の高い腫瘍。
B:高分化で予後良好な腫瘍。 - 51. 4
4:線維肉腫は魚骨様形態(herring bone pattern)を示す。 - 52. 5
髄様癌は小濾胞構造や乳頭状構造など特徴的な集塊はみとめられない。紡錘形、類円形、多辺形などを示し結合性は緩い。 - 53. 1
2:血管をよく認めるのは粘液型。
3:核に切れ込みを持つ細胞を特徴とする。
4:類円形核で細胞質が広いか、裸核状の類円形核が数珠状に配列する。
5:短紡錘形細胞が上皮様集塊を形成する部分と孤立散在性に出現する部分の二相性が特徴的(型による)。 - 54. 2
1:核破砕物貪食組織球がみられる。
3:CD8陽性T細胞が多い。
4:非乾酪性類上皮肉芽腫に分類される。
5:背景に好中球やリンパ球、組織球が多数みられる。 - 55. 3
3:裸核状で核小体が目立つ。 - 56. 1
尿路上皮癌の所見として核偏在性というものがある。細胞膜に接するくらいもしくは飛び出すくらいの核偏在性は悪性を考える。 - 57. 4
1:grade Ⅲ
2:grade Ⅳ
3:grade Ⅰ
5:grade Ⅰ - 58. 2
1:長管骨骨幹
3:長管骨骨幹端~骨端
4:指節骨・中手骨
5:長管骨骨幹端 - 59. 14
- 60. 14
2:クロシドライトの危険度が最も高い。
3:両方とも陽性。
5:使える。反応性に陽性となる。
- 41. 3(BC)
- 【呼吸器】の解答
-
- 61. 3(BC)
A:重層扁平上皮
D:重層扁平上皮
E:重層扁平上皮 - 62. 1(AB)
C~Dは腺癌。 - 63. 3(BC)
A:高度異型扁平上皮細胞の所見。
D:高度異型扁平上皮細胞、扁平上皮癌細胞の所見。
E:軽度はほとんどオレンジG好性を示す。 - 64. 5(DE)
A:真性菌糸を持つ。仮性菌糸をもつのはカンジダ。
B:細菌感染症ではなく、真菌感染症で最も多い。
C:陽性を示す。 - 65. 1(AB)
A:隔壁は持たない。
B:血管侵襲性が強い。 - 66. 5(DE)
生検および細胞診検体で使えない診断名は6つ。①上皮内腺癌②微小浸潤腺癌③大細胞癌④扁平上皮癌⑤肉腫様癌⑥非扁平上皮癌 - 67. 4(CD)
A:内分泌細胞で小細胞癌の発生墓地となる細胞である。
B:全気道に存在し、微絨毛を持つ。
C:硝子軟骨。
D:線毛ではなく微絨毛を持つ。 - 68. 1(AB)
C:低異型度はモルラの形成を認めるが、高異型度は認めない。
D:CDX2やCK20など大腸癌に染まるものをが陽性となる症例もある。
E:印環細胞型や淡明細胞型は含まれず、診断名の最後にその存在を記載する。 - 69. 4(CD)
C:細胞間橋は角化型の特徴である。
D:類基底細胞型でも陽性となる。 - 70. 2(AE)
A:核の極性は保たれている。
E:1ないし数個の核小体を有する。 - 71. 3
10~20%程度は陰性となる。 - 72. 1
2:3cm以下の限局性病変。
3:STASは浸潤の定義に含まれるため、AISではみられない。
4:TTF-1、napsin Aともに陽性を示す。
5:非粘液産生性腫瘍細胞が多い。 - 73. 5
最も多いドライバー遺伝子の変異はEGFRである。 - 74. 2
肺動脈は細気管支、肺静脈は小葉間結合組織を走行するため伴走しない。
呼吸器解剖のイラスト解説はこちら - 75. 3
完全に分化した線毛円柱上皮細胞から発生するのではなく、線毛円柱上皮に分化する予定の基底細胞が扁平上皮細胞へ分化したもの。 - 76. 4
1:肺門部のがんの早期発見を目的に行われる。
2:1日の平均喫煙本数×喫煙年数で算出される。
3:B判定は癌を疑う所見は無い区分の一つ。
5:早期癌であることが多い。 - 77. 4
1:黄褐色
2:緑(ライトグリーン)
3:褐色~褐緑色
5:橙色~緑色(オレンジG~ライトグリーン) - 78. 3
3:どんなものが転移してもよい。肉腫の転移もありうる。 - 79. 23
1:中悪性
4:中悪性
5:低悪性 - 80. 25
1:集塊も孤立性細胞も認められる。
3:核小体は1~数個目立つものが多い。
4:ロゼット構造を認めることもある。
- 61. 3(BC)
- 【消化器】の解答
-
- 81. 5(DE)
D:採取される細胞への影響はない。
E:なるべく広範囲を擦過する。 - 82. 2(AE)
B:NILMに分類される。
C:健常人の20~40%に検出される。
D:深層型扁平上皮細胞集塊が採取される。多数の無核細胞出現は白板症でみられる。 - 83. 3(BC)
A:アンドロゲン受容体が陽性を示すのは唾液腺導管癌。
D:チモーゲン顆粒はもたない。
E:PASもアルシアン青も陽性を示す。 - 84. 5(DE)
- 85. 3(BC)
A:この説明は重複癌の説明である。食道多発癌は食道に原発性の2個以上発生したもののこと。
D:食道下部や中部から発見されることが多い。
E:ジアスターゼ抵抗性PAS陽性の好酸性顆粒状細胞質を持つ。 - 86. 5(DE)
A:通常の消化管層構造と同じく、粘膜下層も存在する。ただし、筋層は他と違い3層構造。
B:幽門前庭部小彎側が好発部位。
C:チモーゲン顆粒は主細胞がもつ。 - 87. 2(AE)
A:B細胞性のDLBCLやMALTリンパ腫が多い。
E:胃の悪性腫瘍の90%は腺癌。 - 88. 3(BC)
A:腫瘤を形成するため膵癌との鑑別が必要になることがある。
D:膵管との交通がある。
E:肺癌が最も多い。 - 89. 5(DE)
D:IPMNは粘液の型によって陽性抗体に差があるが、AFPは膵芽腫であるため関係ない。
E:膵管内管状乳頭腫瘍はMUC1に陽性を示す。 - 90. 4(CD)
A:本疾患は高率に膵胆管合流異常症を合併する。
B:女児に多い。
E:癌化の頻度が低く、ロキタンスキーアショフ洞の増生がみられる。 - 91. 4
1:10~20代の若年者に多い。
2:赤痢アメーバやジアルジアなどは届け出が必要。
3:線維素性炎や偽膜性炎を引き起こす。
5:左側結腸の特に直腸に多い。 - 92. 1
2:若年女性に多い腫瘍ではあるが高齢者や男性にも発生する。
3:間質は毛細血管に富む。
4:石灰化を伴うことが多い。骨化を見ることもある。
5:細胞の結合性は弱い。 - 93. 2
2:管内胆管癌は通常胆汁産生を伴わない。 - 94. 5
1:B型とC型は関与する。C型の方が多い。
2:細胞が小型でN/C比が高い所見が特徴。
3:中分化型では胆汁産生をみることがある。
4:pale bodyやマロリー小体は細胞質内の封入体である。 - 95. 3
1:小児に多い。
2:高齢者に多い。
4:高齢者に多い。
5:高齢者に多い。 - 96. 2
1:これステロールポリープが最も多い。
3:細胞内ではなく、細胞外の粘液が50%以上の領域で見られる。
4:1/2ではなく、1/4以上占める必要がある。
5:円柱上皮で被覆されるため腺癌の発生が多い。 - 97. 5
肝硬変になるとエストロゲン過剰を引き起こすため睾丸は萎縮する。 - 98. 3
核小体は再生性変化や炎症でもみられるため悪性所見とはされていない。 - 99. 45
4:ターコット症候群は大腸ポリープに中枢神経腫瘍を合併するもの。
5:限局性結節性過形成は肝硬変の合併や癌化はみられない。 - 100. 25
2:乳がんのマーカー。
5:大腸ポリープや癌に関連する遺伝子。
- 81. 5(DE)
- 【婦人科】の解答
-
- 101. 1(AB)
C:水溶性や粘液性帯下がみられる。
D:治療抵抗性で予後不良。
E:多くはp16陰性、p53陽性である。 - 102. 3(BC)
A:出血が強い場合、アルギン酸ナトリウムなどの止血剤を用いることがある。
D:3%の酢酸加工を行う。
E:粘液が付着する場合は除去する。 - 103. 2(AE)
B:重層扁平上皮
C:単層線毛円柱上皮
D:単層円柱上皮 - 104. 3(BC)
A:Call-exner bodyは顆粒膜細胞腫でみられる。
D:Coffee beans nuclei(コーヒー豆様核)は顆粒膜細胞腫やブレンナー腫瘍でみられやすい。
E:Psammoma body(石灰化小体)は漿液性癌でみられやすい。 - 105. 5(DE)
1:CIN3には高度異形成と上皮内癌が含まれる。
2:CIN1のほとんどは消退し、HSILに進行しない。
3:ハイリスクHPV代替マーカーはp16INK4a。 - 106. 4(CD)
A:頻度は低いが、扁平上皮癌も発生する。
B:80%以上が類内膜癌である。
E:多くはエストロゲン依存性。そのため危険因子の多くもエストロゲンに長期暴露するものである。 - 107. 5(DE)
A:核分裂像やアポトーシスもみられる。
B:30~40代に好発する。
C:ERは陰性を示す。 - 108. 1(AB)
A:LBC法は5000個以上、直接塗抹は8000~12000個が適正とされる。
B:ASC-USは全報告の5%以下、ASC-Hは全ASCの10%以下が望ましい。 - 109. 3(BC)
A:60~70代に好発する。
D:60代に好発する。
E:両方ともメラニンを有し、異型も強いため鑑別が難しい。 - 110. 2(AE)
A:DNAウイルス。
E:E6はp53の分解、E7はRbの不活化に関与する。 - 111. 4
1:肥満との関連性は低い。
2:高悪性度腫瘍。
3:エストロゲン非依存性腫瘍の一つ。
5:SEICは漿液性癌の前駆病変。上皮内癌だが、卵管経由で播種することがある。 - 112. 5
1:硫黄顆粒はaciinomyces放線菌 - 113. 2
1:同時化学放射線療法
3:化学療法
4:卵巣癌に準じたタキサン製剤とプラチナ製剤による化学療法と最大限の腫瘍減量術(外科手術)
5:両側付属器摘出術+子宮全摘出術+大網切除術 - 114. 3
1:卵胞期は黄体期より体温が低い。
2:LHサージの検出は妊娠ではなく排卵が分かる。
4:エストロゲンをプロゲステロンの合剤であるため含まれる。
5:デーデルライン桿菌は黄体期に増える。 - 115. 1
- 116. 4
1:水腫様流産は栄養膜細胞の増殖がみられない。
2:アジアに多い。
3:部分奇胎は2精子受精の3倍体が多い。雄核発生は全奇胎。
5:妊娠性が多い。 - 117. 4
- 118. 1
2:扁平上皮癌が最も多い。
3:子宮頸部に及ぶ場合は子宮頸癌となる。
4:同じ組織型であればどこでも基本的には同じである。
5:悪性黒色腫は大体予後不良。 - 119. 14
2:HIK1083は陽性。
3:癌ではないため異型が弱い。
5:胃型の形質を持つ。 - 120. 45
4:エストロゲン依存性であるため妊娠で症状が軽快する。
5:癌化の頻度は低い。
- 101. 1(AB)
細胞診模擬試験 ~難易度7~の解説
集計中…
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度7】かなり本番に近い難易度です。
この中から本番類似の問題が出るかもしれません。
多く解けば本番類似の問題が出る可能性は確実に上がります。
毎月模試を解いて合格を必ず手に入れましょう!
試験まで一緒に頑張っていきましょう!
- 【総論】の解答
-
- 1. 3(BC)
A:肥大に含まれる。
B:腺上皮化生である。
D:蛋白変性に含まれる。
E:過形成に含まれる。
化生や変性の詳しい解説記事はこちら - 2. 1(AB)
A:CDK4/6と複合体を形成し、Rbをリン酸化することで細胞周期をG1期からS期へ進行させるタンパクの遺伝子。
B:細胞周期のを進行させるE2Fを抑制するため癌抑制遺伝子。
C:主なミスマッチ修復遺伝子はMSH2, MLH1, MSH6, PMS1, PMS2など。リンチ症候群などに関与する。
D:主な血管新生関連遺伝子にはVEGF、HGF、FGF-2、EGFなどがある。
E:主な細胞接着関連遺伝子にはcadherinやNCAMなどが存在する。 - 3. 2(AE)
貪食とは細胞が異物などを取り込み消化することである。この能力があるのは①好中球②単球③マクロファージ④樹状細胞が存在する。また、③④(あとB細胞)には抗原提示能がある。 - 4. 4(CD)
A:細胞質 or 細胞膜
B:細胞質
E:細胞膜 - 5. 4(CD)
二相性とは特徴的な2種類の細胞が出現している場合を示す言葉。例えば乳腺線維腺腫の筋上皮と乳管上皮、ワルチン腫瘍の好酸性上皮細胞とリンパ球、胞状奇胎のラングハンス型、シンチジウム型トロホブラストなどの出現は二相性を示すと表現される。 - 6. 4(CD)
A:B型とC型肝炎ウイルス、アルコ―ル、喫煙、肥満、脂肪肝、糖尿病などがリスク因子となる。
B:肥満、エストロゲン産生腫瘍、多嚢胞性卵巣症候群、糖尿病、リンチ症候群などがリスク因子となる。
C:アミン、アニリン、ベンチジンの暴露、喫煙、ビルハルツ住血吸虫、尿膜管遺残などがリスク因子となる。
D:肥満、エストロゲン産生腫瘍、多嚢胞性卵巣症候群、BRCA1/2遺伝子異常などがリスク因子となる。
E:喫煙、慢性閉塞性肺疾患、アスベスト、結核、EGFRやALKなどドライバー遺伝子異常などがリスク因子となる。 - 7. 5(DE)
A:卵巣明細胞癌で見られる、基底膜様物質を腫瘍細胞が取り囲んだ構造。ギムザで異染性を示すためこのように呼ばれる。
B:卵黄嚢腫瘍の組織でみられる、血管の周囲に腫瘍細胞が配列し、その周りには空隙があり、さらにその周りに扁平な腫瘍細胞が囲む構造。細胞診検体にみられることはほぼない。
C:形質細胞腫/多発性骨髄腫でみられる細胞質内の小体。細胞内に異常なタンパク質が蓄積されて形成される小体である。
D:観観平配列とも呼ばれ、柵状に並んだ細胞が向き合った状態で配列する細胞配列・組織配列パターンの一つ。神経鞘腫でみられる。
E:硝子化索状腫瘍の細胞質に見られることがある封入体。 - 8. 2(AE)
小型円形腫瘍細胞とはその名の通り腫瘍細胞が小型で円形を示す腫瘍である。種類としては小細胞癌、Ewing肉腫、神経芽腫、横紋筋肉腫、滑膜肉腫、悪性リンパ腫、悪性黒色腫などが該当する。 - 9. 1(AB)
C:外胚葉
D:内胚葉
E:内胚葉 - 10. 5(DE)
- 11. 4
転写とはDNAの情報をmRNAに写し取る作業のことで核内で行われる。その他の選択肢は全て細胞質(または細胞質に存在する細胞小器官)で行われる。 - 12. 1
2:核内細胞質封入体を認めることがある。
3:核内細胞質封入体を認めることがある。
4:好酸性 or 好塩基性の核内封入体を認めることがある。
5:ダッチャー小体と呼ばれる核内封入体を認めることがある。 - 13. 2
テストステロンは精巣のライディッヒ細胞から分泌される。 - 14. 3
1:尿路上皮
2:単層立方上皮
4:単層円柱上皮
5:単層扁平上皮 - 15. 5
1:膀胱三角部、側壁、後壁などが好発部位とされる。
2:壁側胸膜から発生するものが多い。
3:中部に好発する。
4:S状結腸や直腸に好発する。 - 16. 1
2:多段階発癌は大腸がんに代表され、正常組織から前癌病変を経て癌が発生する発癌形式。一方、正常組織から癌が発生するものは de novo発癌と呼ばれる。
3:ヒストンに対するエピジェネティクスな修飾としてアセチル化やメチル化が存在する。アセチル化が起きると遺伝子発現が促進される。メチル化では転写抑制、促進どちらにも関与する。治療の標的としても用いられる。
4:悪性度が高くなると、上皮間葉転換が促進されるため一般的に細胞接着性は低くなる。
5:放射線感受性は腺癌より扁平上皮癌の方が高い。 - 17. 4
- 18. 2
2:通常の多くの細胞はG0期で存在する。 - 19. 13
消化器癌は比較的頻度が低いと言われる。代表的なのは前立腺癌、乳癌、肺癌、腎癌である。 - 20. 45
- 1. 3(BC)
- 【技術】の解答
-
- 21.3(BC)
A:CISH法はDABなどのchromogenを用いたISH法である。対象こそ違えど、発色原理はDABなどを用いた免疫染色と同じであるため、通常HEを観察する際の明視野顕微鏡を用いる。
B:倒立型はステージ下に、正立型はステージ上に対物レンズがある。
C:位相差顕微鏡や微分干渉顕微鏡は生細胞や無染色標本の観察に有用である。
D:暗視野観察は暗い背景に明るい画像を形成することができるため高いコントラストを得ることができる。
E:共焦点レーザー顕微鏡はZ軸の撮影も可能であるため、撮影後に立体を構築できる。 - 22.2(AE)
A:酸性色素のエオジンと塩基性色素のメチレン青、アズールを含む。
B:染め過ぎの場合は水かリン酸緩衝液で脱色するのが良い。
C:RNAが多いと青っぽくなる。
D:Shorr染色は迅速Papancolaou染色
E:透過性が悪い染色であるため、塗抹が厚いとみれない。 - 23.5(DE)
A:イオン結合を主とした染色原理である。ヘマトキシリン-金属レーキが正に荷電し、負に荷電するリン酸基などを多く持つ、核や軟骨基質などと結合する。
B:塩基性色素である。
C:pHが下がると選択性が上がる。マイヤーなどの進行性ヘマトはpH調整剤でpHを下げることで核への選択性を上げている。
D:酸化後に金属とレーキを形成することによって染色性を持つため、色素を溶解するだけでは染色性が無い。
E:生体成分との結合性が強いため、水やアルコールに浸しても容易には離れない。 - 24.3(BC)
A:偶発症には出血、播種、膵炎、膿瘍形成、消化管穿孔などがある。
B:縦隔病変には食道経由で穿刺できる。
C:十分な組織片がある場合は圧座で標本をつくる。
D:出血傾向が強い場合は禁忌となる。
E:組織的には花むしろ状構造や形質細胞浸潤などいくつか特徴的所見があるが、細胞診で判断することはできない。 - 25.1(AB)
C:粘度の高い検体にはすり合わせ法が適する。
D:遠心は通常、3000rpm程度で行う。脳脊髄液は1000rpm。
E:穿刺吸引は陰圧にした後、陰圧解除してから針を抜く。 - 26.3(BC)
A:OG液やライトグリーン液の分別は95%エタノールで行う。
B:乾燥が厳禁であるため有効でない。ただ、乾燥後に固定せず2日以内であれば再水和法によって回復が可能である。
C:これはそのまま。
D:pHが下がるとオレンジGの染色は弱くなる。
E:一般的にギルやハリスはヘマトキシリン濃度が高く、マイヤーやカラッチよりも染色力が強い。 - 27.1(AB)
B:サイトメガロウイルスは核や細胞質に封入体を持ち、PASやGrocottに陽性を示す。
C:ノカルジアやアクチノマイセスはPASやGridleyの染色性が弱い。
D:ムーコルは真菌であるためGrocott染色に陽性を示す。
E:クリプトコッカスは墨汁をはじくため、背景が黒く、菌は白く抜ける。 - 28.5(DE)
A:キシレンの管理濃度は50ppm
B:作業環境測定は3つの管理区分で評価される。
C:ホルマリンの記録保存は30年間。他はほとんど3年間。 - 29.1(AB)
A:どちらでも使用できる。乾燥した場合は乾燥後95%エタノールで固定すると良い。
B:塗抹が厚い場合、偽陽性や陽性所見の不明瞭化などが起きることがある。
C:冬場は酸化を長くする方が良い。
D:過ヨウ素酸で酸化する。
E:核染色は通常ヘマトキシリンを使用する。 - 30.4(CD)
A:実視野は接眼レンズの視野数と対物レンズの倍率で決定する。
B:開口数が大きいと分解能が上がる。
E:色温度変換フィルターは色温度を変換するためのフィルターで、明るさを調節するのはNDフィルター。 - 31.4
水洗による色出しでは水温の影響を受ける。水温が低い場合は長い時間を要する。 - 32.2
1:アルシアン青は構造の中心に銅イオンを持つ色素である。
2:ムチカルミン染色の核染色はムチカルミンよりも先に行う。核染色を後に行うと陽性部分が減弱することがある。
3:アメーバはグリコーゲンをもつため、グリコーゲンを染めるPAS反応が有効となる。
4:可能である。
5:これはそのまま。 - 33.3
収差、つまり像のずれには単色収差と色収差がある。前者には5種類が含まれており、ザイデルの5収差と呼ばれる。 - 34.5
1:使用できる。しかし、抗原が減弱することや失活することがあるので注意。
2:色がついていないDABなどを酵素と反応させる発色操作が必要。蛍光抗体法はこの操作を必要としない。
3:蛍光が時間とともに減弱するため永久標本にできない。
4:DABは水溶性。
5:細胞診検体は立体的で重積が強いため共染や偽陰性化が起きやすい。 - 35.1
2:約5~10μm程度の穴があいている。
3:変性が強い。が、溶血時間は短く済む。塩化アンモニウムを用いた場合は変性が弱いが、時間が長い。
4:赤血球層と上清の間に存在する。
5:遠心力によって塗抹するため粘度が高いと塗抹しづらい。 - 36.4
レバミゾールはアルカリホスファターゼ活性を阻害する。 - 37.2
1:シッフ試薬はアルデヒドと反応するためホルマリンを滴下すると赤紫色になる。変化がない場合は染色能力が無いため交換する必要がある。
3:酸性粘液多糖類を染める。
4:青色に染まる。
5:硝酸銀を用いる。 - 38.4
4:核に染まる。 - 39.15
1:生理食塩水を使う工程はほぼない。
5:バックグラウンドなどの非特異的反応の阻害に用いられる。 - 40.13
2:1本鎖DNAである。
4:DAPIは核全体を染めるため目的配列の染色には用いない。
5:間期核にも使用できるのが利点の一つである。
- 21.3(BC)
- 【その他】の解答
-
- 41.3(BC)
A:再発もある。
E:核分裂像が見られるのは稀である。 - 42.3(BC)
A:面疱型はコメド型とも呼ばれ、癌中心部に凝固壊死を持ち、石灰化を伴うこともある。
B:多くはホルモン受容体陽性、HER2陰性である。
C:ホルモン受容体もHER2も陰性となる。 - 43.2(AE)
本変異を認める腫瘍として、星細胞腫(旧びまん性星細胞腫、退形成性星細胞腫、膠芽腫)、乏突起膠腫が存在する。 - 44.3(BC)
A:Papanicolaou分類は用いず、陽性、偽陽性、陽性の3区分を用いる。
C:小型の場合は反応性中皮の可能性があるため、中皮腫とはできない。
D:肉腫型中皮腫の細胞は体腔液中に出現しにくい。そもそも体腔液の貯留も少ない。
E:ヒアルロン酸であるため消失する。 - 45.1(AB)
C:小脳テント上、傍矢状洞、小脳橋角部、脊髄等に好発する。
D:大脳半球に好発する。
E:前頭葉や側頭葉に好発する。 - 46.5(DE)
D:異常リンパ球ではなく異型リンパ球が増加する。
E:メラニン沈着を認めることもある。 - 47.2(AE)
B:この転座は硝子化索状腫瘍で見られる。濾胞癌ではPAX8/PPARG 遺伝子再構成やRASの変異がみられる。
C:予後は極めて良い。
D:放射線被ばくと関連がある。他に、ヨード不足やCoeden病、Werner症候群などの遺伝性疾患が関連する。 - 48.5(DE)
A:高分化型が最も多い。
B:他の型に比べると低い年齢に発生しやすい。
C:herring bone patternは線維肉腫に見られる。 - 49.1(AB)
C:顆粒状に陽性を示す。
D:好塩基性を示す。
E:それらの細胞が体腔液に出現することは稀である。 - 50.5(DE)
A:ヘモジデリン沈着は骨巨細胞腫などでみられる。
B:ロゼット構造はEwing肉腫などでみられる。
C:類骨は骨肉腫でみられる。軟骨肉腫は類骨を形成しない。 - 51.3
3:粘液ではなく、グリコーゲン。
4:アルシアン青もPASも染まる。 - 52.5
1:二相型や上皮型では上皮様細胞が体腔液中に出現する。肉腫型は細胞が出にくい。
2:早期では出現しにくいとされる。
3:核は類円形。
4:ジアスターゼ処理ではPAS反応の陽性像が陰性化する。 - 53.4
4:良性では乳腺症や乳管内乳頭腫、悪性では非浸潤性乳管癌、浸潤性乳管癌、粘液癌などでみられる。 - 54.2
2:大型で異型の強い腫瘍細胞がみられる。 - 55.4
4:偽柵状壊死は膠芽腫の所見。乏突起膠腫は淡明な細胞質や鶏小屋の金網像などが特徴。 - 56.4
1:アミロイド甲状腺腫など他にもアミロイド沈着する疾患もあるため断定はできない。
2:腎癌、肺癌、乳癌が多い。
3:女性に多い。
4:TP53 変異、CTNNB1 変異、TERT promoter 変異などが悪性度に関与する
5:過形成性病変で腫瘍ではない。 - 57.1
1:ライトグリーン好性や黄色調を示す。 - 58.5
5:4つのグレードに分類される。 - 59.24
2:比較的予後良好。
4:好酸性顆粒状細胞質のeosinophilic cellと大型淡明細胞のpale cellの2種類がみられる。 - 60.12
3:尿中に見られることもある。
4:外線領域に発生しやすい。肥大症は内腺に多い。
5:多くは腺房由来で腺房腺癌とも呼ばれる。
- 41.3(BC)
- 【呼吸器】の解答
-
- 61.4(CD)
A:肺胞は呼吸細気管支からみられる。
B:肺胞同士は肺胞孔を通して繋がる。
E:気管腺や気管支腺は混合腺。 - 62.5(DE)
A:粘液を有するため、それがヘマトに淡染する。
D:円柱上皮は通常、頂部(線毛側)とは逆に存在する。
E:CCP細胞とは変性した線毛円柱上皮細胞のこと。 - 63.4(CD)
A:腺房型は浸潤性腺癌の一つ。
B:微小浸潤性腺癌は置換性増殖が主体である。
E:低悪性度は90%の近くの症例で陽性、高悪性度は約半数で陽性を示す。 - 64.2(AE)
A:必要最小限であれば使用しても良い。
E:このような場合は疑陽性と判定する。 - 65.1(AB)
C:第一選択は抗がん剤、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬を使った薬物療法となる。
D:3~4週を1サイクルとし、明らかながんの進行がないかぎりは4〜6サイクル繰り返して投与を行う。
E:分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤は副作用が小さい。 - 66.3(BC)
B:軟骨主体のものが多い。
C:単発例の方が多い。 - 67.5(DE)
D:コンデンサーを下げるとコントラストが上がり観察しやすい。
E:上昇する。 - 68.2(AE)
B:高円柱状で細胞質に粘液を持つ場合は浸潤性粘液性腺癌に分類される。
C:立体的で結合性の強い集塊が見られる。
D:明瞭であることが多い。 - 69.3(BC)
A:DNAウイルスである。
D:核形不整やクロマチン増量は伴わないことが多い。
E:ヘモジデリンを貪食した組織球が見られる。 - 70.5(DE)
D:胸腺腫では未熟リンパ球が見られるが、胸腺癌ではみられない。
E:膵組織を含むことが多い。 - 71.2
1:6~13%程度陽性がみられる。
3:極めてまれであるが、共発現例の報告がある。
4:染まる。
5:核に染まる。 - 72.1
2:喫煙者にも非喫煙者にも発生する。
3:6種類
4:AISと共に含まれる。
5:非連続的な複数の浸潤部は別々に計測して最大部分を採用する。 - 73.1
2:「ないこと」ではなく、「あること」が浸潤の定義に含まれる。
3:「ないこと」ではなく、「あること」が浸潤の定義に含まれる。
4:「ないこと」ではなく、「あること」が浸潤の定義に含まれる。
5:関係がある。これがあれば浸潤性腺癌となる。 - 74.1
1:日本53%、米国11.3%
2:日本9.7%、米国32.2%
3:日本2.8%、米国4.3%
4:日本0.9%、米国1.7%
5:日本0.3%、米国7% - 75.5
進行例や晩期の病変では好酸球は目立ない。線維性瘢痕の形成や囊胞化,蜂窩肺が主な所見となる。 - 76.5
1:通常喀痰検体で見られることは少なく、気管支擦過では比較的多い。
2:類円形でN/C比は大きい。
3:細顆粒状で分布は不均一である。
4:境界は不明瞭である。 - 77.2
1:肺胞上皮置換性に増殖することが多い。
3:線維性血管間質を中心に”もたない”腫瘍細胞集塊の増殖である。
4:みられる。充実性の場合、粘液を持つ細胞の数が本型の診断に重要となる。
5:神経内分泌マーカーは特徴ではない。CDX2, MUC2, CK20などの陽性が特徴。 - 78.34
1:男性の発生が多い。
2:壊死が見られる場合異型カルチノイドになる。
4:混合型小細胞癌に分類される。
5:見られることもある。その他メラニン産生などもある。 - 79.15
1:腺癌ではなく、扁平上皮癌の特徴である。
5:大きい。一般的にリンパ球の3倍程度までの大きさが存在する。 - 80.24
1:低悪性度と高悪性度に分類される。
3:Ⅳ型コラーゲンやlamininに陽性を示す。
5:肺では非常に稀な腫瘍である。
- 61.4(CD)
- 【消化器】の解答
-
- 81.1(AB)
C:ブラシの方が細胞採取量が多いため良い。
D:広い範囲を擦過する。
E:場合によっては強めに擦過することもある。 - 82.3(BC)
B:第一選択は手術療法。
C:低悪性度腫瘍に分類される。 - 83.3(BC)
A:オンコサイトーマなどでも見られるため、この一つの所見では確定できない。
D:みられない。多形腺腫や腺様嚢胞癌などにみられる。
E:扁平上皮癌が最も多く、粘表皮癌などもある。 - 84.4(CD)
C:一般に低異型度の方が粘液産生が豊富。
D:低異型度の、高異型度、非浸潤癌、浸潤癌と多段階的に発育するため同一病変に異型度の異なる病変も少なくない。 - 85.5(DE)
A:背景はきれいなことが多い。
B:クロマチン増量やN/Cの高い深層型異型細胞がみられる。
C:Tzanck細胞は尋常性天疱瘡などでみられ、エナメル上皮腫は集塊辺縁の柵状配列などを特徴とする。 - 86.2
2:胆管癌より変性が強く、細胞数が多い。 - 87.1
2:リンパ球浸潤が目立つ。
3:desmin, caldesmon, calponin, actin(αSMA)などの筋原性マーカーが陽性となる。KITはGISTのマーカー。
4:非上皮性腫瘍はどの採取法でも結合性が弱い。
5:MALTリンパ腫が最も多い。 - 88.4
1:ソマトスタチンが分泌される。
2:グレリンが分泌される。
3:コレシストキニン(パンクレオザイミン)が分泌される。
5:インクレチン(GLP-1)が分泌される。 - 89.5
5:非上皮性腫瘍の神経性腫瘍に分類される。 - 90.2
2:下部回腸~上行結腸、回盲部に多い。 - 91.1
1:通常の結核と同様に乾酪壊死がみられる。 - 92.2
1:腺房細胞マーカーであるBCL-10やトリプシンなどは陰性になる。
3:Hyaline globulesはPAS陽性。
4:核に陽性を示す。
5:細胞の結合性は弱い。 - 93.5
1:高分化なものに多い。
2:エストロゲン、アンドロゲン等の服用歴(経口避妊薬を含む)がある女性に多い。
3:悪性腫瘍。
4:核小体が目立つ。 - 94.1
2:両細胞とも陽性となるため鑑別には使えない。
3:区分Vは悪性疑い、悪性は区分VI。
4:耳下腺に多い。
5:ETV6-NTRK3は分泌癌、腺様嚢胞癌はMYB/MYBL1。 - 95.1
1:MUC6は陰性。 - 96.45
4:小集塊で重要な項目とされるのは核腫大、核形不整、クロマチン異常の3項目。
5:濃縮が強くなる。 - 97.23
2:良性だが壊死細胞を認めることがある。
3:Edmondson分類のⅣ型に相当する。 - 98.14
2:核分裂像は稀。
3:直腸に多い。
5:Grade分類はki-67と核分裂数により決定するため細胞診では区別できない。 - 99.35
3:GISTで陽性になるのは主にCD117(c-kit)、CD34、DOG1など。S100も陽性になることはあるが一部である。
5:Helicobacter pyloriは腸上皮化生や萎縮粘膜を引き起こす。Barrett食道は関係ない。
100.24
1:小型化する。
3:軽度異型結節、高度異型結節、早期肝細胞癌の順に細胞密度が増加する。
5:高分化な方が細胞質の好酸性顆粒が明瞭。
- 81.1(AB)
- 【婦人科】の解答
-
- 101.1(AB)
C:子宮内膜癌との関連は直接あるわけではない。
D:必ずではない。持続感染が問題で、特に軽度異形成の場合は次に進行する頻度は低い。
E:有用である。酢酸加工などによって肉眼的にある程度推定できる。 - 102. 2(AE)
A:本邦の境界悪性腫瘍で最も多い粘液性は小児から幅広い年齢に発生する。
B:境界悪性でも転移を起こすことはある。
C:卵巣腫瘍は手術療法が基本である。
D:再発することはあるが、死に至らしめるほどではない。 - 103.3(BC)
A:悪性化はかなり少ないとされる。基本的には無い。
C:エストロゲンによって増大する腫瘍であるため、閉経後は縮小することが多い。
D:12種類の平滑筋腫があり、その中には「転移性平滑筋腫」も存在する。
E:発生する場所などによっては影響することがある。 - 104.2(AE)
B:進展の割合は数%程度ではあるが、増殖症自体の発生頻度は比較的高い。
D:増殖症は病変の範囲が広く、異型増殖症は限局性のことが多い。
E:異型増殖症や高分化な癌の治療薬として用いられる。 - 105.4(CD)
A:排卵障害が生じ、月経異常や不妊などに関連する。
B:定義の中に「肥満」が存在する。
C:インスリン抵抗性と関連があると言われる。
E:LHは上昇、FSHは減少する。 - 106.3(BC)
A:円錐切除はCIN3から適応である。
D:経過観察では不十分。NILMの場合は次回定期健診となる。
E:コルポや生検などの精密検査はLSIL以上の時に行う。 - 107.3
- 108.4
- 109.4
1:乳癌で高値になるマーカーの一つ。
2:陽性にならなくはないが特徴的とは言えない。この上昇が特徴的なのは卵黄嚢腫瘍や胎芽性癌など。
3:合胞体性栄養膜細胞を伴う場合は高値になることもあるが、一般的ではない。他に明らかな選択肢があるのであれば除外すべき。
5:粘液性腫瘍や成熟奇形腫などで高値を示す。 - 110.5
1:HPVに関連しないものもあるため、全てに効果があるわけではない。
2:既にHPVに感染している人には効果が限定的である。
3:ワクチンの種類によって3種、4種、9種など一部の型に効果がある。
4:接種後も定期的な検診が必要である。 - 111.5
5:インフルエンザウイルスが胎児に影響したという報告はほぼない。 - 112.5
1:酢酸加工後にみられる異常所見。
2:酢酸加工後にみられる異常所見。
3:異形成などにも見られ、浸潤癌に特異的な所見ではない。
4:正常上皮はヨードで染まる。 - 113.3
1:全胞状奇胎で見られる核型で、父系遺伝子のみからなる。
2:正常な受精による核型であり、胞状奇胎とは関係ない。
3:部分胞状奇胎の核型は通常三倍体(69,XXXや69,XXY)で、これは正常卵子に二つの精子が受精することで生じる。
4:ターナー症候群の核型で、胞状奇胎とは関係ない。
5:性染色体異常であるクラインフェルター症候群の核型で、胞状奇胎とは関係ない。 - 114.3
1:侵入奇胎や絨毛癌などの悪性度の高い場合に選択される。
2:妊孕性が不必要な場合や再発を繰り返す場合などはありえなくないが、一般的には限定的な選択となる。
4:脳転移症例などの絨毛性疾患には用いられることもある。
5:ホルモン療法は一般的に聞かない。 - 115.2
1:鋸歯状変化は分泌期の特徴。増殖期の腺管は細く直線的で、細胞増殖が活発。
3:核分裂像は増殖が活発な増殖期にみられやすい。
4:核下空胞は分泌期初期にみられる。後期に進むにつれて核の上に移行する。
5:妊娠時に起こる内膜間質の反応で月経とは関係ない。 - 116.35
3:乳汁の産生促進や排卵抑制作用がある。
5:子宮筋の収縮を抑制する。 - 117.45
1:手術療法(円錐切除術や単純子宮全摘術)が主な治療法。
2:プロゲステロン製剤などのホルモン剤を用いることがある。
3:基本的に外科手術を行う。進行例などは化学療法の併用もある。 - 118.14
1:これは文章のままで、関連がある。
2:胃型はHPVとの関連が無い、「HPV非依存性腺癌」である。
3:p16INK4aはHPV感染を示す指標となる。胃型はHPVと関連が無いため陰性となる。
5:70%はびまん性に陽性を示すとされる。 - 119.12
文章問題から考えられるのはリンチ症候群である。リンチ症候群ではMLH1、MSH2、MSH6、PMS2、EPCAMの遺伝子異常が知られている。リンチ症候群は、大腸癌と子宮内膜癌(女性)や胃癌(男性)など様々な癌の合併が生じる常染色体優性遺伝の遺伝性疾患である。 - 120.15
2:エストロゲン依存性の疾患であるため、エストロゲン分泌が低下する閉経後は症状が改善することが多い。
3:手術の適用もある。
4:がん化にも関連する。卵巣では明細胞癌の発生と最も関連する。2番目は類内膜癌。
- 101.1(AB)
細胞診模擬試験 ~難易度8~の解説
64.5%(77.4問正解/120問中)
模試の点数入力はこちらから
※点数を送って頂くことでより正確な平均点が集計できます。
ご自身の現在の位置を測定するためにぜひご協力いただければ嬉しいです。
【難易度8】本番レベル~本番より難しい問題です。
本番より難しい問題を解くことで合格する確率を上げることができます。
多様な問題に触れ、あらゆる問題に対応できる適応力を手に入れましょう。
試験まで一緒に頑張っていきましょう
- 【総論】の解答
-
- 1. 4(CD)
- A
副腎皮質機能が低下する疾患。副腎皮質自体に問題がある場合と、下垂体からの副腎皮質刺激ホルモン分泌に問題がある場合の2種類がある。副腎皮質刺激ホルモンは皮膚や粘膜の色素沈着(メラニン沈着)を促す作用があり、副腎皮質自体に問題がある場合は副腎皮質刺激ホルモンが過剰(代謝異常)となるためメラニンの沈着がみられる。 - B
蛋白質であるアミロイドが様々な部位に蓄積する疾患で蛋白質代謝異常に分類される。多発性骨髄腫や甲状腺髄様癌などでみられる。 - C
糖代謝異常の糖原病に代表される先天性疾患でリソソームがもつ酵素が欠損している。脂質代謝異常で有名な疾患としてゴーシェ病やニーマンピック病などがある。 - D
銅代謝異常で有名なものはウィルソン病。ヘモジデローシスは様々な部位に鉄が沈着する鉄代謝異常。 - E
核酸とはDNAやRNAのことで、この核酸に由来するプリン体の代謝異常で痛風を発生することがある。
- A
- 2. 4(CD)
- A
成熟リンパ球と比較的豊富な淡明細胞質を持つ異型の強い腫瘍細胞が出現する。 - B
管状構造や充実性、腺腔様構造または弧在性の細胞がみられる。核は円形から類円形で明瞭な核小体がみられる。顆粒膜細胞腫との鑑別を要する場合がある。 - C
単核の細胞と多核の細胞が出現する。単核細胞はラングハンス型、多核細胞はシンチジウム型のトロホブラストに由来する。流産を示唆する所見も同様と考えて良い。 - D
単核細胞と多核細胞が出現する。特徴的な細胞像だけでなく、好発年齢、好発部位も合わせて覚えておきたい。 - E
N/C比の高い小型円形の腫瘍細胞が特徴的。ロゼット構造を認めることもある。
- A
- 3. 4(CD)
- A
男性の罹患数で最も多いのは前立腺癌 - B
女性の罹患数で最も多いのは乳癌 - C
男性の死亡数で最も多いのは肺癌、次いで、胃癌、大腸癌、膵癌、肝臓癌 - D
女性の死亡数で最も多いのは大腸癌。次いで、肺癌、膵臓癌、乳癌、胃癌 - E
男性食道癌の罹患数は増加傾向
- A
- 4. 3(BC)
- A
一部の認知症に関連する小体 - B
アルコール性肝炎や肝細胞癌などにみられる細胞質内の小体。中間径フィラメントが蓄積したものと考えられている。 - C
免疫グロブリンの過剰産生によってみられる細胞質内の小体。多発性骨髄腫などでみられる。 - D
卵黄嚢腫瘍で見られる小体。腫瘍細胞が血管周囲に配列し、その外側に空間がみられる構造を指す。この言葉だけだと分けわからないが、とてもきれいな画像が卵巣癌取扱い規約に記載されているため是非職場や学校の規約を見てほしい。この構造を細胞診検体でみるのは難しい。 - E
悪性黒色腫にみられる核内封入体。
- A
- 5. 2(AE)
- 6. 1(AB)
- 7. 5(DE)
- A
筋系 - B
神経細胞 - C
間葉系 - D
核(核膜) - E
中枢神経幹細胞
- A
- 8. 3.(BC)
- A
基本的には単層円柱上皮。一部線毛を持つものもあると書いている参考書もあるがきにしなくていい。化生も起きやすい臓器だから線毛は化生の可能性もある。 - B
分泌細胞と線毛細胞がある。線毛細胞はエストロゲンで増加し、漏斗部と膨大部に多い。分泌細胞はプロゲステロンで増加し峡部から子宮部に多い。 - C
多列線毛円柱上皮で被覆される。 - D
太い部分は線毛あるけど、基本的には無しで覚えてよい。 - E
尿路上皮で被覆される。尿路上皮は腎盂から膀胱まで(尿道も一部は尿路上皮)。
- A
- 9. 1(AB)
- A
漏出分泌 - B
漏出分泌 - C
離出分泌 - D
全分泌 - E
内分泌
- A
- 10. 4(CD)
- A
核小体が目立つ大型腫瘍細胞とリンパ球が特徴 - B
核小体が目立つ大型腫瘍細胞とリンパ球が特徴 - C
間質性粘液や軟骨様基質と上皮性細胞集塊の出現が特徴 - D
ジアスターゼ抵抗性PAS陽性の顆粒状細胞質が特徴的。S100に陽性を示す。 - E
tingible body macrophageと各成熟段階のリンパ球がみられる。悪性リンパ腫と間違えないように注意。
- A
- 11. 4
- 12. 1
- 1
皮膚(口腔も)のカフェオレ斑(色素沈着)、線維性骨形成症、思春期早発症を特徴とする疾患 - 2
大腸ポリポーシス、軟部腫瘍、骨腫を伴う常染色体優性遺伝疾患 - 3
皮膚、消化管、乳腺、甲状腺、中枢神経などに過誤腫性病変が多発する常染色体優性遺伝疾患 - 4
大腸ポリポーシスと脳腫瘍が合併する疾患 - 5
主に涙腺や唾液腺が障害される自己免疫性疾患で口腔、眼の乾燥がみられる
- 1
- 13. 3
- 1
1桁の数字は基本T細胞系 - 2
紡錘形細胞腫瘍は次のマーカー分けが有効。
①消化管間質腫瘍 c-kit(CD117), CD34, DOG1
②神経鞘腫 S100
③平滑筋腫瘍 desmin, α-SMA - 3
このリンパ腫はALK陽性のものと陰性のものがある。ALK陽性は若年者に多く予後良好ALK陰性は中高年に多く予後不良 - 4
胆道系はCA19-9が有名なマーカー - 5
このマーカーは肝疾患や卵黄嚢腫瘍でみられる
- 1
- 14. 2
- 1
内 - 外 - 内 - 2
外 - 外 - 外 - 3
外 - 内 - 中 - 4
外 - 内 - 外 - 5
外 - 内 - 内
- 1
- 15. 1
- 16. 2
- 17. 2
- 18. 5
- 5
小児に好発する腫瘍で嚢胞を形成する。コレステリン結晶や扁平上皮細胞がみられる。バーベック顆粒はランゲルハンス組織球症の特徴。
- 5
- 19. 24
- 1
細胞膜&細胞質 - 2
核 - 3
細胞質 - 4
核 - 5
細胞質&細胞膜
119種類の抗体情報まとめはこちら
(閲覧には過去問解説集記載のパスワードが必要です)
- 1
- 20. 14
- 1. 4(CD)
- 【技術】の解答
-
- 21.5(DE)
- A
通常の組織と同様の扱いであるため、ホルマリンで固定する。 - B
ある程度の細胞量が無いと組織ブロックにできない。 - C
塩化カルシウムを用いるのはアルギン酸ナトリウム法。
- A
- 22.4(CD)
- A
開口絞りは対物開口数の70~80%が最適。 - B
このフィルターは減光フィルターとも呼ばれ、照明光の色を変えずに明るさだけを調整する。 - C
分解能の値は分解できる2点間の距離を表す。つまりこの値(距離)が小さいほど分解能が良いことを示す。 - D
開口数が大きいと焦点深度は浅くなる。 - E
補正環とはカバーガラスの厚みのズレを補正してくれるもの。
高倍率(高開口数)のものは焦点深度が浅いため、厚みのズレを補正しないとぼやけてしまうことがある。
- A
- 23.1(AB)
- A
非水溶性のマリノールを使う。 - B
まず70~80℃で封入剤を硬化させた後、50~60℃で軟化させて剥がせるようにする。 - C
1つの標本を複数に切り分けることが可能になるため、同一の標本に対して複数の抗体で免染が可能。 - D
ガラスが破損した場合はこの方法で一度剥がして新スライドガラスに移すことができる。 - E
封入してから時間が経つとカバーガラスが剥がれにくいため、傷をつけるとキシレンが浸透しやすくなり剥がれやすくなる。
- A
- 24.4(CD)
- A
Papで使うヘマトキシリンは退行性。 - B
EA50液の色素の組成は下の3つ。
・エオジン(酸性)
・ライトグリーンSF(酸性)
・ビスマルクブラウン(塩基性) - C
細胞質関連の色素は陰性に荷電して陽性荷電の細胞質と結合する。 - D
OG6液とEA50液溶媒は95%エタノールで分別も95%エタノールで行う。 - E
ショール染色はPapの迅速verで、Papより染色時間が短縮される。使われる色素も異なる。
- A
- 25.3(BC)
- A
これはこのまま - B
核内抗原は熱処理賦活が有効なことがある。ただ、過度な熱賦活によって偽陰性を示すこともあるため注意。 - C
乾燥や過ヨウ素酸などの酸処理は抗原性を失活、減弱させることがある - D
LSAB法で使うアビジンはABC法のアビジンより低分子量であるため浸透性が高い - E
ポリマー法はビオチンを使用しないため内因性ビオチンの除去は必要ではない
- A
- 26.4(CD)
- A
共焦点レーザー顕微鏡は3次元構造も見ることが出来る蛍光顕微鏡。より通常の蛍光顕微鏡よりも分解能が高い。FISHは蛍光を使うためこの顕微鏡が有効 - B
細胞診検体はアルコール固定であるため核酸保持率が良い。一方組織はホルマリン固定でホルマリンは核酸保持に悪い影響を及ぼす。 - C
FISHは2色以上の多色で解析することが出来る。マルチカラーFISHなどは全染色体を別々の色に染色する。 - D
重積が強い部分は正確に染色できないことや正確に結果を解析できないことがある。そのため、可能な限り平面的な部分で判定する方が良い。 - E
FISHは検体によってプロトコールの条件検討が必要。組織と細胞診検体ではプロトコールの変更も必要となる。
- A
- 27.3(BC)
- A
ヒアルロン酸に対するコロイド鉄染色の反応はアルシアン青よりも鋭敏 - B
真菌を染める染色として代表的なのはPAS、グロコット、グリドリー。真菌の中でもクリプトコッカスはさらに次の3つも陽性になる。ムチカルミン、アルシアン青、フォンタナ・マッソン。 - D
ベルリン青染色で用いるのはフェロシアン化カリウム。フェリシアン化カリウムはシュモール染色とターンブル青染色。 - E
コッサ反応は硝酸銀を用いる。
- A
- 28.3(BC)
- A
作業環境測定は半年に一回。 - C
女性労働基準規則含まれ細胞診に関係ある試薬はキシレンとメタノール。 - D
第1管理区分は管理良好と判断された状態。改善の措置が必要なのは第3管理区分 - E
- ホルムアルデヒドの管理濃度は0.1ppm。
- A
- 29.2(AE)
- A
圧挫やスタンプでの検体処理は軽めに行わないと挫滅しすぎて見にくくなる。 - D
オートスメアやポアフィルターなどは細胞成分が少ないものに有効。 - E
喀痰は正常の違う部分3か所から採取するが、特に血性部分では血液成分が多いため辺縁から採取する必要がある。
- A
- 30.2(AE)
- A
固定後は改善が見込めない。 - E
乾燥から2日以上経過すると効果が薄い。
- A
- 31.1
- イミダゾール溶液は発色の増感剤として用いられる。共染がみられる場合は、余分な抗体を十分に洗浄する必要があり、洗浄力を上げる方法として選択肢の2~5の方法がある。
- 32.5
- 1
乾燥固定は通常ギムザに用いられるが、ギムザは厚い標本に適さない。 - 2
乾燥固定でギムザを行う際、ゆっくり乾燥すると細胞が収縮傾向を示す。 - 3
PAS反応は湿固定、乾燥固定どちらでも可能だが、乾燥固定では乾燥後95%エタノールで彩度固定すると良い。 - 4
スプレー式コーティング固定は標本から約15cm離して2~3秒間噴霧する。
- 1
- 33.2
- 1
19G, 20G, 22G, 25Gを用いる。ゲージ数が小さいと穿刺性能は下がるが、細胞採取量は多い。ゲージ数が大きいとその逆。 - 2
20~30回ストロークする、いわゆるfanning technipueを用いて腫瘍の様々な部位からまんべんなく採取する。 - 3
大きな腫瘤の中心部は壊死している可能性が有るため辺縁を刺すのが良い。 - 4
粘膜下にも穿刺できるため、GISTやカルチノイドなどの粘膜下腫瘍にも効果的。 - 5
嚢胞は中が空洞で充実性病変は中が詰まっているため後者の方が細胞量が多くなる。
- 1
- 34.4
- 1
ポアフィルター法やサイトスピン法は細胞量の少ない検体に有効 - 2
髄液の細胞は壊れやすいため、1000回転以下の低回転数で10分程度の長時間遠心する。さらに、細胞の破壊とスライドガラスからの剥離を防ぐためにアルブミンなどの蛋白成分を添加する。 - 3
圧挫は組織をそのまま潰すため、組織構築が反映される。 - 4
3回以上のすり合わせは細胞の挫滅を惹起するため行わない。 - 5
サコマノ液は乾燥を防ぐカーボワックスを含むため塗抹後乾燥する。
- 1
- 35.1
- 2
中皮細胞の細胞質は青っぽい好塩基性を示す。 - 3
ギムザ染色はPapと比較して細胞が剥離しにくい(乾燥固定によって)ため、細胞数が少ない脳脊髄液などには有効。 - 4
迅速ギムザとして、ディフクイックやサイトクイックなどがある。 - 5
ギムザで特徴的なロマノフスキー効果はpH6.4で惹起されるためPH6.4のリン酸緩衝生理食塩水を使う。
- 2
- 36.4
無極性色素は主にズダンⅢなどの脂肪染色に含まれる。 - 37.2
- 1
ブラシなどで採取した後固定液にすぐつけるため、乾燥しにくい。 - 2
自然沈降させたり専用の機器で圧をかけて標本を作製するため、そのまま塗抹するよりも時間がかかる。 - 3
塗抹範囲が円形に限定され狭いため、通常より鏡検時間を短縮できる。 - 4
細胞が収縮しやすい傾向にある。 - 5
細胞が均一にそして平面的になりやすい。
- 1
- 38.2
- 1
1日の検鏡枚数は、90枚を上限とする(一日の勤務時間を8時間とし、鏡検時間の長さにより按分し、鏡検時間を制限する)。 - 2
陽性例・疑陽性例判定報告に関しては、細胞診専門医・指導医が必ずチェックし、いかなる理由があろうとも細胞検査士のみの署名では報告しない。 - 3
全例の報告書及び細胞診ガラス標本の保存期間は5年間を基本とする。 - 4
細胞診陰性報告書には、細胞検査士の署名を行う。また、細胞診陰性報告書では、一定の割合にて細胞診専門医・指導医の検鏡を求め、判定と署名を受けるように努める。 - 5
細胞診陰性と判断された症例については、細胞診陰性例の10%以上を、結果報告前に他の有資格者による再スクリーニングを行うことを基本とする。
- 1
- 39.13
- 1
逆転写PCRとはRNAを逆転写してcDNAにした後、そのcDNAを使ってPCRを行う方法。 - 2
熱変性は95℃程度。伸長反応が70℃程度で行われる。 - 3
アニーリング温度は大体55℃~60℃程度であるが、これはプライマーのTm値によって異なる。 - 4
real time PCR法は既知量DNAをスタンダードとしてDNA量を定量できるPCR法。蛍光物質のSYBR Greenや蛍光プローブのTaqManプローブを使って行うことが多い。蛍光を測定するため電気泳動は行わない。 - 5
PCRの標的は核酸(DNAやRNA)であるため蛋白の発現や局在は分からない。
- 1
- 40.25
- 1
黄色 - 2
橙色 - 3
赤色 - 4
黄色 - 5
橙色
- 1
- 21.5(DE)
- 【その他】の解答
-
- 41.4(CD)
- A
中胚葉由来。 - B
腹膜や胸膜などを被覆する中皮細胞は微絨毛はみられる。細胞診試験ではよく”絨毛”と”微絨毛”を変えて出題されるので注意。 - E
壁側胸膜から発生することが多い。
- A
- 42.1(AB)
- A
洗浄細胞診では静止期中皮と呼ばれるシート状の中皮細胞集塊がみられる。体腔液中には通常みられにくい。 - B
肝硬変などでみられる体腔液は濾出液で、濾出液は透明~淡黄色のものが多い。
- A
- 43.3(BC)
- A
悪性中皮腫には上皮型、肉腫型、線維形成型、二相型があり、肉腫型は体腔液中に出現しにくい。 - D
collagenous stromaは中心のコラーゲン物質を覆う周囲の細胞の厚みによってⅠ型~Ⅲ型まであり、I型に臨床的意義はなく良性でもみられる。悪性中皮腫ではⅡ型やⅢ型がみられる。 - E
中皮腫は微絨毛が正常時より発達することがあり、発達した微絨毛は顕微鏡的に辺縁が不明瞭に見える
- A
- 44.3(BC)
- A
有名な筋上皮細胞のマーカーは次の4つ。p63、α-SMA、calponin、CD10。 - B
検体適正時の乳腺細胞診の報告様式は次の4つ分類される。
①正常あるいは良性
②鑑別困難
③悪性の疑い
④悪性 - C
顆粒状の広い細胞質をもつ細胞で、この存在は良性病変を疑う指標の一つになる。
- A
- 45.5(DE)
- A
線維腺腫や葉状腫瘍は【結合織性および上皮性混合腫瘍】に分類される腫瘍で、上皮成分と間質成分がみられる。同種の細胞が出現するため、鑑別困難な時がある。 - D
非浸潤性乳管癌は乳頭型、篩状-乳頭型、篩状、充実型、面皰型があり、面皰型は中心部に壊死がみられる。 - E
一般的な粘液癌はER陽性、PgR陽性、HER2陰性を示す。
- A
- 46.2(AE)
- B
IHCは4µm、ISHは5µmが推奨される。 - C
6時間以上72時間以内が推奨固定時間である。 - D
IHC 2+ではequivocal判定で同じ検体を用いてISH法、もしくは新たな検体を用いてISH法やFISH法を実施しなければならない。 - E
DISH法でHER2/CEP17比2未満かつ1細胞当たりのHER2遺伝子平均コピー数4.0未満の場合は陰性と判定される。
- B
- 47.1(AB)
- A
検体不適正の条件は乾燥、変性、固定不良、末梢血混入、塗抹不良などの標本作製不良もしくは病変の推定に足る細胞 or 成分(10個程度の濾胞上皮細胞からなる集塊が6個以上、豊富なコロイド、異形細胞、炎症細胞など)がない標本。 - B
悪性に含まれる。 - C
嚢胞液は嚢胞液でコロイドや濾胞上皮細胞を含まない標本。稀に嚢胞形成性乳頭がんが含まれることがある。 - D
濾胞性腫瘍には良性の濾胞腺腫と悪性の濾胞性癌が含まれる。 - E
検体不適正にした場合、その理由を記載する。
- A
- 48.2(AE)
- A
好酸性上皮細胞とリンパ球が特徴。 - B
扁平上皮細胞や線毛円柱上皮細胞がみられる。 - C
腫瘍細胞は異型性が強く、結合性が乏しいため孤立散在性に出現する。核は大型でクロマチンに富み核小体は大型で目立つ。 - D
乳頭癌にみられるような核溝、核内細胞質封入体が目立つが、すりガラス状核や核重畳はみられない。 - E
クロマチンはごま塩状で核小体は目立たない。
- A
- 49.5(DE)
- D
乳頭癌との鑑別にCK19(硝子化索状腫瘍-, 乳頭癌+)とKi-67(硝子化索状腫瘍は細胞膜 or 細胞質に+, 乳頭癌は核に+)が有効。 - E
核内細胞質封入体は乳頭癌に特徴的とされるが、硝子化索状腫瘍や髄様癌でも認めることがある。
- D
- 50.5(DE)
- A
Bリンパ球は濾胞と髄質に多い。傍皮質にはTリンパ球が多い。 - B
tingible body macrophageは良性でよくみられる。 - C
木村病はアジアの若年男性の頭頸部に多い。 - D
サルコイドーシスではアステロイド小体やシャウマン小体をみることがある。
- A
- 51.2
- 1
DLBCLは大型で異型の強い細胞がみられるため、分化度の低い腫瘍細胞と鑑別が必要なことがある。 - 3
未分化大細胞リンパ腫はT細胞性。 - 4
中型~大型で異型性の強い細胞がみられる。核形不整が著明で複雑な切れ込み、桑実状、脳回状、分葉状の形態やリード・ステルンベルグ様の核を示す。核が分葉した花弁様細胞と呼ばれる細胞が特徴的。 - 5
t(11;14)(q13;q32)がみられるのはマントル細胞リンパ腫。
- 1
- 52.4
- 結節性リンパ球優位型の腫瘍細胞はCD20陽性、CD15と30は陰性。古典的ホジキンリンパ腫の腫瘍細胞はCD15、CD30が陽性でCD20陰性。
- 53.3
- 3
30~60歳代に多い。
- 3
- 54.1
- 2
骨内に発生する髄内骨肉腫と骨表面に発生する表在性骨肉腫に大別され、ほとんどは髄内骨肉腫で、表在性骨肉腫は稀。 - 3
細胞質内や粘液性基質にはグリコーゲンが豊富に含まれ、PAS陽性を示す。また粘液性基質は間質性基質も含むためアルシアン青にも陽性を示す。 - 4
N/C比の高い小型類円形腫瘍細胞が弧在性に出現する。 - 5
転移性の方が圧倒的に多い。
- 2
- 55.3
- 1
早朝尿は細胞変性が強いため細胞診検体に適さない。随時尿を採取する。 - 2
自然尿では乳頭状病変より平坦状病変の方が細胞が出現しやすい。 - 4
反応性尿細管上皮細胞の同定には ビメンチン陽性所見が有用といわれている。 - 5
尿管皮膚瘻とは尿管を直接腹部の皮膚に縫い付けて尿の出口を作ることである。変性した腺細胞がみられるのは切除した小腸と尿管をつなぎ、皮膚に縫い付けて尿の出口を作る回腸導管尿。
- 1
- 56.3
癌は通常集塊辺縁にアンブレラ細胞を認めない。 - 57.3
神経鞘腫はAntoni A型とB型があり、典型的な観兵配列を示すのはAntoni A型。 - 58.3
髄芽腫ではHomer Wright型偽ロゼットがみられる。真性ロゼット(Flexner-Wintersteiner ロゼット)は上衣腫や網膜芽腫でみられる。 - 59.35
- 60.15
- 2
尿中バニリルマンデル酸を特徴とするのは副腎髄質腫瘍(褐色細胞腫、神経芽細胞腫)。 - 3
クロマチンの増量した小型円形の裸核状細胞がみられる。 - 4
胎児型横紋筋肉腫は別名ブドウ状肉腫とも呼ばれ、ブドウの房状にポリープ状の病変を形成する。
- 2
- 41.4(CD)
- 【呼吸器】の解答
-
- 61.2(AE)
- B
肺胞と肺胞を繋ぐ孔を 肺胞孔(コーン孔)と呼び、肺胞と細気管支を繋ぐ孔をランバート管と呼ぶ。 - C
肺動脈は細気管支を通り、肺静脈は小葉間結合組織を通るため両者じゃ伴走しない。 - D
肺胞は呼吸に関与するため、呼吸細気管支あたりからみられる。
呼吸器の解剖イラストは解説はこちら
- B
- 62.3(BC)
- B
肺胞表面積の大部分を占めるのは扁平なI型。肺胞表面積の90%を占める。数はⅡ型の方が多いといわれる。 - C
肺障害時に分裂・増殖するのはⅡ型。Ⅱ型が分裂してⅠ型になるといわれている。
呼吸器の解剖イラストは解説はこちら
- B
- 63.3(BC)
- B
喀痰などの液に浮いた浮遊細胞は擦過などで得た新鮮細胞より変性が強い。 - C
粘膜下腫瘍にできる腫瘍は基本的に喀痰に出にくい。EUS-FNAなどが有効。
- B
- 64.3(BC)
- A
クルシュマンの螺旋体は喀痰にみられるヘマトキシリン好性の糸状物質。狭くなった気管支を粘液が通ることでらせん状になるといわれている。慢性気管支炎、肺癌、肺気腫、結核など様々な疾患でみられ、疾患特異性はない。 - D
アスベストは小体は鉄分を含むためベルリン青染色に陽性を示す。 - E
線毛のないゴブレット状の形状を示し、細胞質は多量の粘液のために明るい空胞状で、淡いピンク色を呈し、核は粘液により圧排されている。
- A
- 65.5(DE)
- A
Y字状(45度)に分岐する菌糸と隔壁を有し、菌糸の幅が一定。 - B
嫌気性〜微好気性のグラム陽性桿菌で狭義の放線菌に含まれる。黄色~黄緑色の菌塊(硫黄顆粒)が診断に有用となる。 - C
CD4陽性T細胞に感染する。 - E
その他、Grocott染色、PAS染色、Alcian blue染色、mucicalmin染色、墨汁法(陰性になる)などで確認できる。
- A
- 66.1(AB)
- A
ヘルペスウイルス5型に該当するDNAウイルス。 - B
組織標本や気管支肺胞洗浄液で巨細胞核内封入体を有する細胞を(ふくろうの目)を検出することが可能であるが、他のヘルペスウイルス感染細胞にも共通であるため、確定はできない。免疫染色による抗原検出やISH法によるDNA検出で診断が確定する。
- A
- 67.3(BC)
- A
虫卵が喀痰や便に排出される。一方、宮崎肺吸虫は喀痰や便から虫卵が検出されにくい。 - D
末梢にできやすい。細胞像で出題される可能性もあり。 - E
肺胞上皮への分化を示す細胞が、充実性、乳頭状に増殖し、硬化(線維化)、出血を伴う腫瘍。さらにⅡ型肺胞上皮様の立方状細胞と分化方向の明らかでない円形細胞の2種類の細胞を認めることが特徴的。ヘモジデリン沈着や泡沫状マクロファージも目立つ。細胞像で出題される可能性もあり。
- A
- 68.4(CD)
- C
肺癌の危険因子には次のようなものがある。喫煙、慢性閉塞性疾患、職業的暴露(アスベスト、クロム酸、ラドン、ヒ素、クロロメチルエーテル、クロム酸、ニッケルアスベスト、ラドン、ヒ素、クロロメチルエーテル、ニッケルなど)、大気汚染、結核、肺がんの既往歴・家族歴 - D
肺癌は比較的予後不良な癌の一つ。
- C
- 69.5(DE)
- A
肺癌は腺癌、扁平上皮癌、神経内分泌腫瘍(NET)、大細胞癌、その他に分類され、頻度は各々40~70%:10~20%:10~15%:1~3%。 - B
高悪性度成分には充実型、微小乳頭型、篩状型、複雑腺系型が含まれる。 - C
置換性増殖を優位とする3cm以下の孤立性腫瘍で、0.5cm(5mm)以内の浸潤部分を有する。複数の浸潤部分があっても総和ではなく、最大のものを浸潤径として計測する。 - D
上皮内腺癌は非浸潤癌であるため、以下の4つの浸潤所見がみられない。
①置換型以外の組織亜型が1つ以上
②間質内に活動性線維芽細胞の増生がある
③脈管、胸膜浸潤がある
④肺胞腔内に腫瘍細胞の分離性増殖を認める(含STAS)。腫瘍内に壊死がある場合も浸潤性腺癌。 - E
浸潤性粘液性腺癌は普通と違ってEGFRの変異が稀とされる。代わりにKRASの変異をもつことが多い。
- A
- 70.4(CD)
- C
ドライバー遺伝子の変異は腺癌の約80%にみられる。 - D
- 知っておきたいドライバー遺伝子として以下の10種類があるが、EGFRの頻度が高い。
①EGFR
②ALK
③ROS1
④BRAF
⑤MET
⑥RET
⑦KRAS
⑧HER2
⑨NTRK
⑩PD-L1
- C
- 71.2
基本的な細胞像とマーカーに関する問題。小型裸核状の時点でた1と3と5が消え、核小体を認めることで4の可能性が下がる。さらに扁平上皮癌マーカー陽性、神経内分泌マーカー陰性で4を確実に否定する。
以上から残った2が正解となる。1のようなあまり知らない選択肢が出ると焦ってパニクる人もいるが、試験には選択肢があるから落ち着いて消去法で選んでいこう。 - 72.4
- 1
同心円状とも呼ばれる構造で厚みのある細胞質や構造物でみられる所見。扁平上皮癌に多い。 - 2
粗いクロマチンは扁平上皮癌の特徴。 - 3
代表的な扁平上皮癌の特徴。 - 5
扁平上皮癌に多い特徴。
- 1
- 73.3
- 1
細胞質は狭小でN/C比が高く、裸核状のことが多い。 - 2
核小体は目立たないことが多い。 - 3
この現象は小細胞癌の壊死部でよくみられるもので腫瘍細胞由来の核物質が血管壁に沈着して好塩基性に染色される現象。 - 4
光顕のみで診断可能で免疫染色は必須ではない。 - 5
小細胞癌は悪性度が高いため、他にどんな組織型が混在しても小細胞癌(厳密に言うと、混合型小細胞癌)になる。
- 1
- 74.2
- 1
神経内分泌腫瘍の核縁は薄いことが多い - 2
診断には神経内分泌分化や神経内分泌顆粒を免染や電顕で確認する必要がある。 - 3
小細胞癌は一番重要度が高いため、他にどんな組織型が混在しても小細胞癌(混合型小細胞癌)になる。他の組織型に小細胞癌を含むことは無い。 - 4
両者とも同じ神経内分泌腫瘍で大きい細胞や核小体をもつことがあるため鑑別を要することがある。 - 5
診断には核分裂像が重要で壊死を伴わない部分の11個以上/2mm2が基準となる。
- 1
- 75.2
- 1
壊死の有無と核分裂像の数で定型と異型に分ける。 - 3
粘膜下腫瘍であるため、喀痰に認めることはほとんどない。EUS-FNAなどが有効。 - 4
細胞質は幅広く泡沫状であるが、細胞質の辺縁は不明瞭。典型的なパターンだと、類円形の核があってその周りにモヤモヤしたライトグリーンの物質があるようにしか見えないものが典型的。 - 5
定型カルチノイドの定義は「2mm2あたり核分裂像が2個未満で、壊死を伴わないカルチノイド。」
- 1
- 76.1
- 1
CK7(ー)、CK20(+) - 2
CK7(±)、CK20(ー) - 3
CK7(+)、CK20(±) - 4
CK7(+)、CK20(ー) - 5
CK7(+)、CK20(ー)
- 1
- 77.4
細胞診検体は組織の一部が剥離した喀痰などを使うため全体を把握することができない。そのため組織全体で判定をする必要がある組織型は使用できない。生検も一部しか見ることができないため推奨されない推定組織型がある。具体的には、上皮内腺癌、微小浸潤腺癌、大細胞癌、腺扁平上皮癌、肉腫様癌、非扁平上皮癌の6つ。 - 78.
前縦隔の時点で1は考えにくい。リンパ球が多い時点で1と3は考えにくい。細胞質が広い時点で多くの2は考えにくい。ホジキンリンパ腫の可能性を否定できないが、類円形核で否定される。類円形核の時点で4が考えにくい。 - 79.25
- 1
中縦隔 - 3
前縦隔 - 4
上縦隔 - 5
前縦隔、中縦隔
- 1
- 80.45
- 1
核のくびれはDやEで見られる - 2
OG好性細胞で1/3のもの。 - 3
ときに細胞相互封入像がみられる。
- 1
- 61.2(AE)
- 【消化器】の解答
-
- 81.3(BC)
- B
頬粘膜は非角化型重層扁平上皮。 - C
上咽頭は多列線毛円柱上皮。
- B
- 82.5(DE)
- A
LBCでは細胞の回収率低下や乾燥が防げるため、有効 - B
含嗽(がんそう)とは”うがい”のことで、鏡検を妨げる食物残渣や血液を洗う効果や細胞量を増やす効果があるため行う。 - C
どこでも綿棒よりブラシの方が細胞採取量が多い
- A
- 83.2(AE)
- A
きれいな背景にケラトヒアリン顆粒を含む細胞がみられる。Two-tone color細胞質をもつ細胞もみられるのが特徴。 - B
立方から円柱状細胞の柵状配列が特徴。 - C
口腔カンジダ症の一つであるため、カンジダの所見がみられる。 - E
自己免疫性水疱形成性疾患でデスモゾームの消失により棘融解した細胞(結合性が失われた細胞)であるTzank cell(ツァンク細胞)がみられる。
- A
- 84.4(CD)
IgG4関連唾液腺炎は高度なリンパ球・形質細胞浸潤と著明な硬化性線維化がみられ、腺房細胞は萎縮・消失する。良性疾患なのでもちろんリンパ球に異型はみられない。 - 85.1(AB)
- C
低悪性度のものが多い。ちなみに低悪性度のものは粘液細胞が多い。 - D
筋上皮細胞の細胞質が淡明で豊富 - E
チモーゲン顆粒を持たないのが特徴の一つ。
- C
- 86.5(DE)
- A
非角化型重層扁平上皮 - B
下部は平滑筋のみで被覆される。上部は横紋筋。中部は横紋筋と平滑筋。 - C
バレット食道は本邦より欧米の方が多い。
- A
- 87.1(AB)
- C
表在癌は粘膜下層にとどまるもの。早期癌は粘膜内にとどまるもの。 - D
隆起性病変が多い。 - E
細胞質は好酸性顆粒状でジアスターゼ抵抗性(非消化性)のPAS陽性物質をもつ。
- C
- 88.5(DE)
- C
壁細胞がビタミンB12(赤血球の成長に必要)の吸収を促進をする【内因子】出しているため、胃を全摘すると赤血球が正常に成長できず悪性貧血を引き起こす。 - D
幽門部に多い。 - E
消化器では胃の筋層だけ内斜筋、中輪筋、外縦筋の3層構造になっている。他は大体内輪筋と外縦筋。
- C
- 89.4(CD)
- A
GISTが最も多い。 - B
MALT細胞リンパ腫に関与する。 - C
上皮性腫瘍で孤立散在性に出るものは基本的に低分化。 - D
・1型:腫瘤型
・2型:潰瘍限局型
・3型:潰瘍浸潤型
・4型:びまん浸潤型
・5型:分類不能 - E
卵巣転移はクルーケンベルグ腫瘍。消化器癌(特に胃癌)は転移する場所によって以下の3つに分けられる。
①左鎖骨上窩リンパ節 ー ウィルヒョウ転移
②卵巣 ー クルーケンベルグ腫瘍
③ダグラス窩 ー シュニッツラー転移
- A
- 90.2(AE)
- B
胃、小腸、大腸の順に多い。 - C
非上皮性腫瘍に分類される - D
小腸のGISTでみられる
- B
- 91.4
- 2
鋸歯状構造を示すのは過形成性ポリープ、鋸歯状腺腫、広基性鋸歯状腺腫/ポリープがある。 - 3
特徴として次のようなものがある。男性に多い、色素沈着、爪の萎縮、脱毛、遺伝性無し。 - 4
大腸ポリポーシスに骨腫瘍や軟部腫瘍を合併する常染色体優性遺伝疾患。大腸ポリポーシスに脳腫瘍を伴うのはターコット症候群。
- 2
- 92.1
- 2
原因不明の炎症性疾患で杯細胞の減少が認められる。 - 3
結核がどこでできても乾酪性類上皮肉芽腫。 - 4
アメーバ赤痢菌は原虫。 - 5
アセチルコリンエステラーゼ活性の増加を認める。
- 2
- 93.3
- 1
肝臓はグリソン嚢と呼ばれる膜に囲まれていて、それが中に入り込んでグリソン鞘になり多数の小葉を作る。 - 2
血液は外から肝臓方向に、胆汁は肝臓から外方向に流れる。 - 3
肝三つ組みは小葉間胆管、小葉肝動脈、小葉肝静脈(門脈)のこと。 - 4
肝臓の中の血管は比較的大きめの孔がたくさんある洞様毛細血管で、類洞と呼ばれる。
- 1
- 94.4
- 1
アルコール性肝疾患も非アルコール性脂肪性肝炎も肝細胞癌に進行する可能性が有る。 - 2
中高年の女性に多い自己免疫性疾患。 - 3
正常肝などから発生し、肝硬変からは発生しない。 - 4
核腫大やN/C比の高い細胞がみられ、高分化型肝細胞と鑑別が必要な場合がある。 - 5
細胞密度が増した増殖性病変で軽度構造異型、細胞異型を示すが癌ではない。
- 1
- 95.2
肝細胞癌には組織学的な分化度があり、それぞれに特徴があるとされる。- 高分化
好酸性顆粒と脂肪変性 - 中分化
偽腺管構造と胆汁産生 - 低分化
巨細胞と多核細胞 - 未分化
壊死と異型の強い細胞
- 高分化
- 96.5
- 1
十二指腸乳頭部は 微絨毛を持つ吸収上皮、杯細胞、パネート細胞、内分泌細胞がみられる。 - 2
胆嚢は粘膜筋板と粘膜下層がない。 - 3
非腫瘍性に扁平上皮化生は稀で幽門化生や杯細胞化生が多い。 - 4
正常でも見られる。
- 1
- 97.4
- 1
肝細胞癌と違って 肝硬変の合併はほとんど無い 。 - 2
正常上皮が円柱上皮であるため、発生頻度が高いのは腺癌。 - 3
高齢の男性に多い。 - 4
胆汁産生は通常はみられない 。 - 5
症状は無いことが多いが、肝門部発生例では閉塞性黄疸を伴うこともある。
- 1
- 98.2
- 1
高齢男性に多い。 - 2
5年対生存率は7%と低く、予後不良な腫瘍の一つ。 - 3
通常主膵管との交通を認めない。 - 4
CD10、βカテニン(核)、ビメンチン、CD56が陽性でクロモグラニンAやトリプシンは陰性。 - 5
膵頭部に多い。
- 1
- 99.34
- 100.15
- 1
ホルモンを産生する機能性、産生しない非機能性があり、非機能性の方が多い。 - 2
zollimger-Ellison syndromeは胃酸の過剰分泌と進行の速い難治性の消化性潰瘍が生じるものだからガストリノーマと関連する(胃酸を出させるのはガストリン)。 - 3
MENⅠ型の一部に含まれる。 - 4
核分裂像とKi-67によるグレード分類が行われ、NET G1~G3(高分化)、NEC(低分化)に分類される。 - 5
良性はインスリノーマが多く、それ以外は悪性が多い。
- 1
- 81.3(BC)
- 【婦人科】の解答
-
- 101.1(AB)
- A
グリコーゲンを蓄積するのは基本的には中層細胞。分娩後は基底細胞にグリコーゲンが蓄積する。 - B
デーデルライン桿菌の出す乳酸によって酸性に保たれる。
- A
- 102. 5(DE)
- A
ケラトヒアリン顆粒がみられやすいのは表層細胞。 - B
月経期にみられる。 - C
カンジダではなく、トリコモナスとの共存が多いとされる。
- A
- 103.1(AB)
- A
酢酸加工後にみられる所見。白斑は加工前にみられる。 - B
扁平上皮部分は淡紅色の上皮がみられる。ブドウの房状にみえるのは円柱上皮部分。 - E
モザイクなどの異常所見をみることもある。
- A
- 104.4(CD)
- A
未分化生殖腺から発生する。 - B
尿生殖洞から発生する。 - C
ミュラー管から発生する。 - D
ミュラー管から発生する。
- A
- 105.4(CD)
- A
多段階発癌形式。エストロゲン非依存性がde novo発癌。 - B
子宮体癌の原因のほとんどはエストロゲンの過剰。妊娠中はプロゲステロン優位なので妊娠が多い多産の人は妊娠経験が無い未産婦の人より子宮体癌になりにくい。 - C
タモキシフェンは乳癌の治療薬として使われるが、子宮体癌のリスクを上げる効果があるため注意。
- A
- 106.3(BC)
- A
軽度異形成では上皮の基底側1/3に異常細胞が認められる。 - B
軽度異形成には約80%、中等度、高度には約90~100%、上皮内癌ではほぼ100%の陽性率がみられる。 - C
CIN2は約10%程度がCIN3に進展する。CIN1は約10%程度がCIN2に進展する。 - D
HPV関連腫瘍の代替マーカ―はp16。 - E
細胞診に関連するHPVの重要な遺伝子はE4,E6,E7の3つ。
・E4
ケラチンを分解することによって、顕微鏡下ではコイロサイトーシスとしてみることができる。
・E6
p53の分解を促進して細胞周期を進行させる。
・E7
Rbを不活化して細胞周期関連の蛋白発現を転写レベルで亢進させる。
- A
- 107.2(AE)
- A
妊娠性が多い。 - B
水腫状の変化は認めるが、栄養膜細胞の異常増殖は認めない。 - C
アジアに多い。アジアに多いか、欧米に多いかなどの地域差は総論に出題されることがあるため、一か所にまとめておくと使える。 - D
雄核発生は全胞状奇胎。
- A
- 108.3(BC)
- A
上皮性腫瘍-良性腫瘍 - D
性索間質性腫瘍-悪性腫瘍 - E
胚細胞腫瘍-良性腫瘍
- A
- 109.5(DE)
- A
分葉状頸管腺過形成(LEGH)を背景とする。 - B
予後不良。 - C
高分化な癌。 - D
粘液を持つ腫瘍は大体境界明瞭。 - E
胃型粘液は黄色。
- A
- 110.2(AE)
- A
平滑筋腫には転移性平滑筋腫が存在する。 - E
癌肉腫はポリープ状の腫瘤を形成する。
- A
- 111.2
産褥期はホルモンの影響は無い状態であるため、傍基底優位の左方移動を示す。- 1
中央移動 - 2
左方移動 - 3
左方、中央移動 - 4
右方移動 - 5
右方移動
- 1
- 112.3
絨毛癌は化学療法が主体。 - 113.3
クラミジアの代表的所見は星雲状封入体。 - 114.2
- 1
外陰の扁平上皮癌はHPV関連の類基底細胞癌、コンジローマ様癌とHPVが関連しない高分化扁平上皮癌などがある。 - 2
外陰類基底細胞癌はHPVに関連し、HPVに関連するものは比較的若年者に多い。 - 3
パジェット病は10%程度は浸潤性病変を示すが、扁平上皮内に限局するものが多い。 - 4
膣病変が子宮頸部におよぶものは子宮頸癌、外陰におよぶものは外陰癌に分類される。 - 5
悪性黒色腫は大体予後不良。
- 1
- 115.4
- 116.4
- 1
鋸歯状変化(グネグネした形)をみるのは分泌期。 - 2
核下空胞は分泌期前期にみられる。 - 3
脱落膜変化を示すのは内膜の間質細胞。上皮細胞はアリアス・ステラ反応を示す。 - 5
核の偽重層化は増殖期にみられる
- 1
- 117.5
放射線照射後の細胞は比較的何でもあり。そして大体悪そうな変化を示すことが多い。「N/C比に変化は無い」など、放射線によって起きない変化を覚える方が早い。 - 118.3
シラーデュバル小体や好酸性硝子様球体の出現が特徴的。成熟リンパ球は未分化胚細胞腫でみられる。 - 119.14
大部分が明細胞癌と関連するが、類内膜癌との関連もある。 - 120.45
- 101.1(AB)