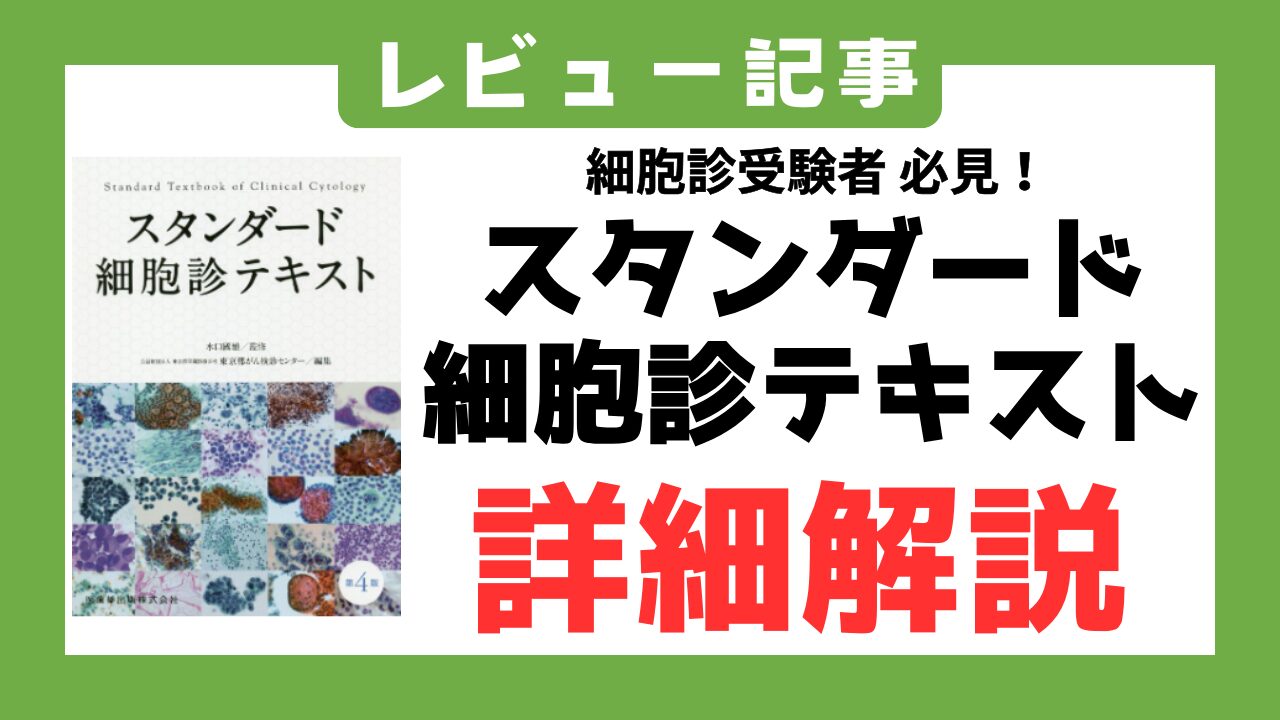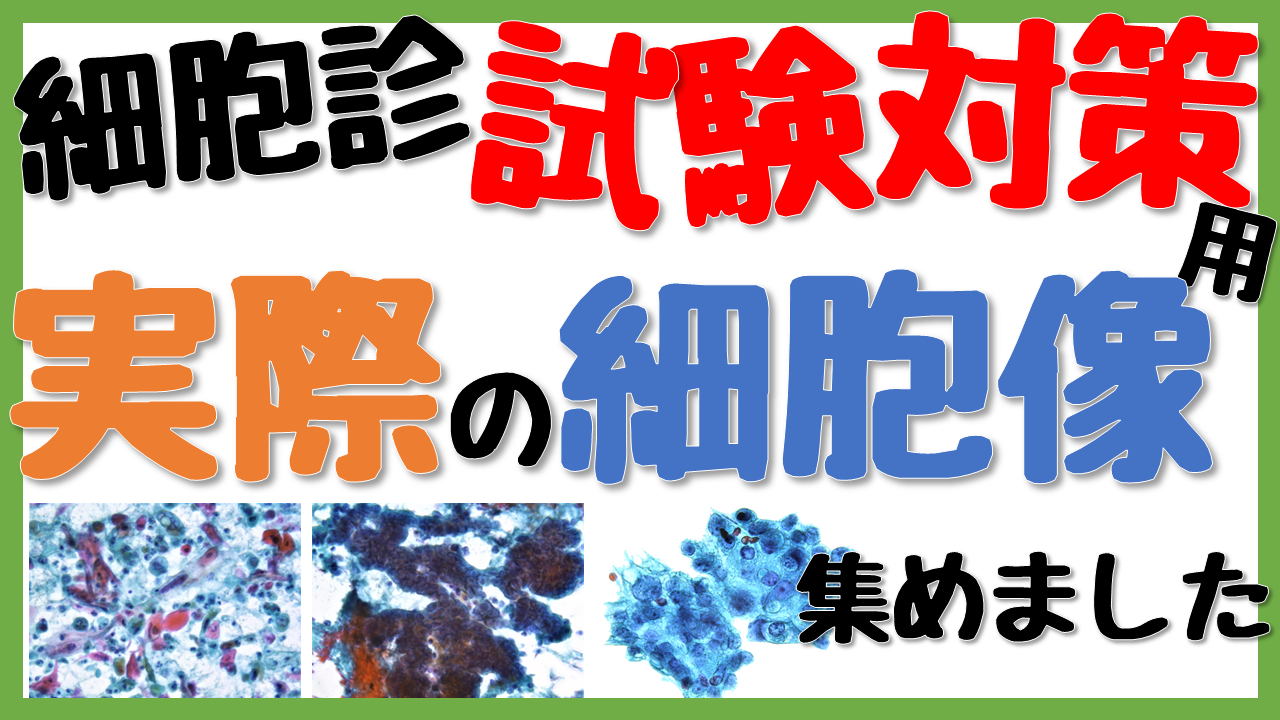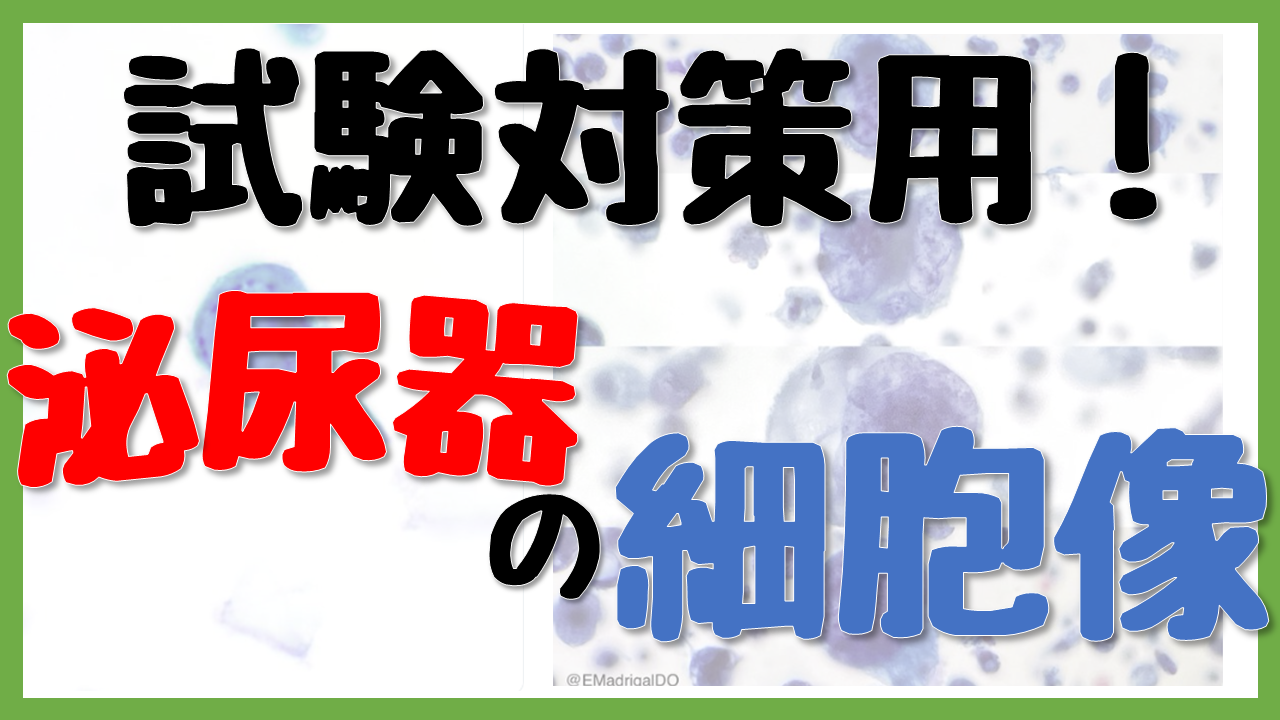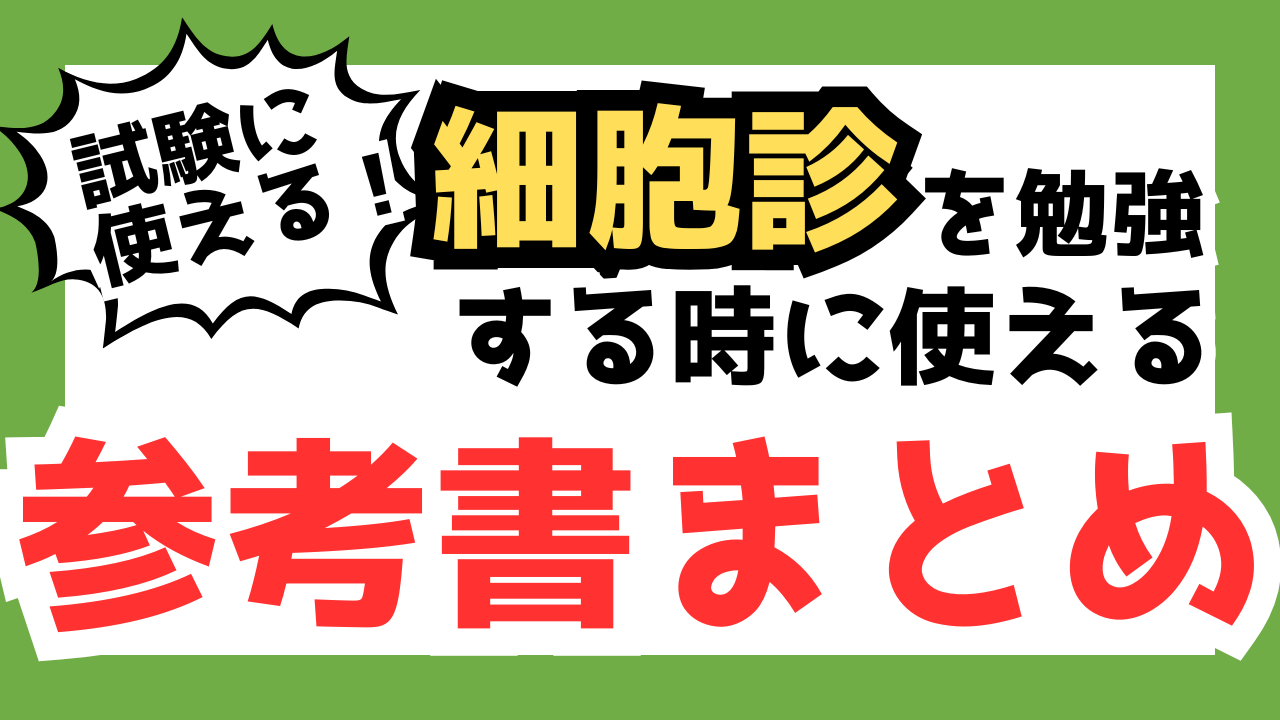細胞診検査士試験のよくある質問と回答 Q&Aコーナー
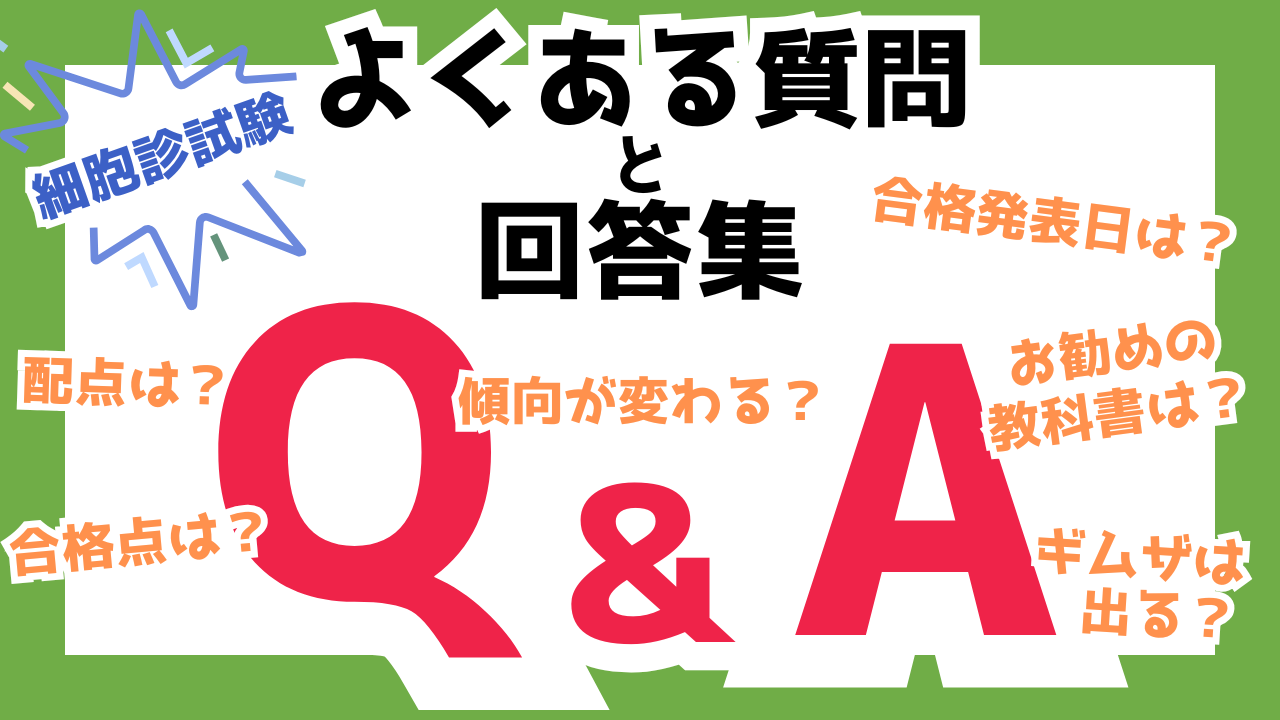
今まで3000件以上の細胞検査士試験に関する質問回答をしてきましたが、重複しているものが多くあります。
それらの中でも特に多い質問をここにまとめています。

疑問があるときはまずここを見てみてね!
質問がある方は下URLからお気軽にどうぞ
https://mond.how/ja/dot_zebra
試験内容・配点・基準について
- 試験日程はいつ出ますか?
-
毎年ばらつきはありますが、大体7月あたりです。
細胞検査士ホームページを随時ご確認してみてください。
- 願書の受付はいつから開始ですか?
-
毎年大体8月初旬から開始です。
細胞検査士ホームページを随時ご確認してみてください。
- 細胞検査士試験の合格点は何点ですか?
-
公式な発表はありませんが、一次試験は全体の70%です。
二次試験は固定されておらず65%前後で推移しているように思われます。
- 一次試験の配点は?
-
筆記が600点、細胞像が300点です。
この配点から一次試験の戦略が考えられます。
- 二次試験の配点は?
-
同定150点、スクリーニング250点です。
この配点から二次試験の戦略が考えられます。
- 一次試験は画像問題も筆記も両方7割を超える必要がありますか?
-
公式な発表はありませんが、おそらく全体で70%です。
しかし筆記は6科目中1科目でも50%を下回るとその時点で不合格です。
年度によって試験のシステム変更もありえますので受験する年の要綱を必ず確認してください。
- 二次試験の合格基準は?
-
二次試験は明確な合格基準は分かりません。毎年の結果を見ると65%前後で推移しているように思われます。
- 一次試験は合格、二次試験不合格の場合はまた一次試験からの受験ですか?
-
一次合格、二次不合格の場合、次年度のみ一次試験が免除です。
- 細胞診の合格率は何パーセントですか?
-
年度によって違いますが、2014年から2024年の11年間の平均は一次試験が51.24%、二次試験が56.87%です。
年度ごとに関しては合格率を年度別にまとめた記事をご覧ください。
- 今年の細胞検査士試験は傾向が変わりますか?
-
分かりません。
受験者は毎年傾向が違うと言うので、受験時は傾向が変わると思って過去に出たことない知識も入れた方が良いと思います。
- 一次試験、二次試験の結果発表は試験から何日後にありますか?
-
年度によってばらつきがあります。
●一次試験
・2022年度:試験から16日後
・2023年度:試験から17日後
・2024年度:試験から16日後
●二次試験
・2022年度:試験から15日後
・2023年度:試験から23日後
・2024年度:試験から15日後※二次試験は2日目終わりから計算
- 細胞診試験はどんなスケジュールを立てるのが良いですか?
-
まずは試験情報を手に入れてから過去問を使った一次試験対策をお勧めします。
月ごとのおすすめスケジュールを記載した記事がありますのでそちらも参考にしてください。試験対策に使えるチェックリストもまず最初に確認していただきたいです。
【一次試験対策について】
- 過去問を解けば合格できますか?
-
過去問だけでは合格できません。
関連する周辺知識は最低限覚えてから挑んでください。
過去問解説集を使って勉強すれば最低限の周辺知識だけでなく、傾向も掴むことができます。
時間はかかりますが、全ての周辺知識を自分で調べてももちろん勉強になります。
- 最新の細胞診過去問はいつ頃発表されますか?
-
例年1月のおわり頃か2月のはじめ頃に出る「イエローページ1月号」に掲載されます。日本臨床細胞学会のイエローページで見ることができます。
- 過去問解説集だけやれば筆記は合格できますか?
-
過去問解説集だけというのはお勧めできません。
最低限の目安として過去問解説集をお使いください。
- ノートにまとめるのと過去問解くのはどちらが先が良いですか?
-
過去問を解く方がお勧めです。
過去問は最低限必要な知識が詰め込まれています。
それを”覚える”のが優先です。
ノートにまとめるのは時間がかかるのと知識の定着効果が薄いためお勧めしていません。
1日でも早く過去問に手をつけ、周辺知識も含めて頭に入れてください。
- 本を熟読するのは良い勉強法ですか?
-
人によりますが、覚えられるのであれば本を読むでも良いです。
しかし、現存する細胞診勉強用の参考書は内容がアップデートされておらず、試験に対応できない内容が多い点には注意してください。
必要な参考書全てに目を通す必要があります。2025年現在で最新の本は【細胞診のすすめ方】です。
~基礎から学ぶ~ 細胞診のすすめ方〈第5版〉
- 教科書のおすすめはありますか?
-
2025年現在で最新の本は~基礎から学ぶ~ 細胞診のすすめ方〈第5版〉です。
おすすめの理由とその他のお勧め書籍については下の記事をご覧ください。
社会人必見! 細胞検査士試験に最適な参考書を全て紹介
- 細胞像対策のおすすめ書籍はありますか?
-
実際の過去問が収録された「細胞検査士細胞像試験問題集 第2版」が最もおすすめです。
そのほかは細胞診像対策におすすめの書籍とサイトを紹介した記事をご覧ください。
- 過去問解説集は問題や文字の検索はできますか?
-
できます。
具体的なやり方(iPhone ver.)は以下の動画で説明しています。
デバイスによっては検索方法が異なりますのでお持ちのデバイスの検索方法をお試しください。
【二次試験対策について】
- スクリーニング試験の①正常または良性②問題とすべき細胞〜③悪性細胞〜の選択肢はどのように区別するものなのでしょうか?
-
基本的に
①診断名に影響しないもの
②診断名に影響するが悪性ではないもの
③悪性
と考えてもらえれば対応できると思います。
- 二次試験対策は何をすれば良いですか?
-
とにかく標本を見て【慣れる】ことが重要です。
同じ疾患でも症例が異なれば違う見え方をすることがあります。その多様性にいかに対応できるか、そして時間内に見つけることができるかが二次試験突破の鍵です。
それらは【慣れ】によるところが大きく、標本の数および種類をどれだけ見ることができたかに依存することが多いためできるだけたくさんの標本を見てください。
- 二次試験で感染症も無い完全なNILMが出ることはありますか?
-
可能性はあります。
- スクリーニングで陰性標本を自信を持って陰性にできるようにするにはどうすれば良いですか?
-
陰性の像を確実に頭にインプットしてください。
それをするために陰性標本を多めに見てください。診断基準が崩れた場合も陰性標本だけをたくさん見るのがお勧めです。
- スクリーニングで見落としを防ぐ効果的な練習方法はありますか?
-
弱拡大でピックアップする細胞の基準を明確にしてください。
例えば、色の濃さや大きさなど分かりやすいものです。基準が明確になったら今までよりも強めに取ってみてください。
気になる細胞が今までよりも増え、鏡検時間は増すかもしれませんが見落としは防ぎやすくなります。
- カンジダやトリコモナスが見つけられません。どうすれば見つけられますか?
-
常に意識することが重要です。カンジダは数が少ない場合意識していなければ見逃します。
トリコモナスは目立たないことがあるため意識しないと見逃します。
この2つはSTDで比較的若めの年齢の人でみられやすいと思います。
そのため高齢者の場合は意識を外すというのも一つの手です。
- 鏡検するスピードがなかなか上がりません。どうすれば良いでしょうか?
-
スピードを意識した練習と細胞を確実にピックアップする練習を分けて行ってください。
スピードを上げるにはそのスピードに目を慣らす必要があります。
正確にピックアップできなくても良いので決めた時間で流し、そのスピードに目を慣らす練習をしてください。
- スクリーニングでは縦に見るのと横に見るのはどちらが良いですか?
-
どちらでも大丈夫です。
私は全て縦に見ますが分野によって変更する人もいます。
例えば婦人科は横、体腔液は縦などです。一般的に横で見る方が折り返し数が少なく、時間を短縮できる傾向にあります。
- スクリーニングで設問1、2は正解で設問3の組織型が違う場合は0点ですか?
-
ある程度の点数はもらえると思いますが、正確な採点方法は発表されていないので分かりません。
- 同定とスクリーニングは出題分野は同じですか?
-
違います。
ぜひ二次試験に出題される可能性が高いものをまとめた記事をご覧ください。出題範囲は公開されていませんが、試験の性質および今までの傾向からある程度範囲を予測することができます。
- スクリーニングと同定の分野の内訳は?
-
スクリーニングは婦人科8問、呼吸器6問、消化器3問、体腔液・尿・その他8問です。
同定は分野の内訳は不明です。
- 二次試験でLBCは出ますか?
-
過去に出題はあります。
今後も出る可能性があります。
- 二次試験でギムザ染色はでますか?
-
出ます。
今年も出るかはわかりませんが出題の可能性は十分あるので対策をしておいてください。
- 婦人科の高度異形成と微小浸潤癌を間違えてしまいます。鑑別方法はありますか?
-
現在、微小浸潤癌は組織型から除外されています。
試験で鑑別する必要はありません。
- 二次試験に出るものは決まっていますか?
-
ある程度決まっています。
ぜひ二次試験に出題される可能性が高いものをまとめた記事をご覧ください。
- 二次試験の同定とスクリーニングは何択ですか?
-
例年通りであれば同定は5択程度、スクリーニングは9択程度です。
- 「同定試験」「スクリーニング試験」とは具体的にどのような試験のことですか?
-
●同定試験
狭い範囲を90秒で鏡検し、選択肢から答えを選ぶ試験。●スクリーニング試験
標本のほぼ全範囲を5分で鏡検し、選択肢から答えを選ぶ試験。一つの症例に対して設問が大きく3つある。さらに詳細な情報が知りたい方は試験に関する情報を全てまとめた記事をご覧ください。
- 二次試験のスクリーニングや同定は標本固定で人が動きますか?それとも人が固定で標本を回しますか?
-
例年通りであれば標本を回します。昔は標本が固定で人が動いていたので変更もありえます。
- 二次試験の問題数はいくつですか?
-
例年通りであればスクリーニング25問、同定30問です。
ちなみに第53回まではスクリーニングも同定も30問でした。
- 顕微鏡を見ていると酔います。解決策はありますか?
-
見る方向を変えてみると改善されるかもしれません。
例えば今縦に見ているのであれば横に見る。またはその逆です。
今まで酔う人をたくさん見てきましたが、多くの標本を見るうちに酔わなくなる人がほとんどです。慣れもかなり影響すると思うので頑張ってたくさん見てみてください。
【勉強環境やメンタル】
- 勉強していると周囲の音や動きが気になって集中できません。どうすれば良いでしょうか?
-
どうしても気になる場合は一人になれる場所で勉強してください。
ただ、本番は人がたくさんいて音や動きも目に入ります。
試験対策として、周囲の音や動きが目に入っても集中できるだけの集中力を身につけることを私はお勧めします。
- 試験を受けまだ結果が出ていませんが、落ちた気がします。応援してくれた職場の人に合わせる顔がありません。どうすれば良いでしょうか。
-
全然大丈夫です。
応援してくれた人のことは気にしなくてOK。
もしダメだったとしても手伝ってくれた人は何とも思っていません。また、結果は出るまで分からないのでし、受かったと想定して少しでも早く二次試験の対策を始めてください。
おそらく一次試験ももう少し早く始めればよかったって思っていると思うので、受かってた時のために二次試験の準備を早く始めた方が良いです。
とにかくお疲れ様でした(^^)
よく頑張りました!
- 働きながら一発で一次試験、二次試験ともに合格する人はいますか?
-
いますがかなり少ない印象です。
例えば2022年度55回の一般受験者合格率は21.7%です。この中には複数回目の受験者も含めているため一発で受かっている人は少なくともこの数字よりは少ないことになります。
- 2回連続で一次試験に落ちました。どうすれば良いでしょうか?
-
大丈夫です。
私が知る限り社会人受験者は2回以上受ける人の方が多いです。
全然普通のことなのでもしまだ取得したいと思う気持ちがあれば一緒に頑張りましょう!
【試験会場について】
- 学会場にスーツケースは持って行けますか?
-
試験会場によるかと思います。
試験会場は年度によって異なるため、日本臨床細胞学会のお問い合わせフォームから問い合わせてみることをお勧めします。
【試験に関連した知識】
- クッシング症候群や副腎腫瘍はなぜホルモン細胞診で中央移動するのでしょうか。
-
ここを理解するにはホルモンの合成過程を理解する必要があります。
プロゲステロンなどのホルモンは急に作られるのではなく、いくつかのプロホルモンと呼ばれる物質を経て合成されます。
クッシング症候群は最終的にグルココルチコイドの中のコルチゾールが増える疾患ですが、コルチゾールができる過程にプロゲステロンが作られます。
そのため、プロゲステロンが過剰となり中央移動になります。
実際、クッシング症候群や副腎腫瘍などの検査ではプロゲステロン高値という検査所見があります。
- 「ジアスターゼ消化性のPAS陽性」と「ジアスターゼ消化PAS陽性」の違いはなんですか?
-
グリコーゲンかグリコーゲン以外のPAS陽性物質かの違いです。
①ジアスターゼ消化性のPAS陽性=グリコーゲン
②ジアスターゼ消化PAS陽性=グリコーゲン以外上記以外にも以下のような言い回しがあります。
③ジアスターゼ抵抗性PAS陽性=ジアスターゼで消化されないPAS陽性物質=グリコーゲン以外
【顕微鏡以外でできる二次試験対策】
- 顕微鏡を見る以外二次試験対策としてできることはありますか?
-
下の3つは顕微鏡がなくてもできる二次試験対策としておススメです。
❶一次試験の知識を忘れない
❷所見を思い出す瞬発力を高める
❸出る疾患を知るさらに具体的な方法は「細胞検査士試験の徹底準備ガイド」も参考にしてください。