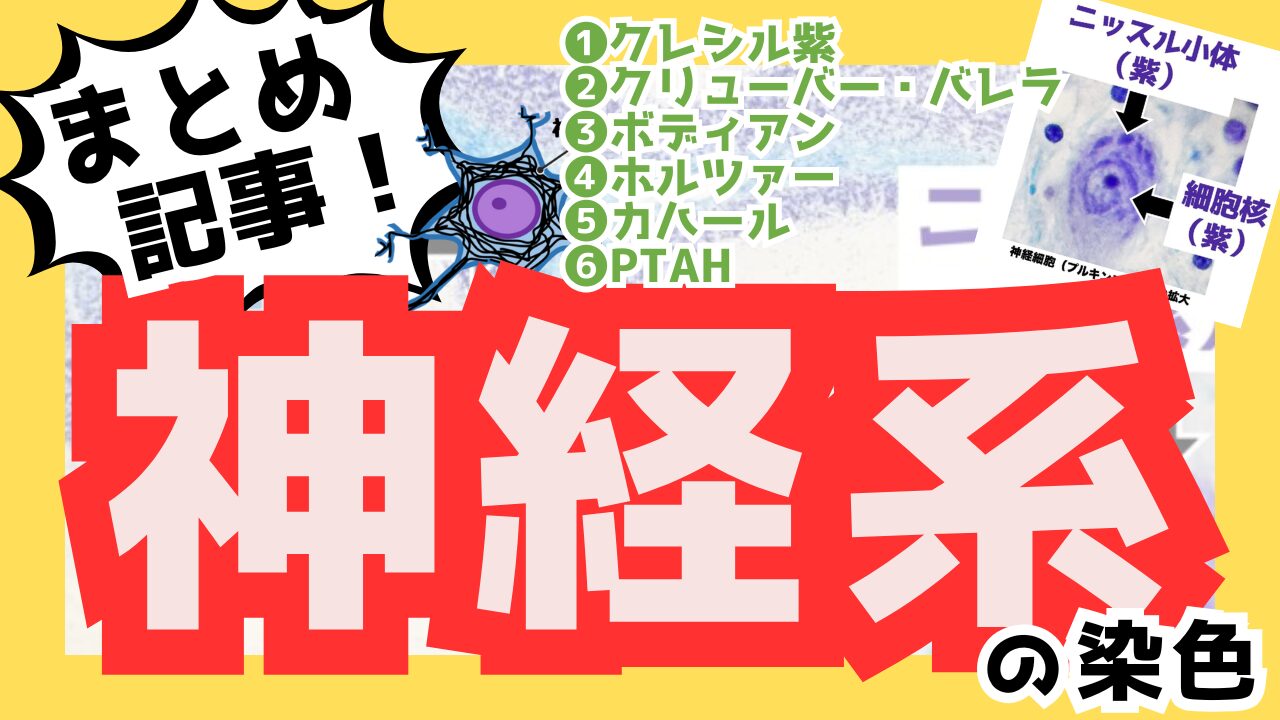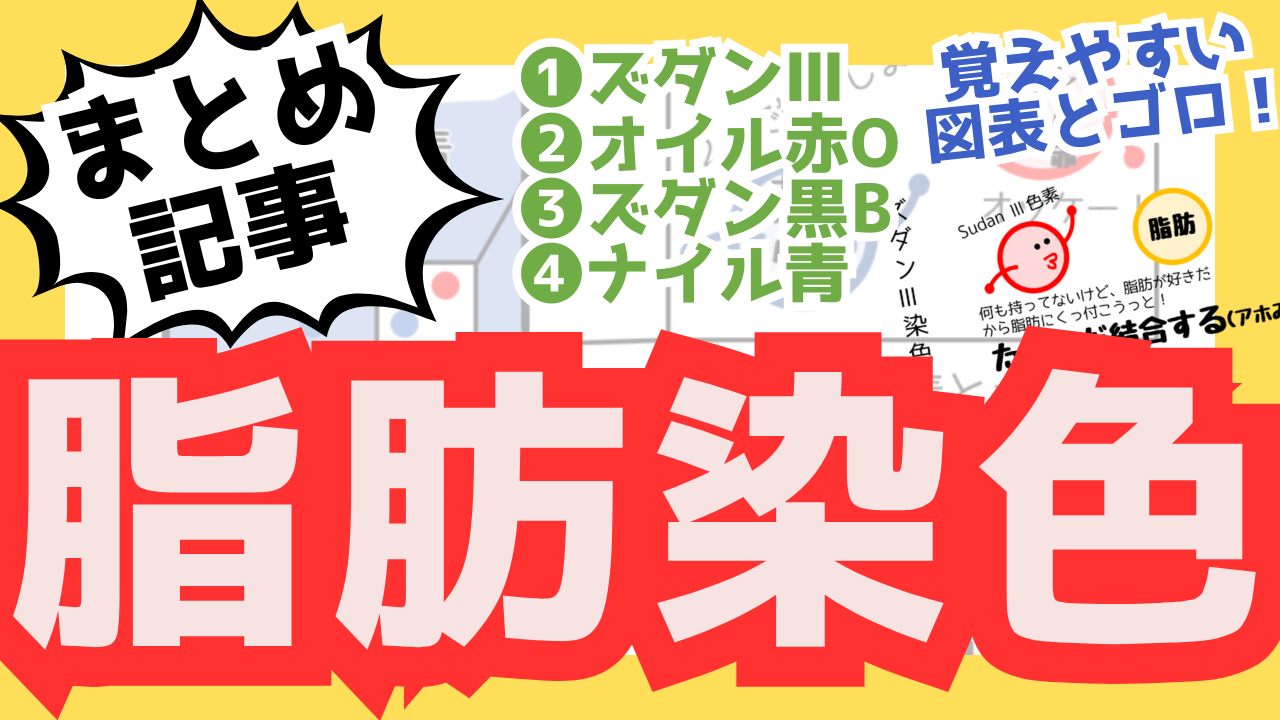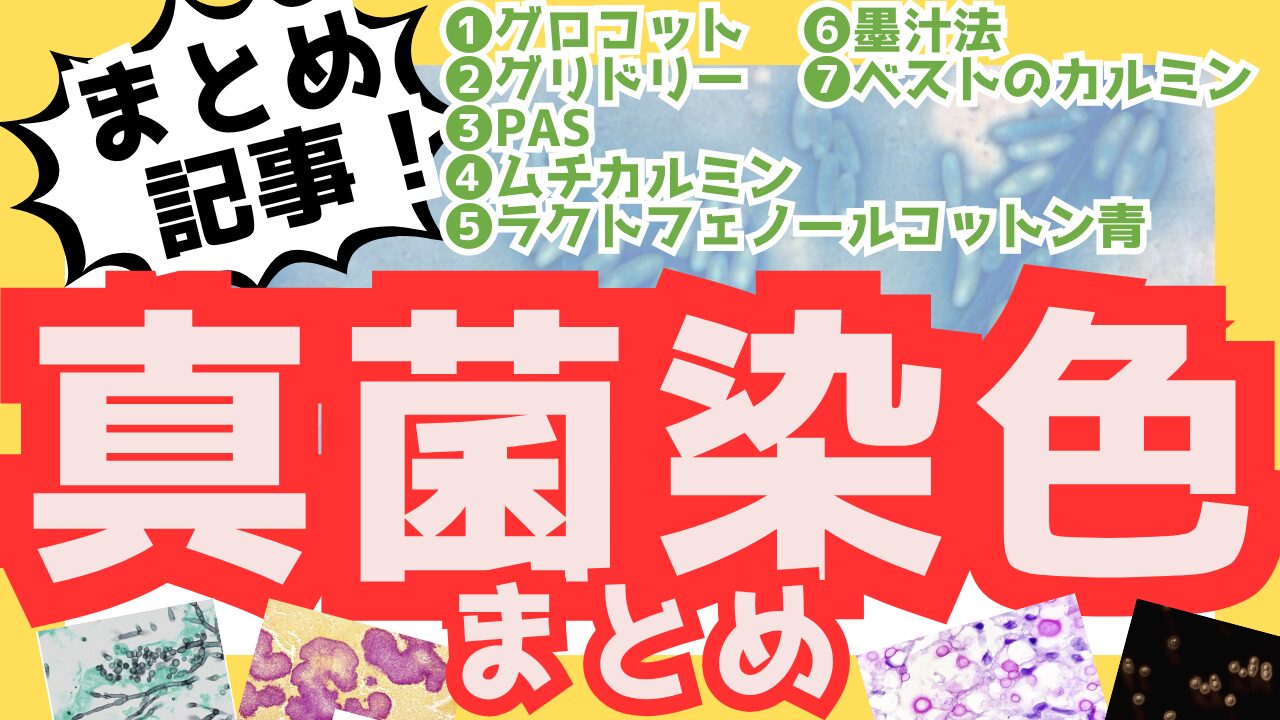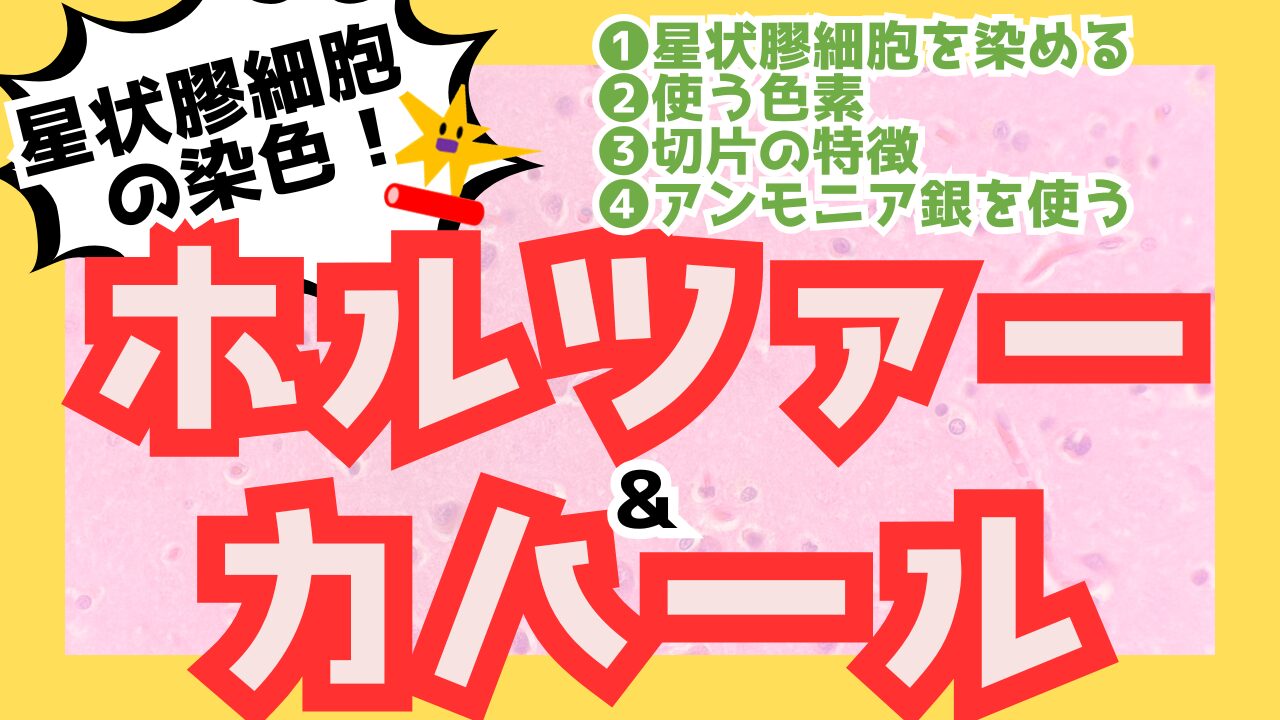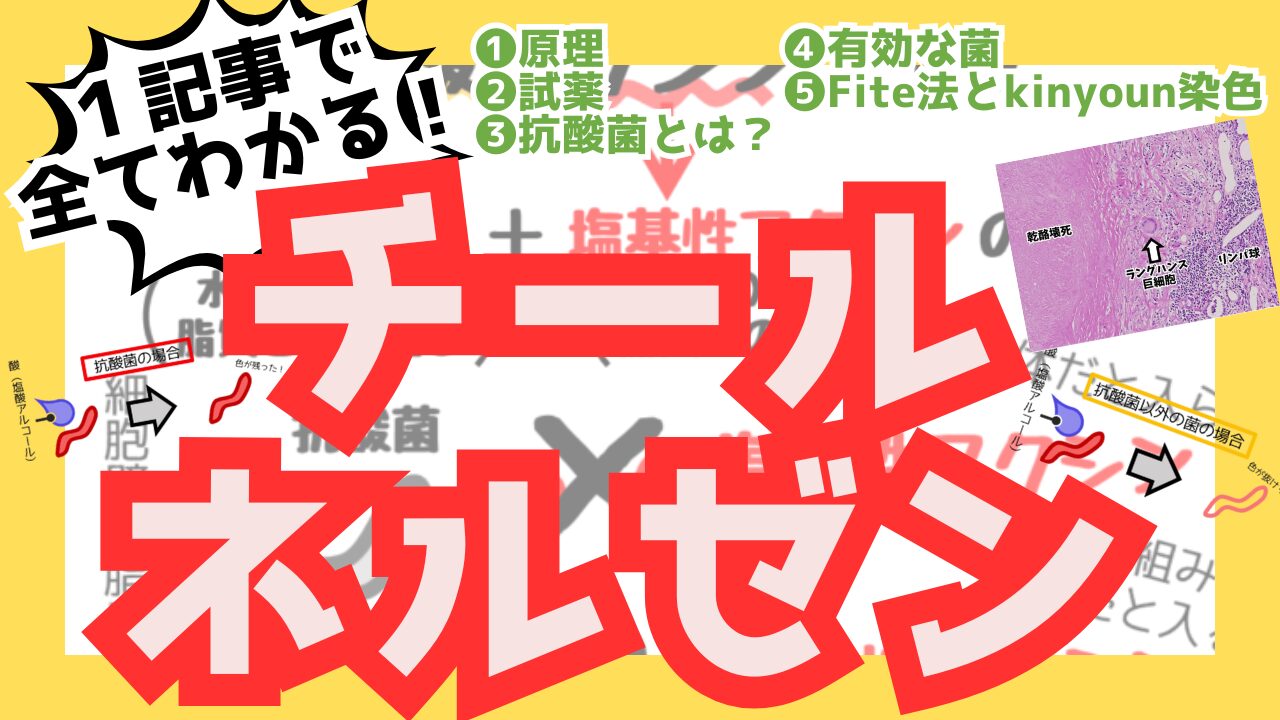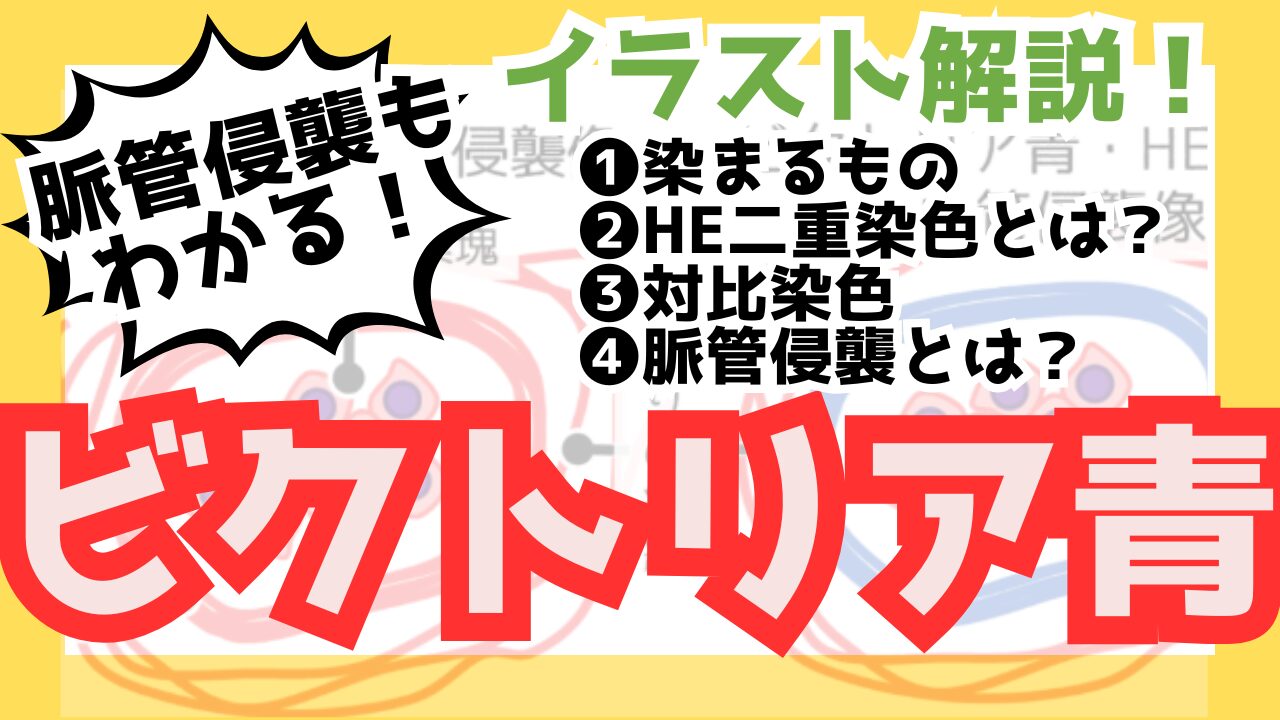【核酸の染色まとめ】❶フォイルゲン反応❷メチル緑・ピロニン染色❸ブリリアント・クレシル青染色❹X染色質染色❺マン染色
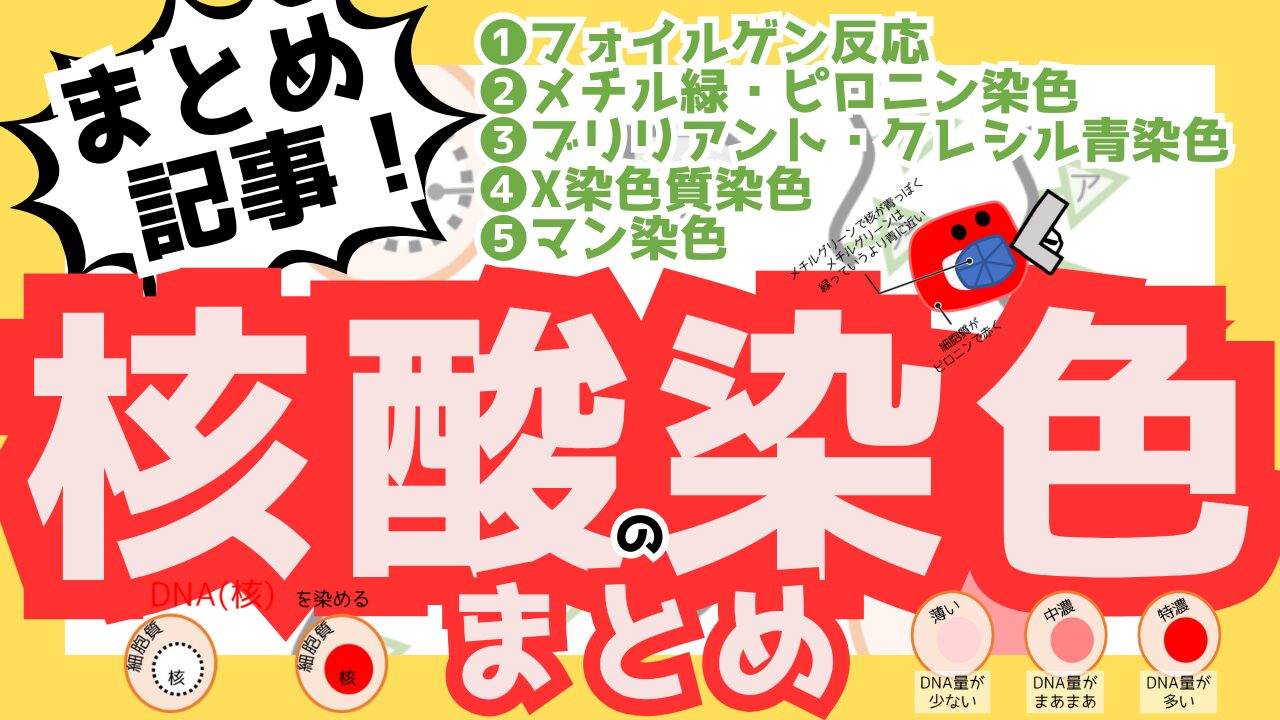
核酸とはDNAやRNAのことです。
DNAやRNAを特異的に染め出すことで、特定の疾患の鑑別などができます。
また、核小体やX染色質といった特定の核酸を検出する染色法もあります。
臨床検査技師国家試験では前者2つ、細胞検査士試験では後者も合わせた全ての染色をマスターしましょう。
核酸の染色5種類
- フォイルゲン反応
- メチル緑・ピロニン染色
- ブリリアント・クレシル青染色
- X染色質染色
- マン染色
- ヘマトキシリン
ヘマトキシリンはHE染色で解説したのでここでは割愛します。
❶フォイルゲン反応
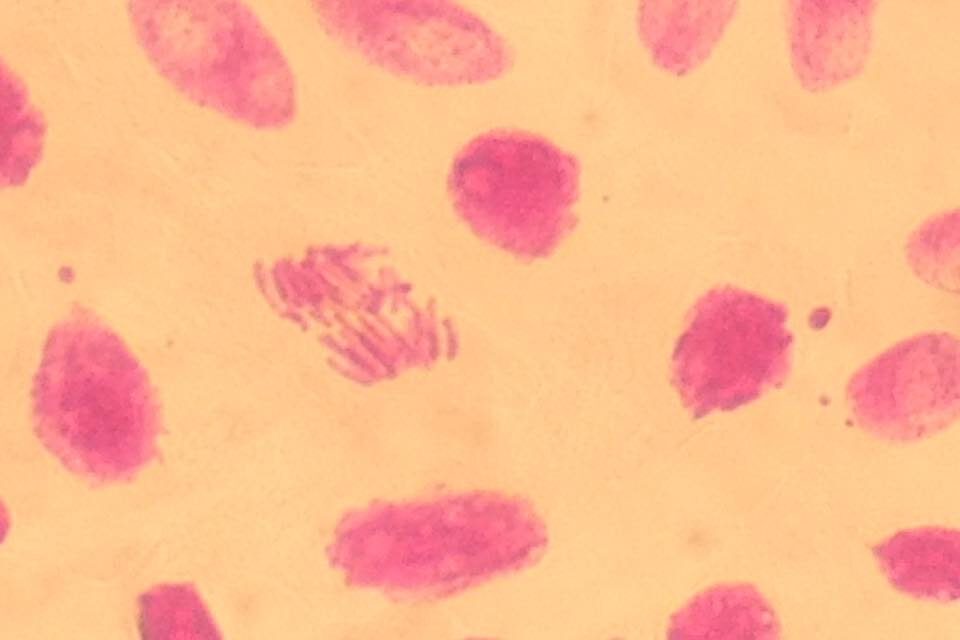
フォイルゲン反応の画像
フォイルゲン反応(Feulgen reaction)は塩酸とシッフ試薬を使ってDNAを染める方法です。
この染色の最大のポイントはDNAを定量できる点です。
- DNAを赤く染める
- DNA量を定量できる
- 原理がPAS反応と似ている
- 塩酸とシッフ試薬を使う
- 加温する
フォイルゲン反応の全体像
特に重要な点は赤文字にしています。
(水洗は省略)
- 脱パラ・脱キシ・親水
- 1N(1M)塩酸【加温:60℃】
(加水分解) - 1N塩酸
(洗浄) - シッフ試薬
(呈色) - 亜硫酸水
(洗浄) - 脱水・透徹・封入
フォイルゲン反応はDNAを染色・定量する
フォイルゲン反応はDNA(核)を染めます。
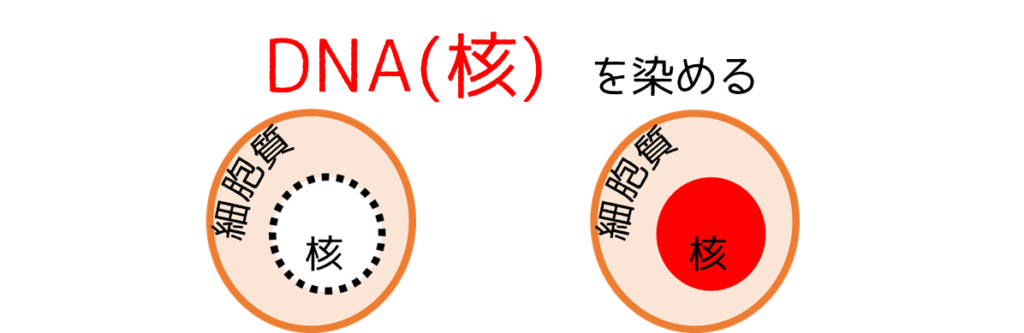
さらにこの染色の利点は染色強度がDNA量と比例することです。
つまりDNA量を色で定量できます。
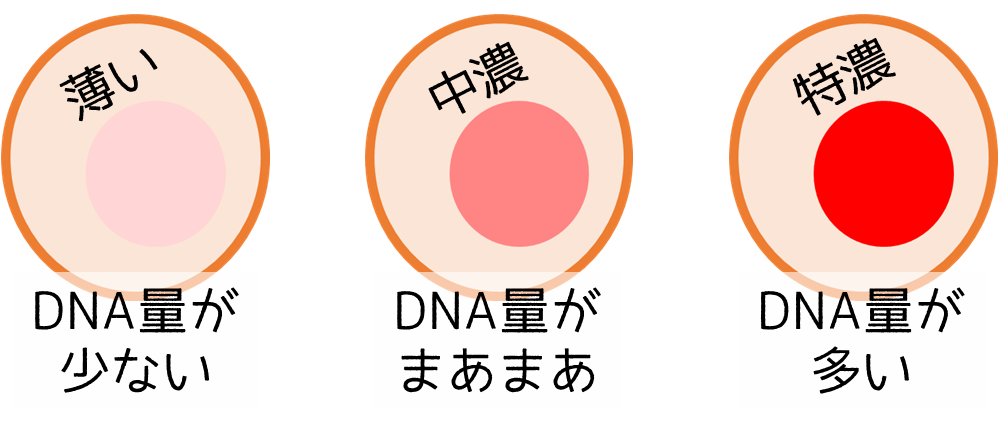
フォイルゲン反応の原理
フォイルゲン反応の原理はPAS反応とよく似ています。
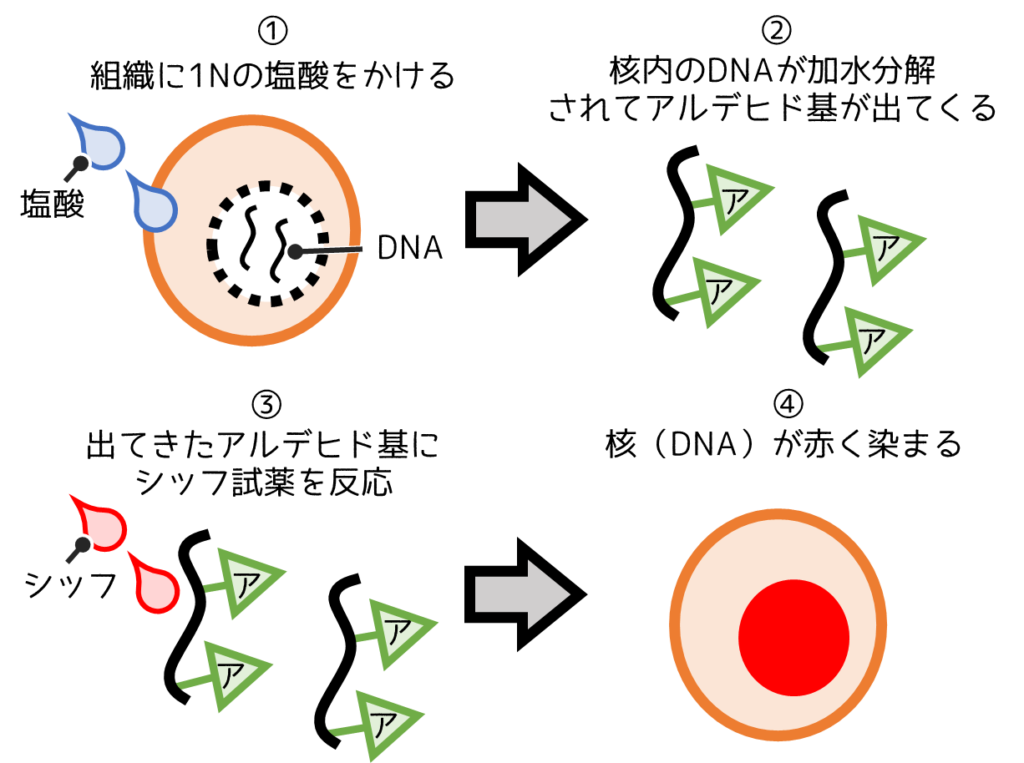
PAS染色と似た原理は全部で5種類あります。
試験にも出題されているので必ず覚えておきましょう。
シッフ試薬の組成も頻出なので確実に覚えましょう。
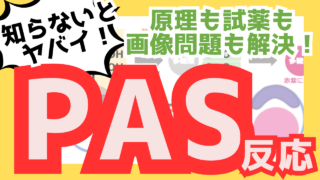
❷メチル緑・ピロニン染色
メチル緑・ピロニン(methyl green pyronin)染色は塩基性色素であるメチル緑でDNA、ピロニンでRNA(核小体や粗面小胞体)を染める染色です。
メチル緑という名前ですが、この色素の染色結果はほぼ青色である点は注意。
また、別名「ウンナ・パッペンハイム染色」とも呼ばれ、パッペンハイム染色(ギムザ染色)と混同させる問題が出題されます。
phが重要でpH4.2の酢酸緩衝液を使いますが、高い時と低い時は以下のような影響があります。
- pHが高い時:メチル緑に染まりやすい
- pHが低い時:ピロニンに染まりやすい
- 形質細胞の検出に有効
- メチル緑でDNAを青に染める
- ピロニンでRNAを赤く染める
- 両色素とも塩基性色素
- pH4.2の酢酸緩衝液を用いる
- 別名:ウンナ・パッペンハイム染色
メチル緑・ピロニン は形質細胞の検出に有効
形質細胞は抗体(免疫グロブリン)を作るB細胞性リンパ球です。
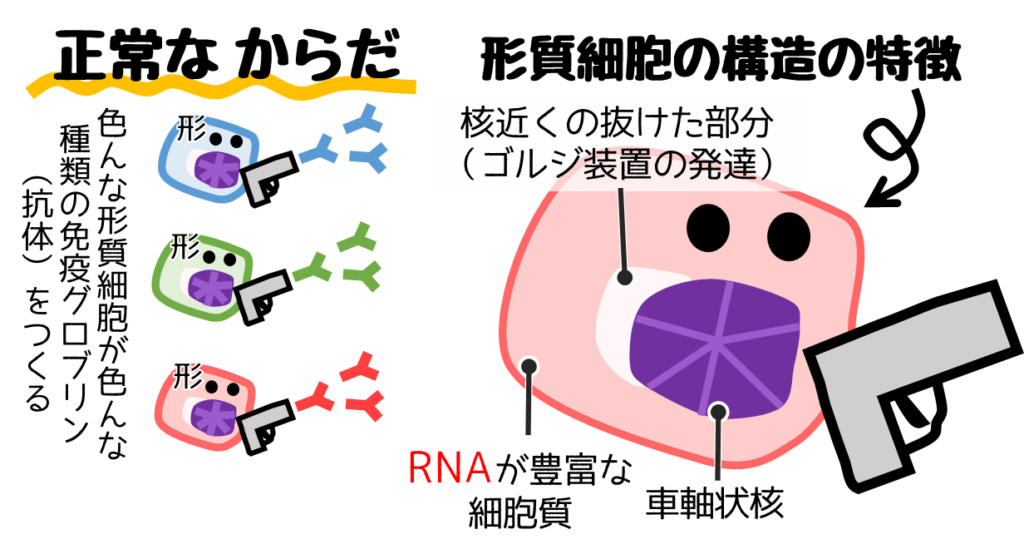
形質細胞の細胞質はRNA(粗面小胞体)が豊富で、核にはDNAが豊富に含まれています。
そのため、核(DNA)はメチル緑で青く染まり、RNAが多い細胞質はピロニンで赤く染まります。
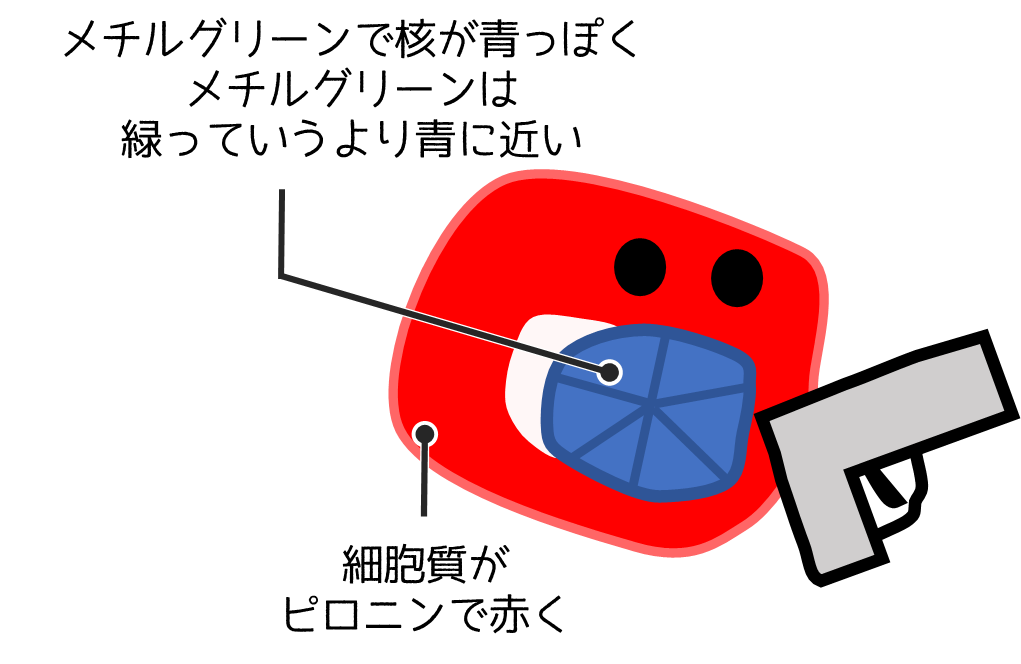
このように特徴的な染まり方をするため、形質細胞や形質細胞由来の腫瘍などの検出に有効です。
メチル緑・ピロニンが有用な疾患
形質細胞に有効なため、形質細胞が腫瘍化した多発性骨髄腫(形質細胞腫)に有効です。
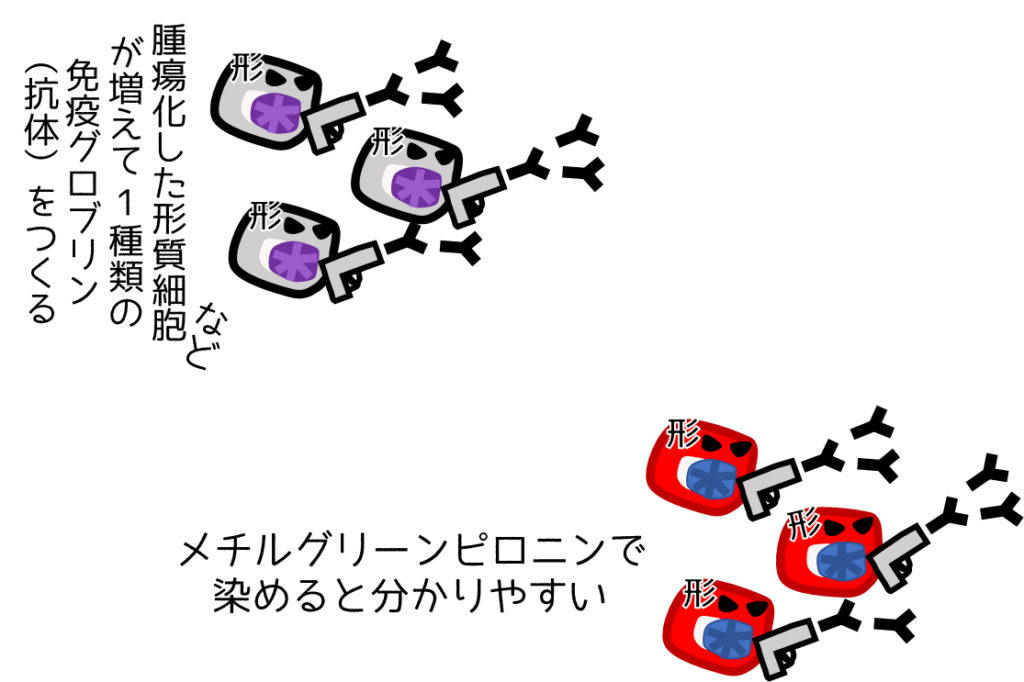
❸ブリリアント・クレシル青染色
ブリリアント・クレシル青(brilliant-cresyl-blue)染色は核小体を青く染める染色です。
超生体染色と呼ばれる方法の1つで、未固定の生きた細胞を染める。
- ブリリアント・クレシル青
核小体やハインツ小体など - インジゴカルミン
胃や大腸の内視鏡検査で使われる青色の色素。 - ニューメチレン青
網状赤血球 - ヤーヌス緑
ミトコンドリア(糸粒体) - 中性赤
細胞質内顆粒・空胞
❹X染色質染色
X染色質(X-chromatin)染色はその名の通り、X染色質を染める染色法です。
X染色体は2本(ヒトにおける女性の染色体)以上ある場合、1本が不活性化しています。
この現象はライオ二ゼーションと呼ばれ、凝縮して不活性化したX染色体は
【X染色質】【Xクロマチン】【バー小体】
などと呼ばれます。
このX染色質は塩基性色素のクレシル紫で染めることができます。
X染色質は核膜に接して存在しているのが特徴的です。
X染色体の数によってX染色質の違いがあります。
- X1つ(正常男性)
45, XY
X染色質:0 - X1つ(ターナー症候群)
45, XO
X染色質:0 - X2つ(正常女性)
46, XX
X染色質:1 - X2つ(クラインフェルター症候群)
47, XXY
X染色質:1 - X3つ(トリプルX)
47, XXX
X染色質:2
❺マン染色
マン(mann)染色は核小体を赤、クロマチンを青紫に染める染色です。
核小体はエオジン、クロマチンはメチル青で染めます。
核酸の染色に関する練習問題
問1
フォイルゲン反応の最大の特徴は何?
A.DNA量を定量的に評価できる。
B.メチル緑とピロニンという2種類の色素を使用する。
C.生きた細胞を染色する超生体染色である。
D.RNAを特異的に赤く染色する。
- 答えはここをクリック
-
A
問2
メチル緑・ピロニン染色における形質細胞の染まり方は?
A.核が赤色に、細胞質が青色に染まる。
B.細胞全体が均一に赤色に染まる。
C.細胞全体が均一に青色に染まる。
D.核が青色に、細胞質が赤色に染まる。
- 答えはここをクリック
-
D
問3
超生体染色に分類されるものはどれ。
A.ブリリアント・クレシル青染色
B.メチル緑・ピロニン染色
C.フォイルゲン反応
D.X染色質染色
- 答えはここをクリック
-
A